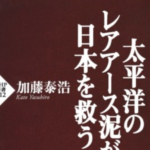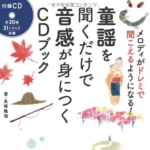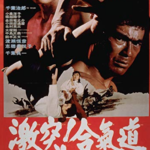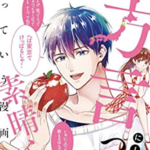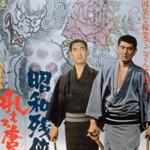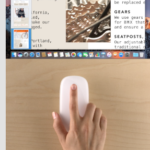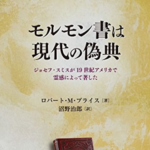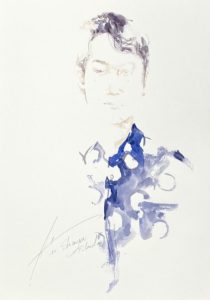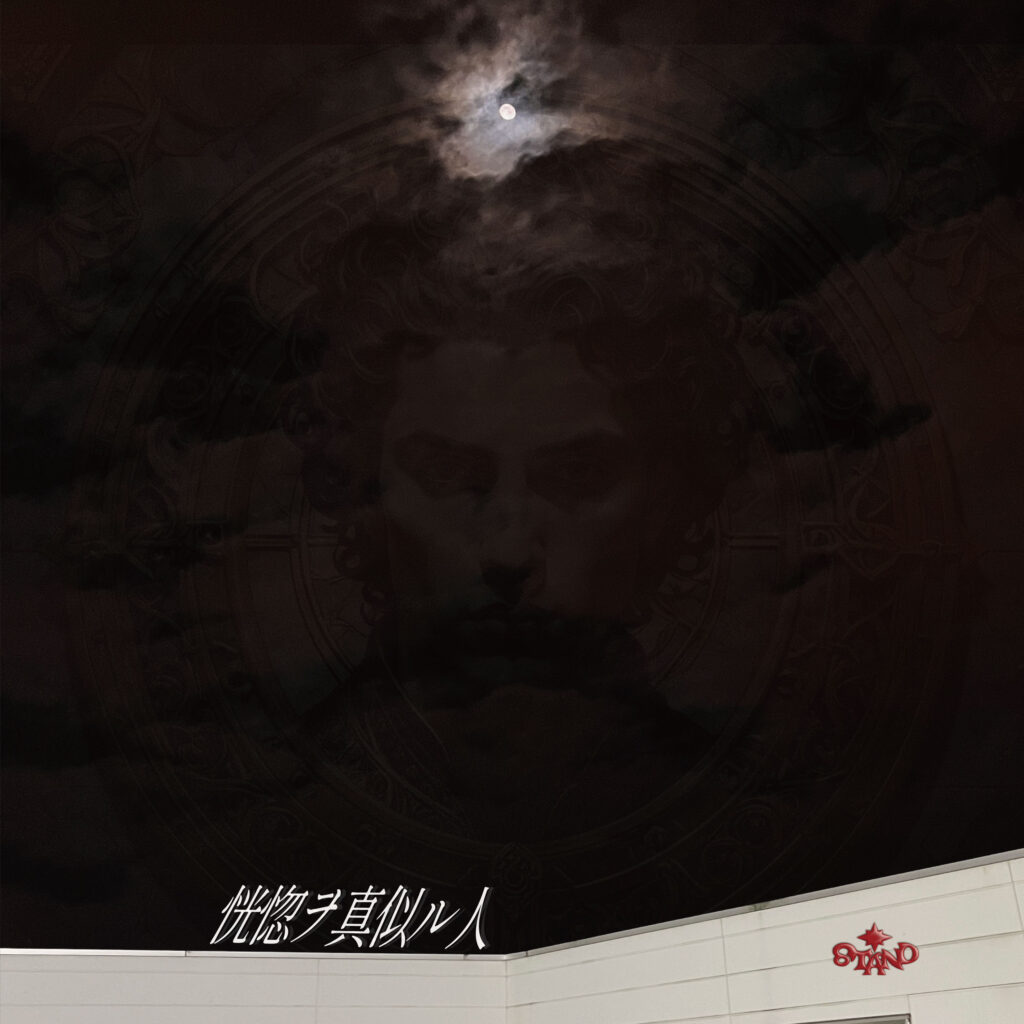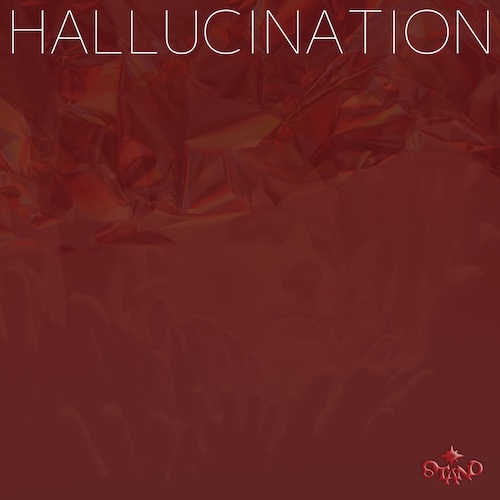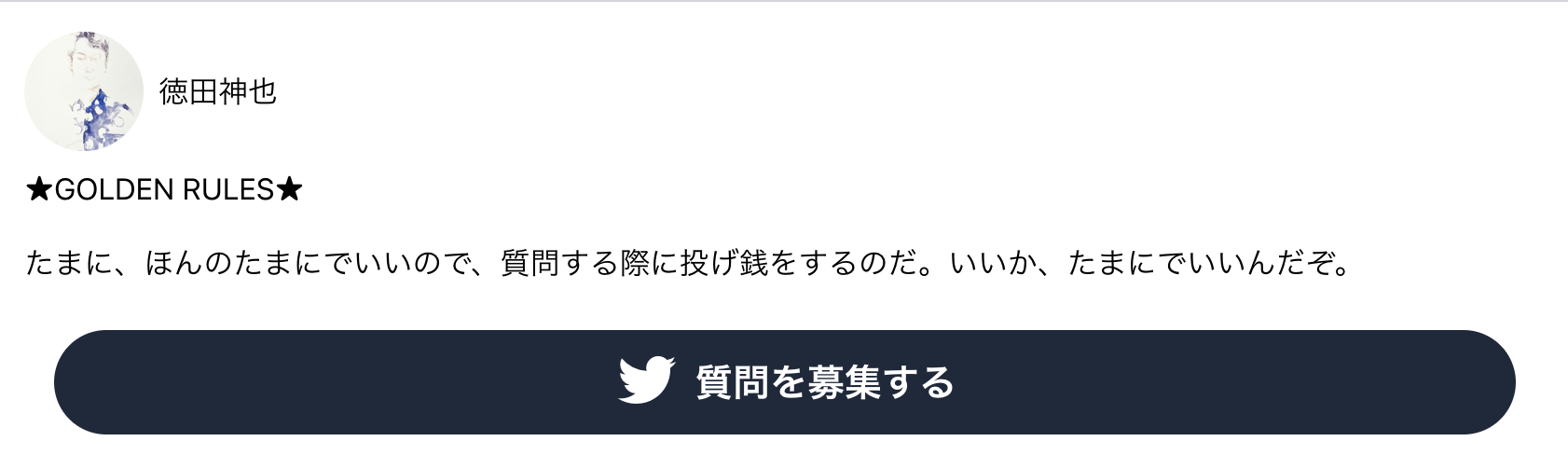日本での酒造りの起源は、紀元前1,000年前後までさかのぼることができる。
縄文式竪穴から酒坑が見つかっている。
庶民にが日常的に飲酒の習慣を持つようになったのは日清・日露の戦いの頃で、兵士が戦地での祝杯の習慣を持ち帰ってからだ。
それまでは、酒は「ハレ」の日だけに飲む特別なご馳走だった。
同緯度の国にもない湿潤な気候が、日本の酒を特別なクオリティのものへと進化させていった。
※酒造メーカー独自の、蔵じたいに生存する「家つき酵母」などは、一度廃業すると再現が難しい。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
斎藤孝監修。自然、歴史、文学、科学・技術、芸術、伝統・文化、哲学・思想の7分野からの、日本にまつわる365日分の知識。この本をさらっと読み、知ってるようで知らなかったことをさらっと初めて知りつつ、ああそうなんだね~なんて知ったかぶりしながらほんの少しだけ、書くことを1年間続けます。最低限「350ページ以上ある本を読んだよ!」の事実が残るだけでも、価値はゼロではあるまいて。言わんや「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことかと。
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365