因果な稼業でござんすねぇ!って…誰のセリフなの…??
シリーズ第8作め。
ここへ来て鶴田浩二が登場するんじゃあ、パッケージもそうなっちゃいますよね…。
「唐獅子」というのは主人公・花田秀次郎(高倉健)の背中に入った、彫り物のデザイン、「唐獅子牡丹」のことです。「吠えろ唐獅子牡丹」は語呂が悪いからでしょうかね。ちなみにブルース・リーの「燃えよドラゴン」は本作の2年後の公開です。
激しい格闘シーンから始まります。
オープニングの時点では、なんの因果もわからない。
ただ、高倉健と松方弘樹が殴り込みをして、敵の組長を殺した…っていうところ。
最後のとどめを松方弘樹に譲ったところから、花田秀次郎(高倉健)は助っ人だったとわかります。
いつのまにかこのシリーズ、オープニングテーマに歌詞がなくなってますね。
やはりあの歌(歌唱・高倉健)は、最後の出入りの時にびしっと決めたい…という判断でしょうか。
文三(ぶんぞう・松方弘樹)と思いを寄せ合っていたおみの(光川環世)を、親分の黒田米吉(葉山良二)が横恋慕して、強引に奪ってしまいます。けっこう葉山良二はこのシリーズで、正義の役が多かったんですが、今回は若衆の女を手籠にした悪役、ですね。ラスボス。長いシリーズでは、こういう配役も楽しみの一つ。
舞台は長野へ。
昭和初期の設定なんですけど、なんだか風景も服装も、江戸時代のようです。近代的な部分が一切出てこない。
音楽も、わざと牧歌的なものが流れてくる。お地蔵さんがあって、振り分け荷物で草鞋・番傘・手甲脚絆、みたいな。
ここで、信州へ逃げた文三を追う、黒田組若衆・小岩(沼田曜一)ら3人プラス花田秀次郎による、仁義が切られます。
かように不躾ではなはだ失礼でござんすがお控えなさい。
ご当家の親分さんお姐さん、
陰ながらお許しをこうむります。向かいます上様とは今日こう初めてお目通りかないます、従いまして
手前、生国は前橋にございます。
縁持ちまして親分は黒田一家を名乗ります、
前橋黒住町に住まいする米吉(よねきち)若い者でございます。姓名の儀は小岩源七(こいわげんしち)と申します、
お見かけ通りの若年者でござんす、
行末万端よろしくお引き立てを、願います。
同じく、手前米吉若い者で、
姓名の儀は井岩又市(いいしまたいち・高野眞二)と申します。
同じく、手前米吉若い者で、
村井音松(むらいおとまつ・花田達)と申します。
手前、生国と発します、東京・浅草です。
渡世、つきましては、親分なしの子分なし。
縁持ちまして、前橋は黒田一家、米吉親分の客分に預かります。
花田、秀次郎と申します。
いちいち、ご丁寧にござんす。
仰せの通り、お初にござんす。手前、当家矢崎伊之助(やざきいのすけ)の若い者、
姓名の儀は尾関正八(おぜきしょうはち)と申します。
お見かけ通りのしがない者にござんす。
お見知りおかれまして万端よろしく、おたの、申します。さ、お上げなさいまし。
いいえ、上さんからお上げください。
では、ご一緒に。
この時の、挨拶を受ける矢崎組の尾関正八(中田博久)の、姿勢が、見たことのない姿勢なんです。
いわゆる土下座の形ではなく、両手を揃えて、重ねて中心で畳に指先をつけています。
正座ですらない。
蹲踞(そんきょ)というか、うんこ座りというか…これが挨拶の型。なんですかね。
こんな挨拶の姿勢が存在するなんて、まったく知らないですよね。
あまりにわかりにくいので、直接見ていただきたい。
開始、13分40秒あたりです。
そして今回は…勝手にキャプチャ画像を載せてしまうのは良くないのですが、一枚だけ、お許しいただきたい。
 中央でこちらに向いているのが座って尾関正八(中田博久)。
中央でこちらに向いているのが座って尾関正八(中田博久)。
これって、膝立ててますよね?正座ではない。
正座って、絶対に折り目正しい礼儀にかなった作法としての坐法だ、となったのは明治以降らしいですよね。諸説あるんでしょうけど。言われてみれば畳なんか一般家庭には江戸時代、そうそうないし、上流階級は確かに正座もしてたんでしょう。
そうなると、正座ができるのは贅沢な暮らしの象徴で、明治以前にはもっと、違った礼儀にのっとった坐法が一般的にはあったのかも知れない。そういえば、百人一首にしたって戦国武将の肖像画にしたって、正座をしているであろう姿は(着物で見えないけど)多分、皆無でしょう。これについては謎のままです、知ってる方がおられたら教えてください。
今回の「吼えろ唐獅子」では他にも、「作法」についての描写が出てきます。
文三(ぶんぞう・松方弘樹)探索のため、信州の矢崎組の客人となった黒田組の小岩・井岩・村井、そして花田秀次郎(高倉健)。
ここには、他にもすでに客人がゴロゴロしています。
「客間」で花田秀次郎は、筋の通った人らしく、挨拶をします。
ご一統さんにて御免をこうむります。
手前ご当家親分さんより、一宿のお付き合いをお許しいただきました、旅の者でございます。
なにとぞ、ご昵懇におたの申します。
これがちゃんとできる人って、すでに古風で、律儀な人なんだ、という描写なのだと思います。
黒田組の三人は、一切しません。
仁義は切りましたが、それは上辺だけのもの、ということなんでしょう。
筋金入りの花田秀次郎は、違うんですね。
そこへ先ほどの座り方をしていた尾関(中田博久)が
客人がた、トキノシノギです、どうぞこちらへ
と誘います。
時のしのぎ??
何それ。
これって、和食でいう「御凌ぎ(おしのぎ)」から来てるんですね。
定例の食事時間以外に食べる。つまりちょっとした軽食、空腹シノギに…っていう意味だと思います。
しかし劇中では、粗餐、みたいな感じの謙遜というか、
普通の食事のことを、「時のしのぎ」と言ってるような感じですね。
出てきたのは
イワシ、白米、タクアン2枚、味噌汁。
これを見て、横柄な黒田組の3人は「ひでえ扱いだな」「犬や猫じゃあるめえし」と陰口を叩きます。
ちゃんとしている花田秀次郎は、
ちゃんと「ご厚情に、預かります」と頭を下げます。
他の3人はいただきますも言わない。
客人たちの食事には世話係がついていて、おかわりの白米をよそってくれます。
ただ黙って空の茶碗を差し出す奴ら。
花田秀次郎が差し出した茶碗は、まだ普通に盛られているくらいの段階で、山の真ん中に穴が空いている。
????
それに対して世話役は
作法にかなったおかわり、恐れ入ります
と言うんです。
なんで?
全部食べてからが2杯め、っていうんじゃないの?
まだ1杯めも何口かしか食べてないような段階でおかわりを差し出すのが「作法」なのか…。
作法で調べてみると、「ひとくち分、残すのが作法です」と書いてあったりして、逆です。
また謎が一つ増えた…知ってる方がおられたら教えてください。
↓
判明しました(※2025年2月追記)。
↓
旅人の作法として、というかこれは賄(まかな)う、もてなす側の作法なんですが、「旅人には、山盛りの飯、2杯」と決まっているそうです。
で旅人は、山盛り2杯も食べられない場合、1杯めを少し食べ、てっぺんにスペースを開けて白米を注いでもらい、「2杯めとする」んだそうです。
だから世話係の若衆が「作法にかなったおかわり、恐れ入ります」と言ったんですね。これは、「1膳メシは仏様のお供えと同じなので縁起が悪い」というところから来ています。
ご飯を一杯だけ、というのは「縁起が悪い」のです。験担ぎ(げんかつぎ。エンギをひっくり返した言葉だという説)を大事にする博徒たちの、お互いに、礼を尽くすという作法だったのです。
秀次郎は何やら懐紙を出し、食べた魚の骨を、包むんです。そして自分の懐に。
その上で
手厚きおもてなし、ありがとうございました
と礼をします。
この作法・礼儀が、「昭和残侠伝」な感じなんですね。
廃れゆく旧き良き作法。
この時点ですら、他の旅人はあの体たらくですから、我々が知らないのもむべなるかな。
さらにもう一つ。
矢崎組で開帳されていた賭場。
サイコロを振る丁半ばくち、というやつですが、花田秀次郎は参加するのに、ちゃんと挨拶をするんです。
なんとそのタイミングは「丁の目」の時。「半の目」の時には、入らないんだそうです。
へ〜と言うしかないけれど、
サイコロの目の合計が、丁は偶数、半は奇数です。
数字にまつわる、縁起をかついだ作法、なんでしょうね。
おそらくは偶数だから「割れる」、暖簾で言えば二つに分かれるから入れる、っていうことなんでしょうか。
文三は、重吉の弟だった
身を隠す文三(松方弘樹)と逃げようと、追いかけてきたおみの(光川環世)。
あの冒頭の出入りは文三が、ドサクサで殺されてしまえばいいのに…という、親分の策略だったのです。すでにおみのが、文三と惚れあっているを知って、嫉妬してたんですね。
病を押して金沢に逃げたおみのを追って、文三は筋を通すために探索に加わります。
そこには兄・風間重吉(池部良)が。
今回、割合として重吉の登場が35分経過後、というのは珍しい展開ですね。
毎回、名前は同じで設定が違う、という基本を守って登場する風間重吉(池部良)。
なんだか花田秀次郎は冒頭から、助けたくない勢力に加担してる状態が続いてるんですが、これは最初の、黒田組の客分だったことに対する恩義、なんですね。
金沢では、築港工事の入札で、稲葉一家と三洲組(さんしゅうぐみ)が基本的にモメています。
行きがかり上、文三とおみのをかくまった三洲組。
親分の三州政治(さんしゅうまさじ・鶴田浩二)に対し、花田秀次郎が(また)、仁義を切ります。
三州の、親分さんとお見受けいたしまして、取り込み中、仁義は御免こうむります。
手前、ただいま、ご当地、稲葉一家の厄介もんです。
生国と発します、東京は浅草です。
姓名の儀、花田秀次郎と申す、駆け出し者です。
ご丁寧なお言葉に申し遅れまして御免こうむります。
手前、当家の三州政治と申します。
お見知りおかれまして、よろしくお頼もうします。
この、2大スターによるアップ合戦、
仁義を通して、二人の侠客として交わされるなんらかの情。
そしてなんということでしょう、この三州政治(さんしゅうまさじ・鶴田浩二)親分の奥方は、8年前、刑務所に入る前に、花田秀次郎と惚れあっていた、加代(かよ・松原智恵子)だったのです!!
なんという数奇な運命。
なんという悲恋。
もう、静かに「約束のお守り」を川に投げ捨てるしかない秀次郎…。
この悲しい要素、他にいろいろありすぎて、今回に関してだけはすごく「特に無くても良かった感」が強いんですけれど。
警察権力をも手なづけた汚い稲葉一家に、けっきょく文三(松方弘樹)は殺されてしまいます。病の伏せつつも、最後まで文三の手を求めたおみのへの、黒田親分の激しい嫉妬、ですね。
黒田組への一宿一飯の義理を返す行動をとらざるを得ない花田秀次郎。
三洲親分に決闘を申し込み、怪我を追わせつつ、もう黒田組には我慢できない状態に陥ります。
もはや、義理は果たせたのか。
渡世の世界において「金筋(きんすじ)」と評される花田秀次郎が持つ「侠客としての筋」。
これ以上、花田秀次郎はどう落とし前に向かうんでしょう。
一方、弟と、弟が愛した女を殺された風間重吉(池辺良)。
その責任を感じた花田秀次郎は「どうか私の命をとってください」と、重吉にドスを投げます。
しかし、風間はドスを投げ返します。今回ちょっと、眉毛描きすぎじゃない?
義理を守る都合でこうなってしまったことを、苦渋ながら理解してくれていたんですね。
次の朝、盛り土をした二人の墓の前で、復讐を誓う風間重吉。
花田秀次郎がそこに合流。
カタギのはずの風間ですが、
アタシたちには、赤い着物か…
と言いかけます。
すると秀次郎が
白い着物だ
と返すんです。
白い着物は白装束、つまり死んだ時に着せられる、っていうのはわかるんですが、赤い着物って??
昔、監獄では囚人に、赤い着物を着せるのが決まりだったそうです。
だから捕まって刑務所に入ることを「アカオチ」って言うんですね。これもおそらく、江戸の規律でしょう。当たり前ですけど昭和元年(1926年)は、明治に改元した慶応4年からまだ、60年も経ってないんです。言葉や記憶が、活きいきと受け継がれている時代、ということですね。そこから40年以上経った1971年公開の「昭和残侠伝 吼えろ唐獅子」ですが、説明なしにこういう言葉がぽんぽん出てくるところも、人気の秘訣だったのかもしれません。
さて、道行きです。
親にもらった大事な肌を
墨で汚して白刃の下で
積もり重ねた不孝の数を
なんと詫びようかお袋に
背で泣いてる唐獅子牡丹白を黒だと言わせることも
しょせん畳で死ねないことも
百も承知のやくざな稼業
なんで今さら悔いはない
ろくでなしよと夜風が笑う
それにしても浅草の人である主人公が、前橋から信州へ行って、そこから金沢で決死の殴り込みに向かうって、なかなかの移動距離ですよね。旅情とか地域性とかは、あまり感じさせないけれど。
今回は珍しく、早朝の殴り込みになりましたが開始時点で、あと9分30秒あります。ちょっと余裕ある。
そーっと入っていって、いきなり郎党に斬りつける二人。
黒田親分が秀次郎に言い放つシーンがあります。
秀次郎!!それがてめえの仁義かっ!!
言い返す秀次郎。
てめえらに仁義もクソもあるかい!
ヤクザの風上にも置けねえ…!
こんなセリフ、かつては無かったです。
殴り込んだら、終わりまでただただ殺戮するだけだった。
やはり、腹に据えかねてたんですね、あの食事のマナーの悪さとか…。
怒ってたんだね、秀次郎…。
風間重吉はやっぱり今回も、ちょっと短めの刀剣を持っています。
脇差と長刀の中間くらいの長さ。
なんでちゃんとした長刀を持ってこないわけ?
だから殺されちゃうんでしょ??
腹を突かれ、それでも戦う重吉。
文三(松方弘樹)も一緒に来れてたら、もっと優勢になれたのに…。
今回は、花田秀次郎も刺されてしまいます。右の後ろから、背中を刺されてしまう…あんなの致命傷だと思うけど…。さらに背中も切られてしまいます。大丈夫か死ぬぞ。
三洲親分の助っ人もあり、無事に黒田親分の討伐に成功。
しっかりとどめも差します。
それにしても「重症」「瀕死」になるとみんな、これ定番なんですけど、メイクが変わります。
目と、眉毛の間を青白くする。これで「血の気が引いている」という表現にしているんですね。
無事に風間重吉は死に、三洲親分(鶴田浩二)に逃される…というところで物語は終わります。
それすら、秀次郎は「それは仁義にならねえ」と固辞しようとします。なんて律儀なんじゃ。死ぬなよ秀次郎。
警察は来てないし、逮捕もされてないけど生死はこれ、不明だぞ今回…。
とにかく全編にわたって、阿野金一(玉川良一)がいい味を出し続けてる、そんな「吼えろ唐獅子」でした。
ーシリーズ9作ー
第1作『昭和残侠伝』1965年10月1日公開
第2作『昭和残侠伝 唐獅子牡丹』1966年1月13日公開
第3作『昭和残侠伝 一匹狼』1966年7月9日公開
第4作『昭和残侠伝 血染めの唐獅子』1967年7月8日公開
第5作『昭和残侠伝 唐獅子仁義』1969年3月6日公開
第6作『昭和残侠伝 人斬り唐獅子』1969年11月28日公開
第7作『昭和残侠伝 死んで貰います』1970年9月22日公開
第8作『昭和残侠伝 吼えろ唐獅子』1971年10月27日公開
第9作『昭和残侠伝 破れ傘』1972年12月30日公開
…2020年は「仁侠ものチャレンジ」で陰ながらお許しをこうむります。


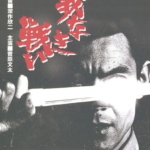
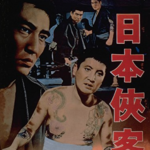

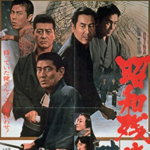





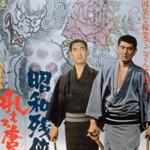






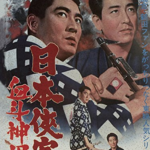

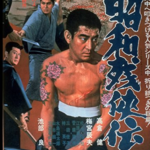


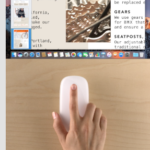

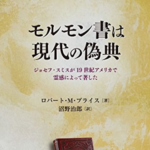


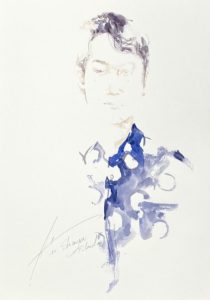
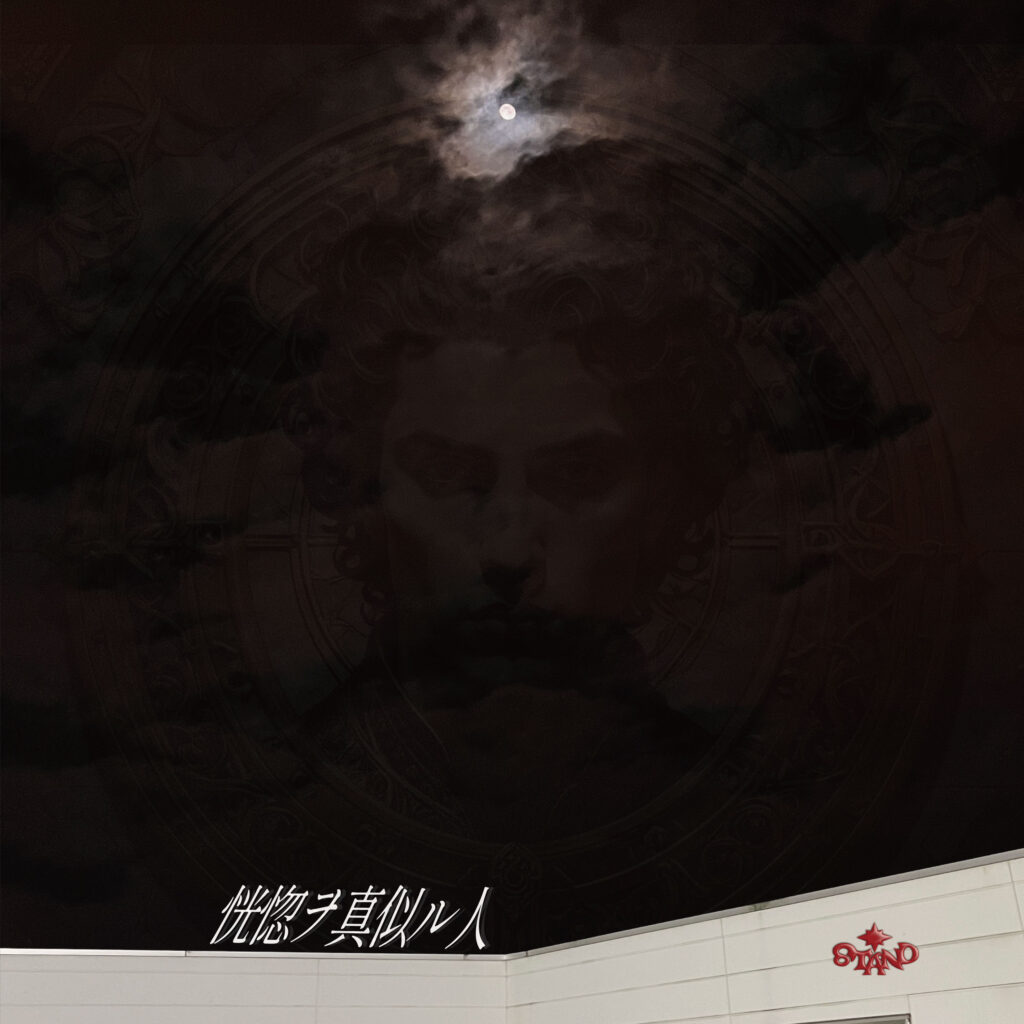
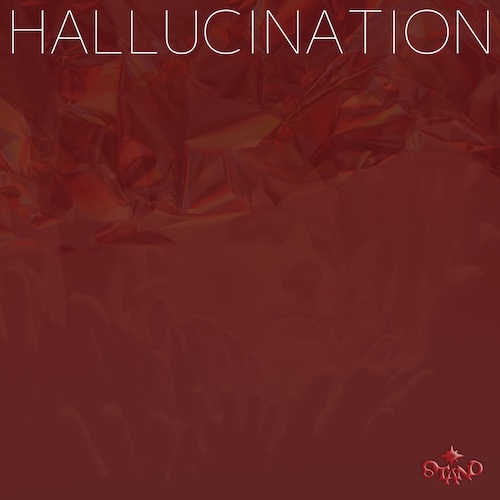




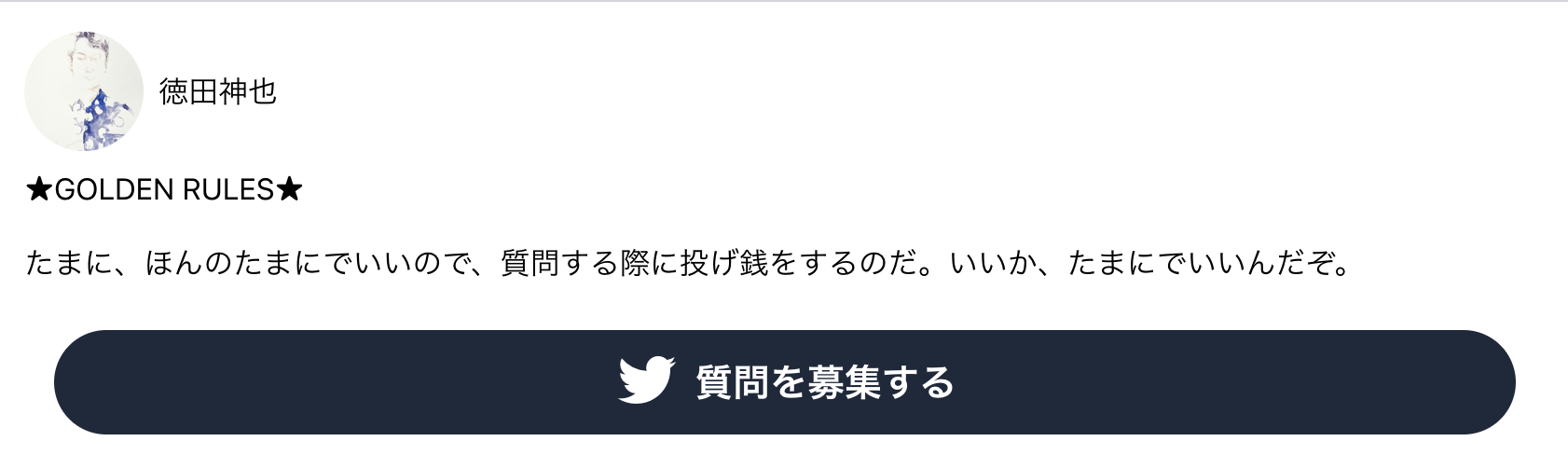






還暦を過ぎた典型的な「昭和人間」です。
高倉健が好きで、ネットサーフィンでこちらのブログにたどり着きました。
私は「昭和残侠伝 吠えろ唐獅子」が好きで、とくに台詞が胸に響きます。
とくに、三州の親分(鶴田)を手にかけなければならない花田秀次郎(健さん)。その秀次郎を気遣って親分は言います。「勝負は時の運。切るも因果、切られるも因果。どちらが倒れても、この場限りにしておくんなさい」。はからずも切るはずだった親分の命を助けた彼は駆け寄ります。そんな秀次郎を見た親分のひと言。「一宿一飯の義理であっしを切りに来なすったおめぇさんが・・・。因果な渡世だな」と。そして、秀次郎は返します。「運否天賦、出たとこ勝負。そのお心遣いは無用に願います」。
このシーンはとくにしびれますね。長々と書いてすみませんでした。
失礼いたします。