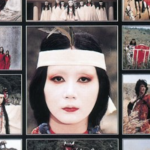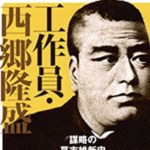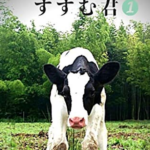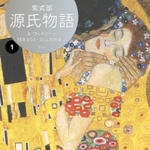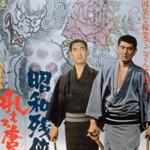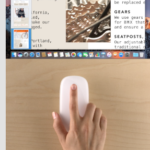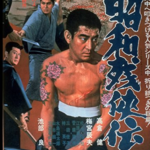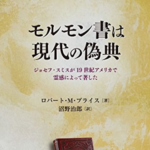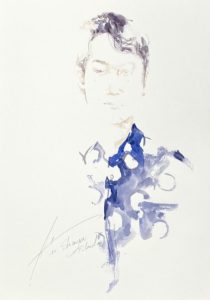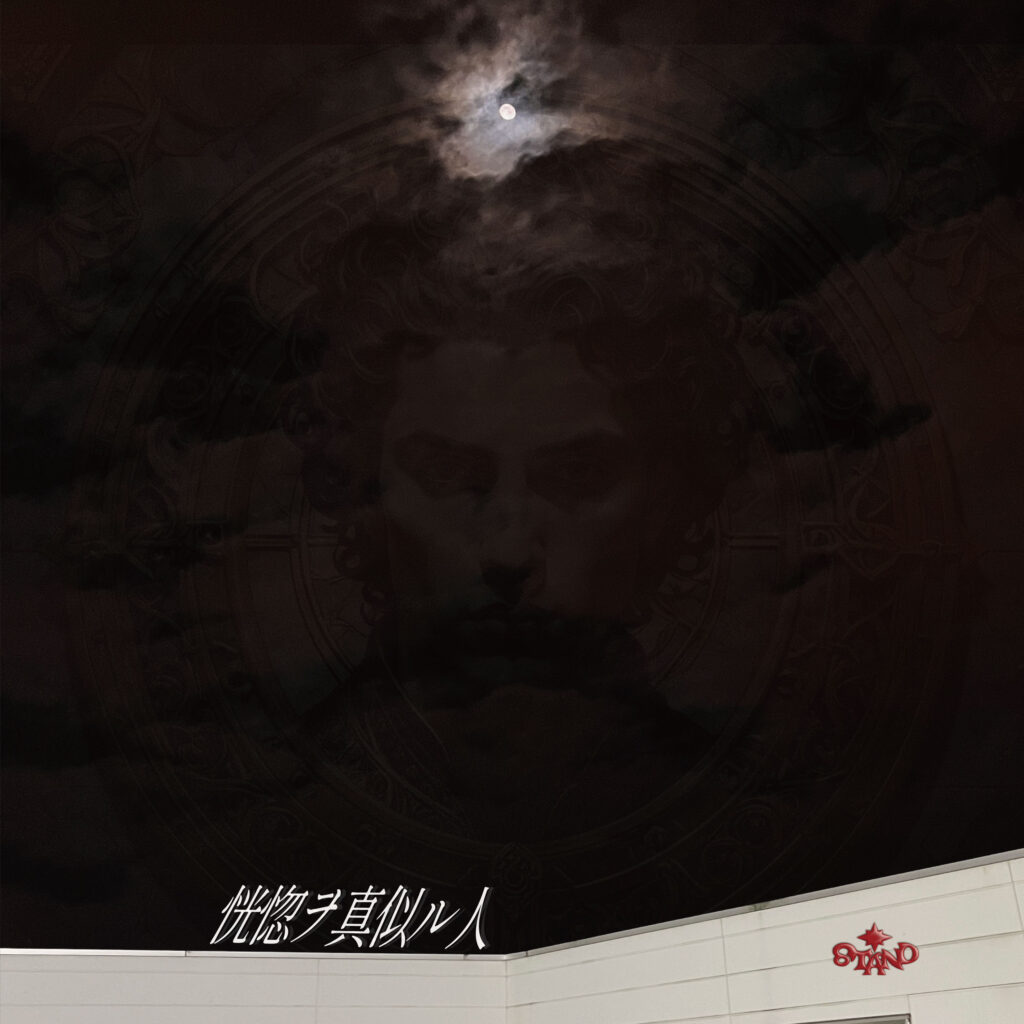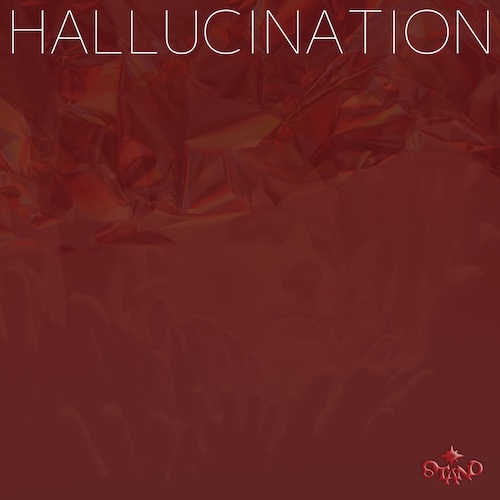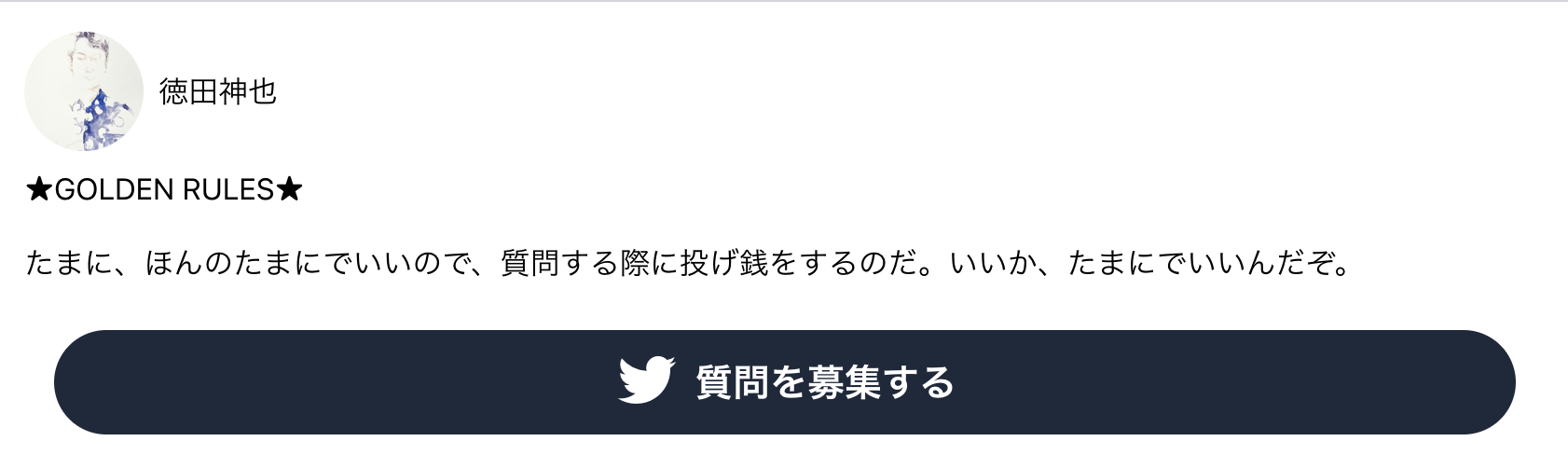海洋・河川に恵まれた日本では、治水そのものが、その土地を統治する上で重要だった。
治水は、水害から人民を守り、収穫高を上げるために必須のハイテク技術である。
古墳時代にはすでに治水工事跡が発達し始め、飛鳥時代にはダム式ため池が作られていた。
手法によって甲州流・美濃流・上方流などと呼ばれる。
江戸時代前期には関東流(伊奈流)がメインになり、後期には上方流が中心になった。
※現代の「首都圏外郭放水路」は地下50mを流れる、増水したぶんをトンネルを通じて江戸川へ流す仕組みである。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
斎藤孝監修。
自然、歴史、文学、科学・技術、芸術、伝統・文化、哲学・思想の7分野からの、日本にまつわる365日分の知識。この本をさらっと読み、知ってるようで知らなかったことをさらっと初めて知りつつ、ああそうなんだね~なんて知ったかぶりしながらほんの少しだけ、書くことを1年間続けます。最低限「350ページ以上ある本を読んだよ!」の事実が残るだけでも、価値はゼロではないはず。言わんや「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことかと。
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365