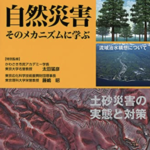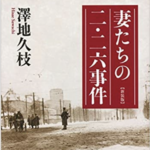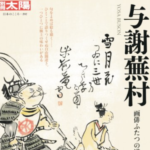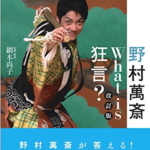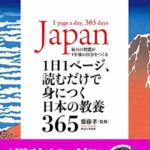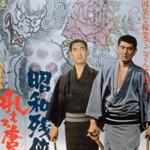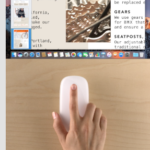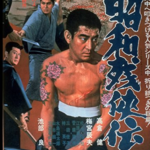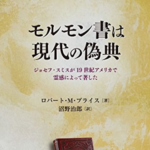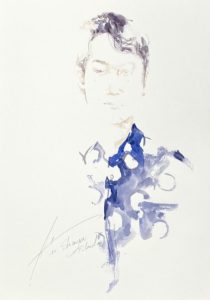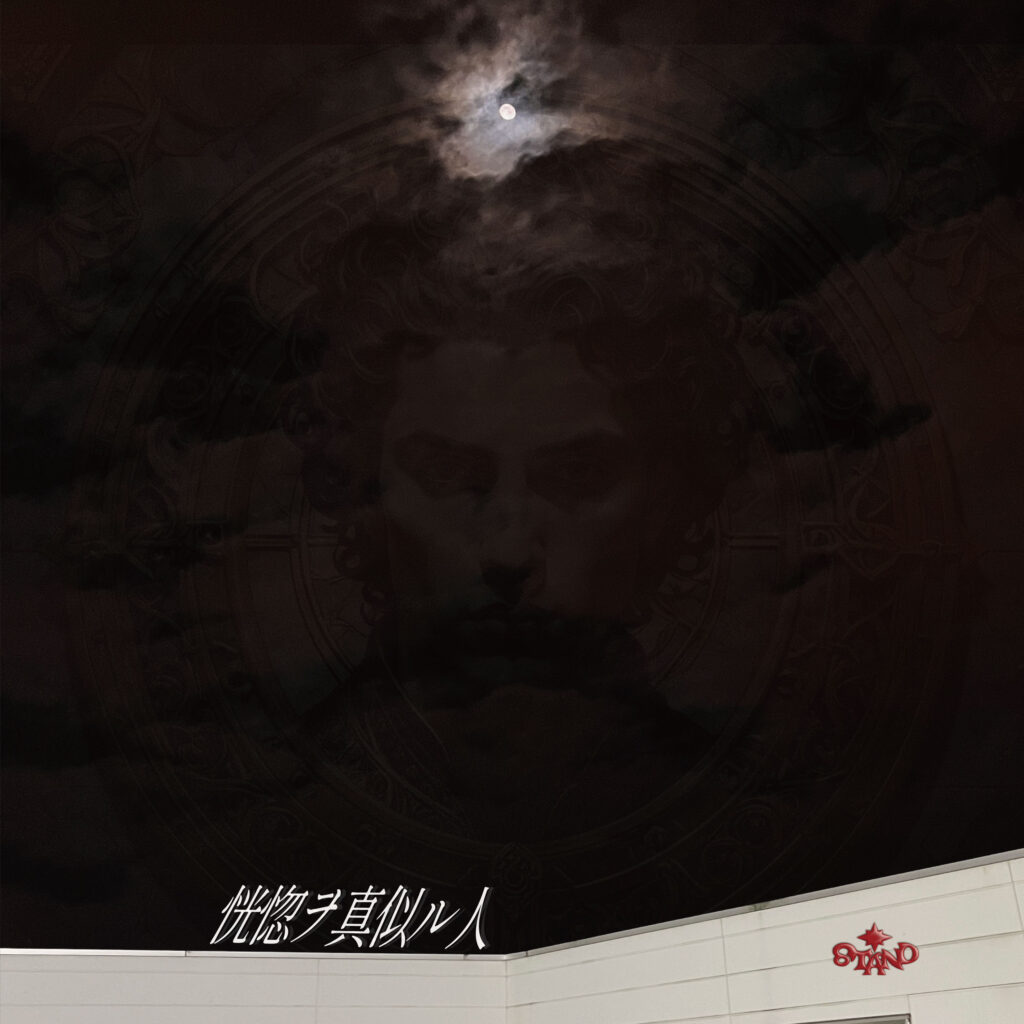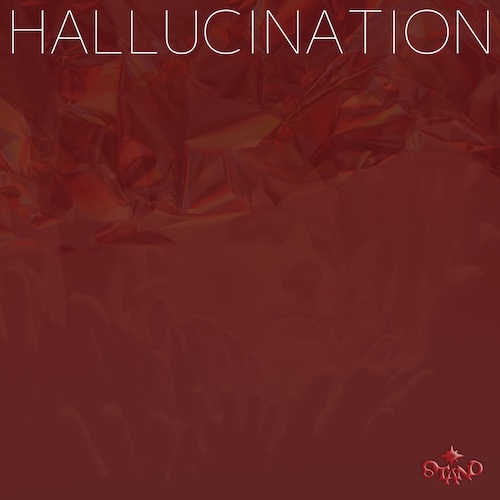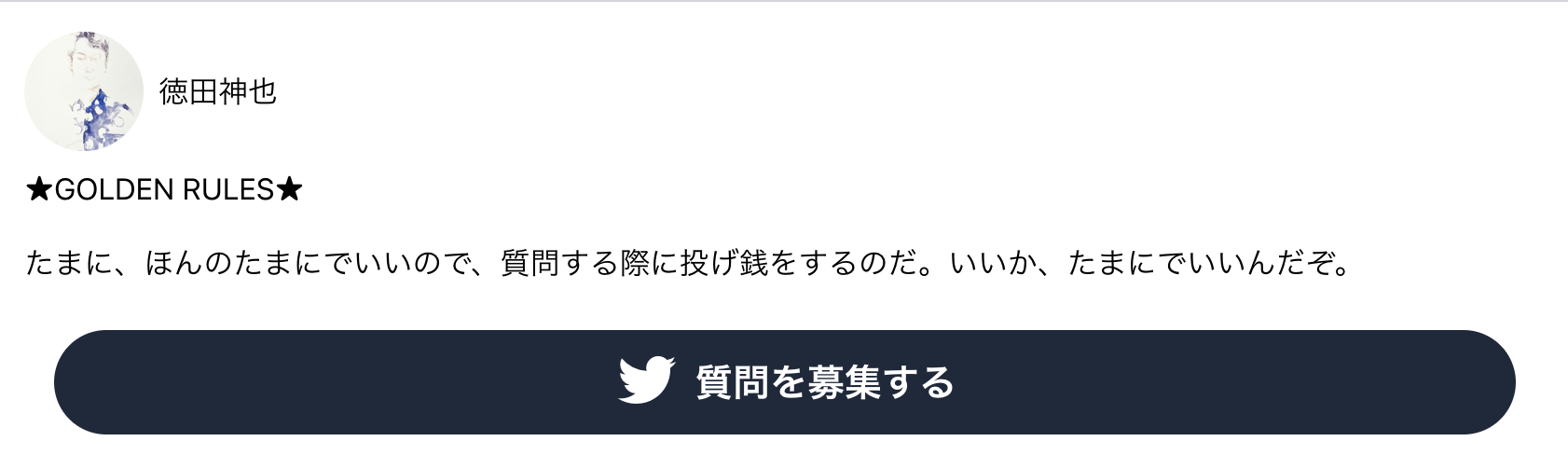蒔絵(まきえ)と螺鈿(らでん)。
蒔絵には「研出蒔絵(とぎだしまきえ)」「平蒔絵(ひらまきえ)」、「高蒔絵(たかまきえ)」があり、それぞれに金と漆を使った技巧が施される。
起源としては「末金縷(まっきんる)」という技法だろうと言われ、その技は正倉院宝物「金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんかざりのからたち)」に見られる。
螺鈿は虹色光沢を持つ貝殻を素材に使った細工である。
角度によって模様の輝きが変化する。
有名なのは国宝「片輪車螺鈿蒔絵手箱(かたわぐるまらでんまきえてばこ)」である。
※螺鈿の螺は巻き貝、螺鈿の鈿は金の飾りを意味する。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
斎藤孝監修。自然、歴史、文学、科学・技術、芸術、伝統・文化、哲学・思想の7分野からの、日本にまつわる365日分の知識。この本をさらっと読み、知ってるようで知らなかったことをさらっと初めて知りつつ、ああそうなんだね~なんて知ったかぶりしながらほんの少しだけ、書くことを1年間続けます。最低限「350ページ以上ある本を読んだよ!」の事実が残るだけでも、価値はゼロではあるまいて。言わんや「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことかと。
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365