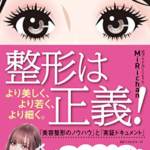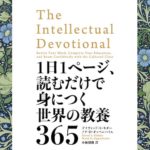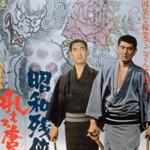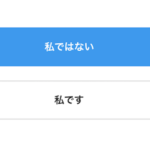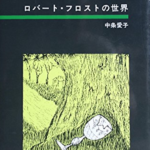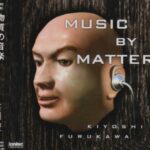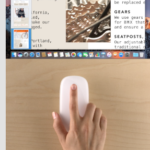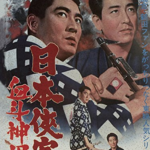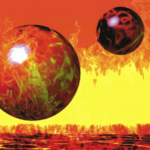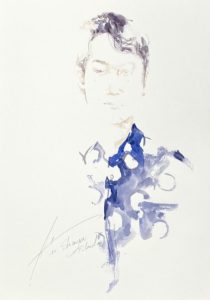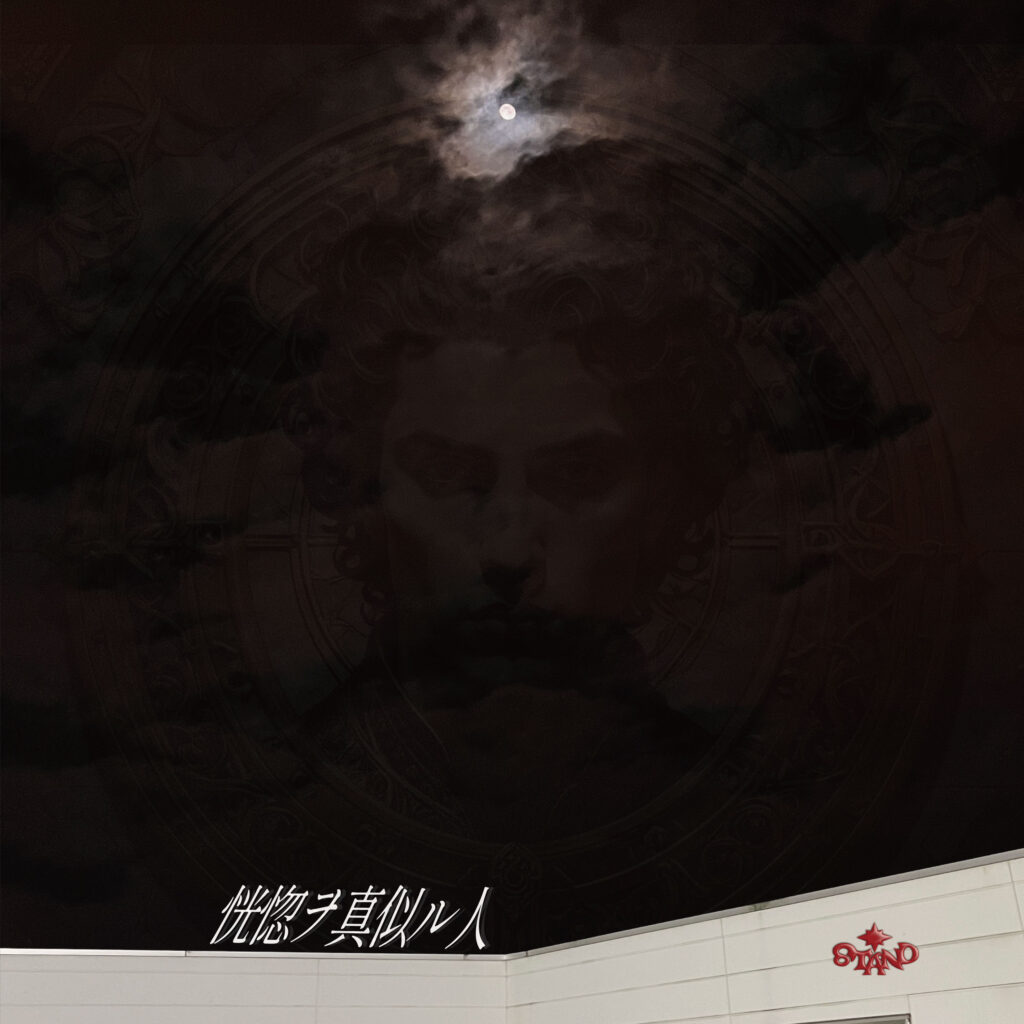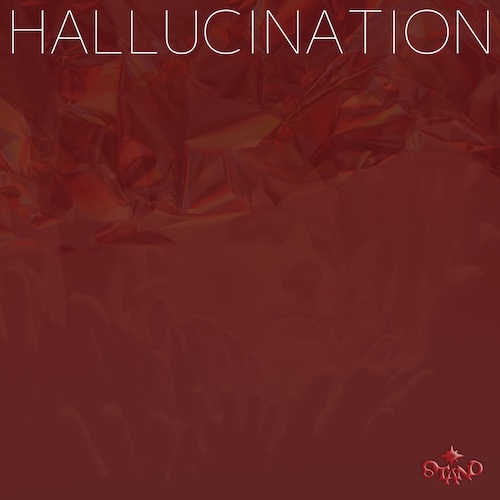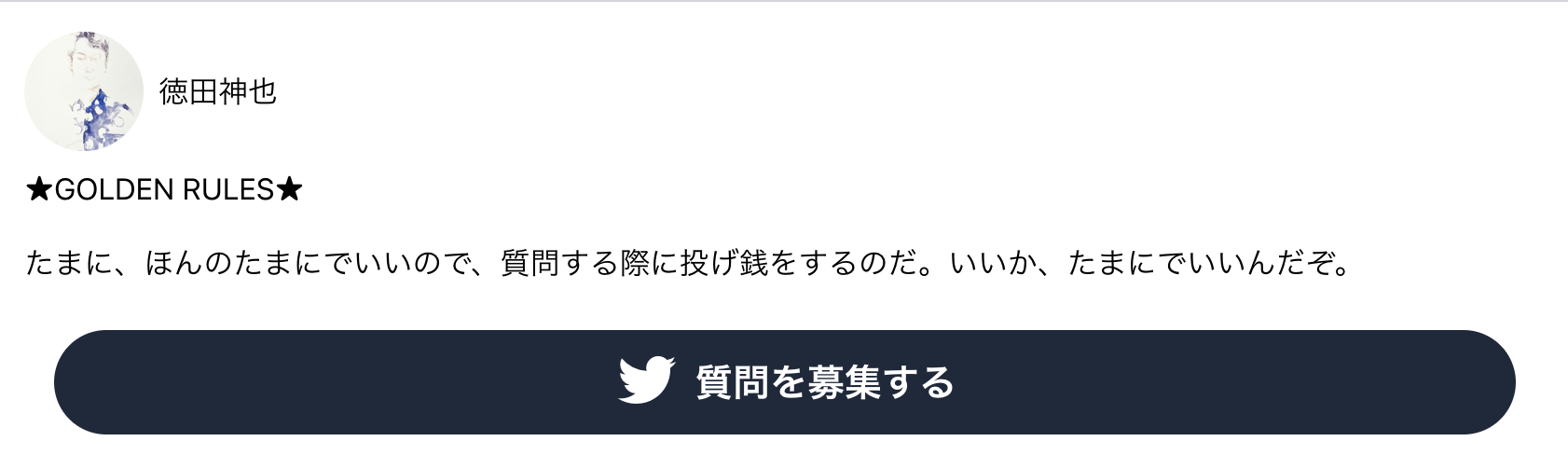メロディーは今では、音楽の中ではもっともオリジナリティを求められている要素だと言えるだろう。少しでも似ていると「パクった」と言われかねない。
だが15世紀のフランスでは、単純な旋律は共有されることがよくあったという。
「ロム・アルメ」や「きらきら星」の旋律も、共有財産のように使われていた側面があったそうだ。
これはつまり、曲を作る上で何が重要視され、何を大切にするかが、時代によって変わっていくということの表れなのかもしれない。
アレンジや音色が時代によって移り変わることは容易にわかるが、そのメロディが「80年代っぽい」とか「00年代っぽい」とかは、その旋律だけを取り出して並べた場合、わかるものなのだろうか。
時代の中で、旋律に「◯◯っぽい」という偏りが生じるころ、それを打ち破る先進的な作曲家が出てくる。それが珍しがられ支持され、また「◯◯っぽい」と言われるまでそちらへ偏っていく。
だけど、どこかで聴いたことのある旋律だからこそ、親しみを覚えることもある。
それを繰り返しているのかもしれない。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
1日1個、一年続けたら自動的に少しだけ賢くなるんじゃないか実験。
デイヴィッド・S・キダーとノア・D・オッペンハイムのベストセラー。小林朋則氏訳。
歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、365日分の知識。
この本を読みつつ、知ってるようで知らなかったこともちゃんと知りつつ、ああそうなんだね~なんて思いながら、少しだけ書くことを続けます。最低限、「360ページ以上ある本を読んだ」の事実が残れば、それでいい。「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことか、と。
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365