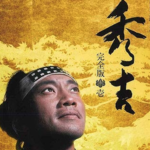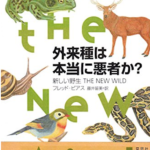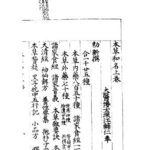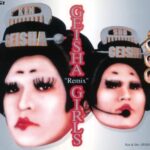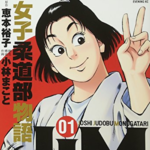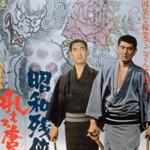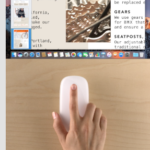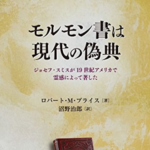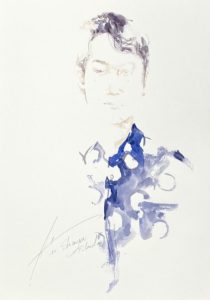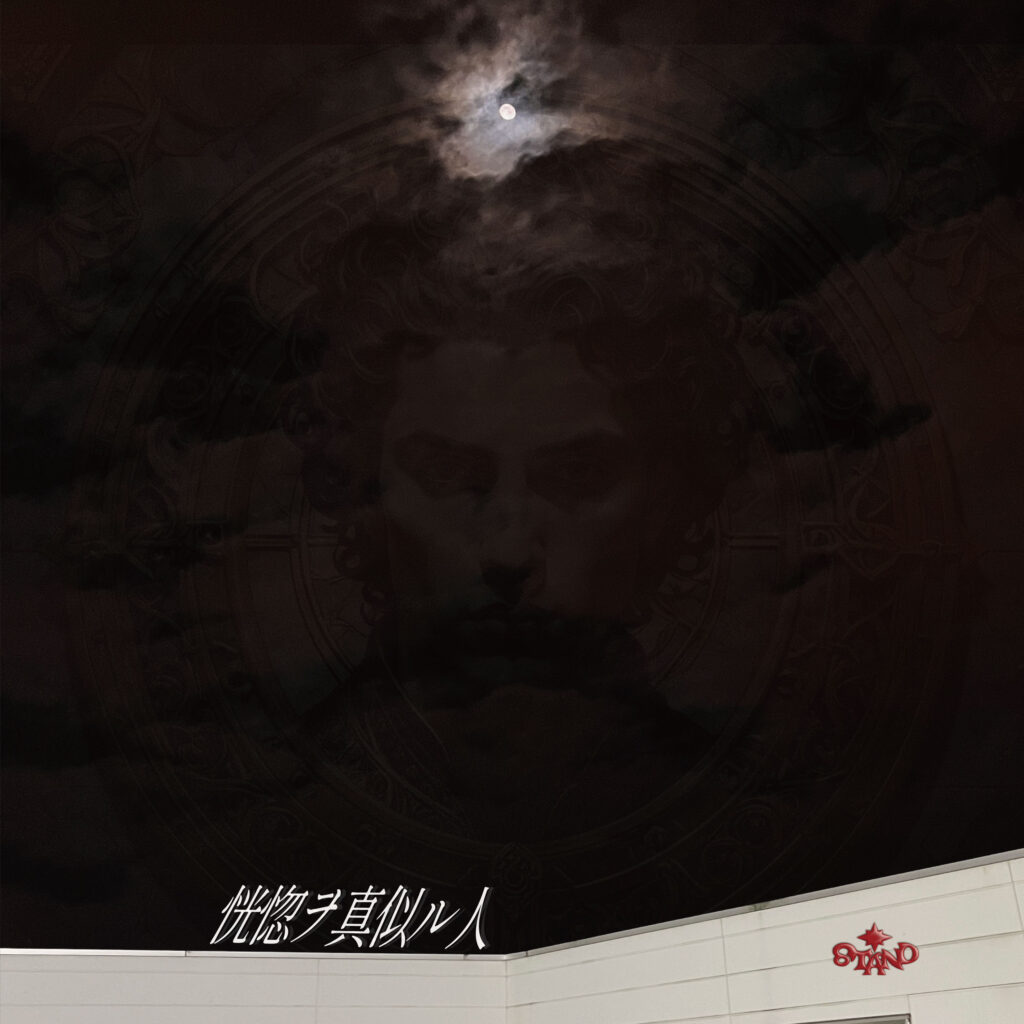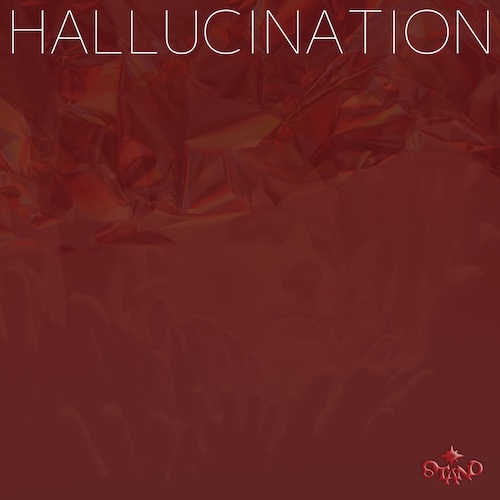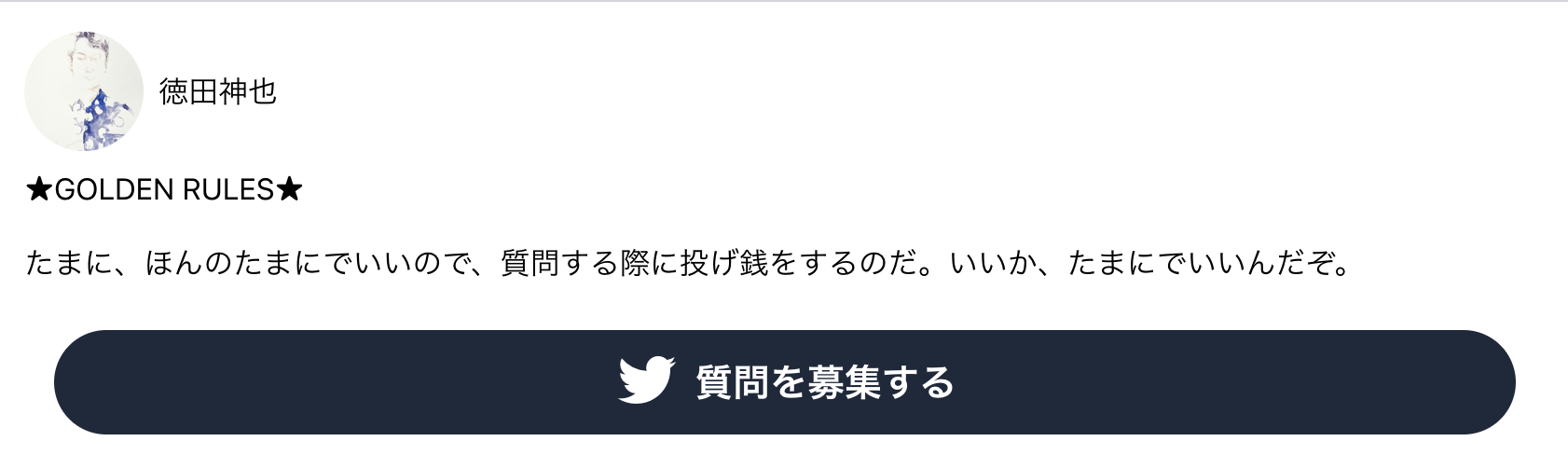明治になって教育現場では廃止された和算。
江戸時代に飛躍的に発展した。
海外の数学界よりも早く発見された数式などもあり、業績は大きい。
数学書『塵劫記』には答えを載せず難問を記した「遺題継承」というコーナーがあり、人気を博した。
中でも関孝和は「算聖」と呼ばれるほどの功績をあげており、筆算による代数の計算法である「点竄法」を発明し、円の算法の発達にも寄与した。
※今でも算数で習う「つるかめ算」は当時、「雉兎(きじうさぎ)算」と呼ばれていた。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
斎藤孝監修。
自然、歴史、文学、科学・技術、芸術、伝統・文化、哲学・思想の7分野からの、日本にまつわる365日分の知識。この本をさらっと読み、知ってるようで知らなかったことをさらっと初めて知りつつ、ああそうなんだね~なんて知ったかぶりしながらほんの少しだけ、書くことを1年間続けます。最低限「350ページ以上ある本を読んだよ!」の事実が残るだけでも、価値はゼロではないはず。いわんや「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことかと。
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365