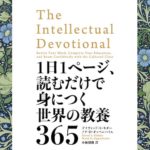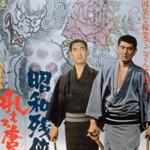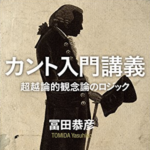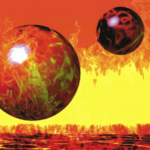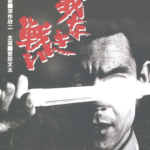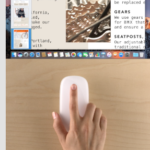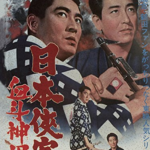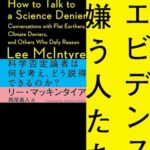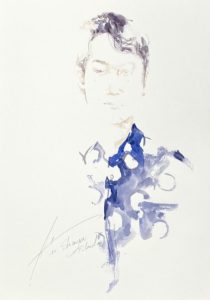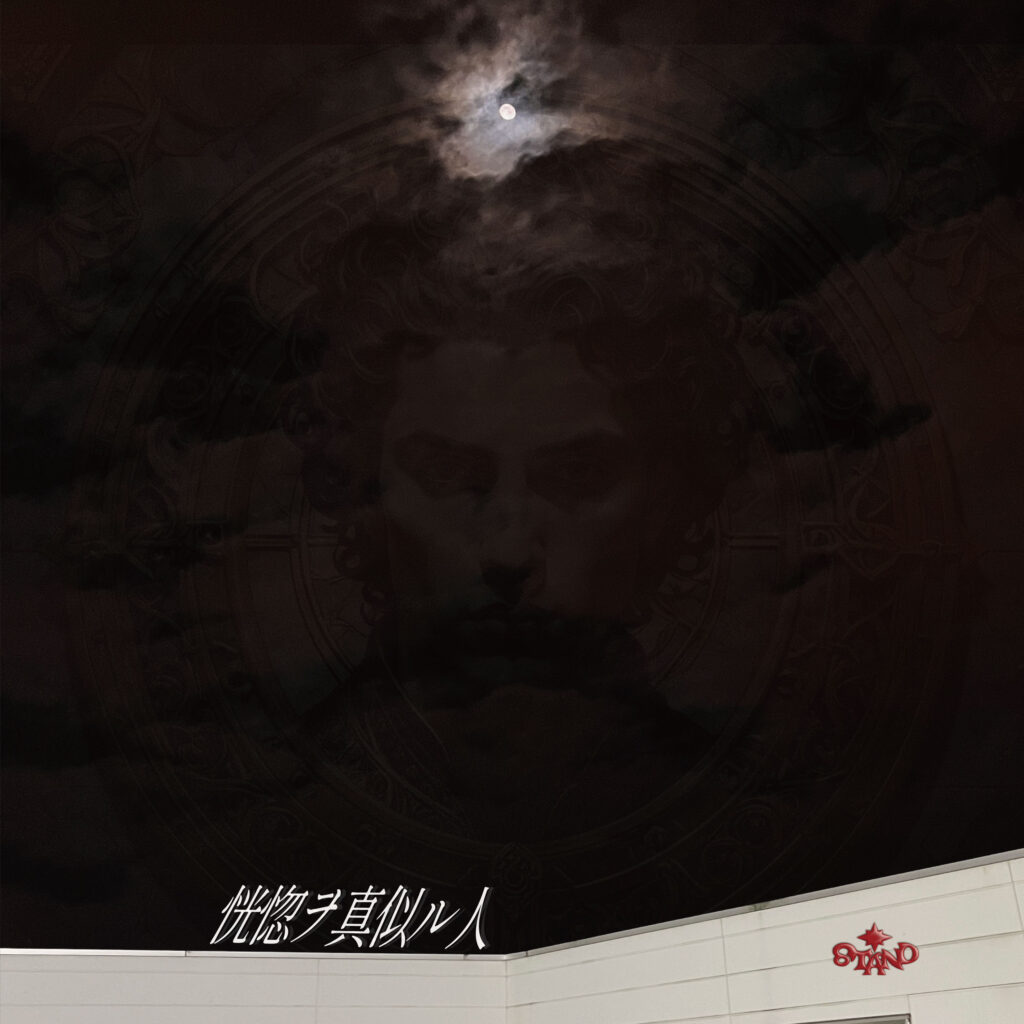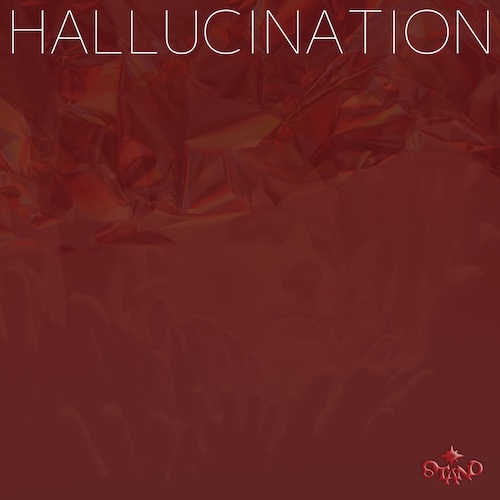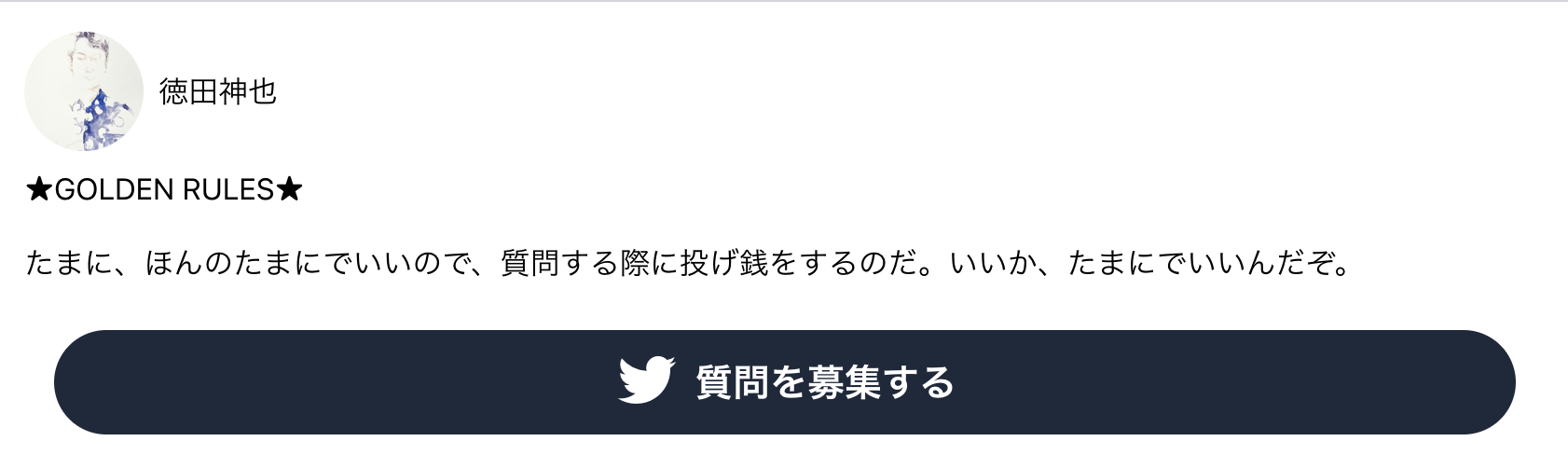われわれが「音楽」として認識しているものは、西洋音楽を基礎にしているものがほとんどだと言っていいだろう。
ピッチ・スケール・キーの整理に則って、組織化された音の団。
音楽を、そんな風に考えたことはないけれど、専門的な分解を経れば、その構成要素がずいぶん解析されているのが西洋音楽だ、と言える。
それ以外の音楽においてはそこまで明晰に分解されていないものもあって、それだけに音高なども微妙で、西洋音楽(とその子孫たち)を聴き慣れたわれわれにとっては妙に違和感があって、だけどノスタルジックで、どこか郷愁さえ感じさせるものがある。
転調と言えば、話題になっていたのがSHISHAMOの『明日も』という曲だ。
SHISHAMO『明日も』サビの転調に関する音楽に関わってる人の反応
https://togetter.com/li/1286797
サビの部分で転調することが、「違和感に感じるかどうか」が何かの分かれ道、というわけでもない。
違和感というか「ちょっと変わった感じ」「驚き」「急にドアを開けた感じ」を演出するのにじゅうぶん、効果を発揮してるわけだし。
つまり「だからって悪とかそういうことではない!」ということだ。
音楽理論をきっちり学んで来た人にとっては「その法則破りはちょっと…」とか思うところもあるとは思うけど、「それを許容するかどうか」は「理論を知ってるかどうか」とはまったく別次元の問題、だ、ということだろう。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
1日1個、一年続けたら自動的に少しだけ賢くなるんじゃないか実験。
デイヴィッド・S・キダーとノア・D・オッペンハイムのベストセラー。小林朋則氏訳。
歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、365日分の知識。
この本を読みつつ、知ってるようで知らなかったこともちゃんと知りつつ、ああそうなんだね~なんて思いながら、少しだけ書くことを続けます。最低限、「360ページ以上ある本を読んだ」の事実が残れば、それでいい。
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365