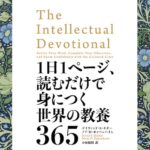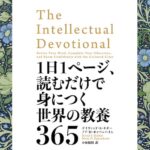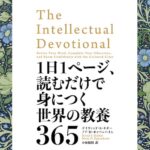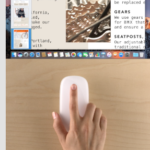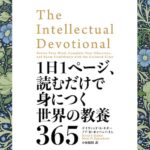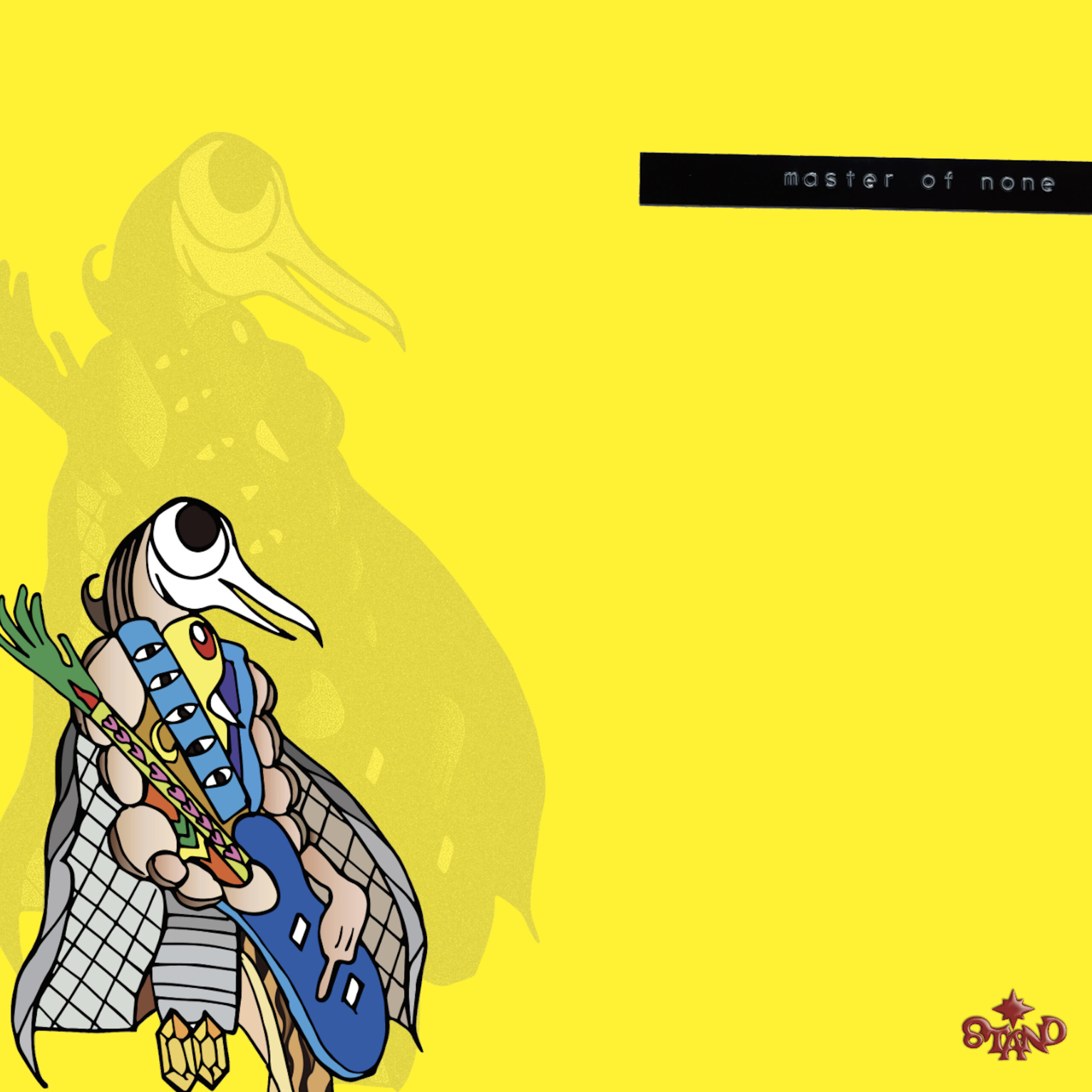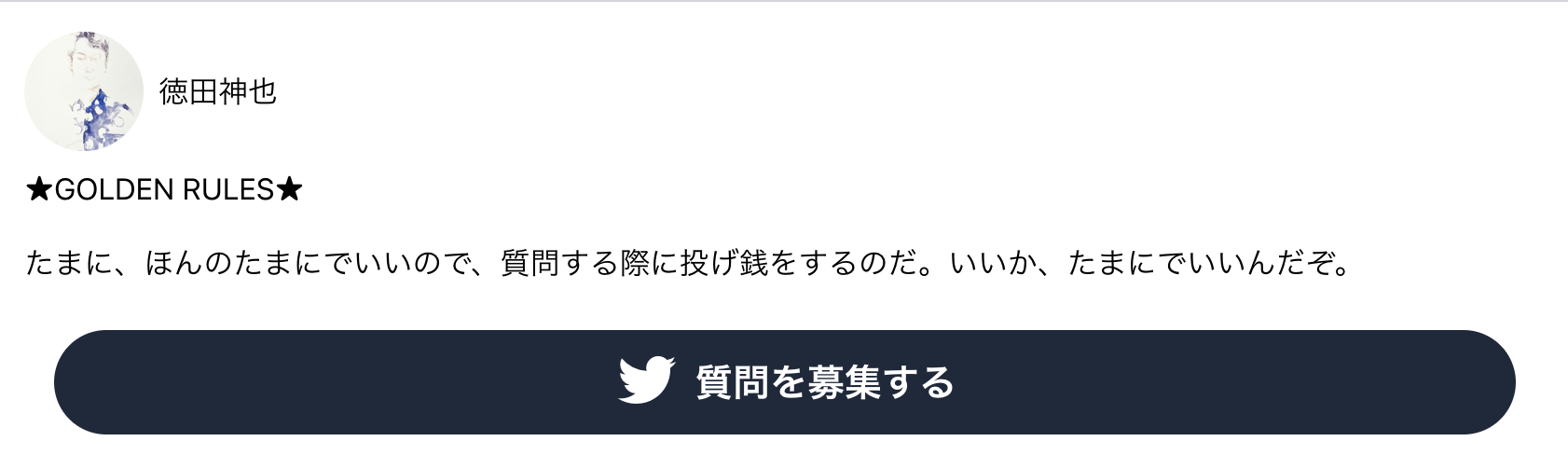クリムトと言えば接吻セップンうるせーんだわ、とか思ってしまっててすいません。
もはや、全ての元凶はナチス。
ナチスによる第三帝国建設への暴虐吹き荒れるオーストリアで、この絵のモデルとなったあのアデーレ、そして姪がその絵を取り戻す。
観ていると、もはや「オーストリアのモナリザ」とまで言われるようになった美術品の行く末はどれが正しいのか、そして家族への幽玄な描写とナチスの苛烈さと共に、考えることになります。
そう言えばバブルの時代、「ゴッホとルノアールの絵をわしの棺桶に入れてくれ」と言って大顰蹙を買ったという日本の社長がいたという話を聞いたことありますが、本当なんですかね。
でも実際は「芸術は人類の資産だ」と啖呵切れるほど、我々はそれに親しんでるわけでもないし、個人が100億円以上出して買ったんだから家とか家具とかと一緒で、好きにしてもいいんじゃないか…と少しだけ思わないでもないんですよね。
もちろん、失われた作品は、二度と戻らないからだめなわけですが。
「所有権」についての厳密な係争の結果、「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I」は、マリア(ヘレン・ミレン)の元に戻る裁定がくだる。
マリアはそれをギャラリーに預ける決定をするわけなんですが、自分の持ち物だからと言ってそれをじゃあ家の居間の日光ガンガンに当たるところに立てかけておいていいのかっていうと、いやいやそれは誰かが言ってあげないといけないんじゃないの、という気持ちにはなりますよね。だいたい、そういう高尚な趣味が循環する層の方々の間では、そんな荒々しいことにはならないんでしょうけど。
たまに、理解がまったくない人間(自分に理解できないだけでなく、理解している人のことを認めようとしない人間)が現れて、美術や後世に伝えるべき芸術がおもいっくそうしなわれる、みたいな事態って起こるんですよね。
劇中に出てきたナチスの幹部は、少なくとも芸術を解する知性を持っていた。
だけど日本だって、例えば廃仏毀釈の吹き荒れた明治初期、信仰どころか仏教美術とか優れた木工作品、という観念すら失った人たちによって、貴重な仏像とか、経典とか、もうすごい勢いで焚き火にくべて燃やされたんですよ。近所の人らとか住職によって、土の中に埋めて隠さないとやばい、っていうくらいに。
なんで「黄金のアデーレ」はオーストリアに?
3年かけてグスタフ・クリムトが描いた「黄金のアデーレ」。
フェルディナント・ブロッホ=バウアーというお金持ちのおっさんが、奥さんをモデルにして描いてもらった。
モデル当人のアデーレは、この絵をオーストリア絵画館に寄贈することを遺言していました。これが、現オーストリア政府が所有権を主張する理由だったんですね。でもアデーレは単なるモデルであり、本当の「所有者」は金出して描いてもらった夫のフェルディナント・ブロッホ=バウアーなんです。で、その相続権があるから姪が、法廷でオーストリアに勝った、ということなんですね。
所有権はともかく、上に書いてもらったように、国家が管理する美術館にあった方が品質としては保持できるような気がしないでもないですが、やはりそういう法廷闘争があってこそ、この絵と有名画家、戦争と狂気が生んだ悲哀、というものを知ることができましたし、この絵の強烈なインパクトは、そういうところからも発せられているのではないか、と改めて思うのでありました。
思わず、iPhoneケースを買ってしまったwww
使わないんですけどね…

静かだけど苛烈で、美しいけれど悲しい、そんな映画でした。
法律事務所のボスとして、チャールズ・ダンスが、裁判長としてジョナサン・プライスが出演していますね。え?ダンス氏はタイウィン・ラニスター役、プライス氏はハイ・スパロウ役、じゃないですか。劇中では、もう死んだけど。
ああ、これの話です。