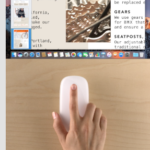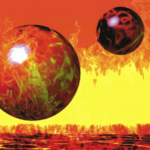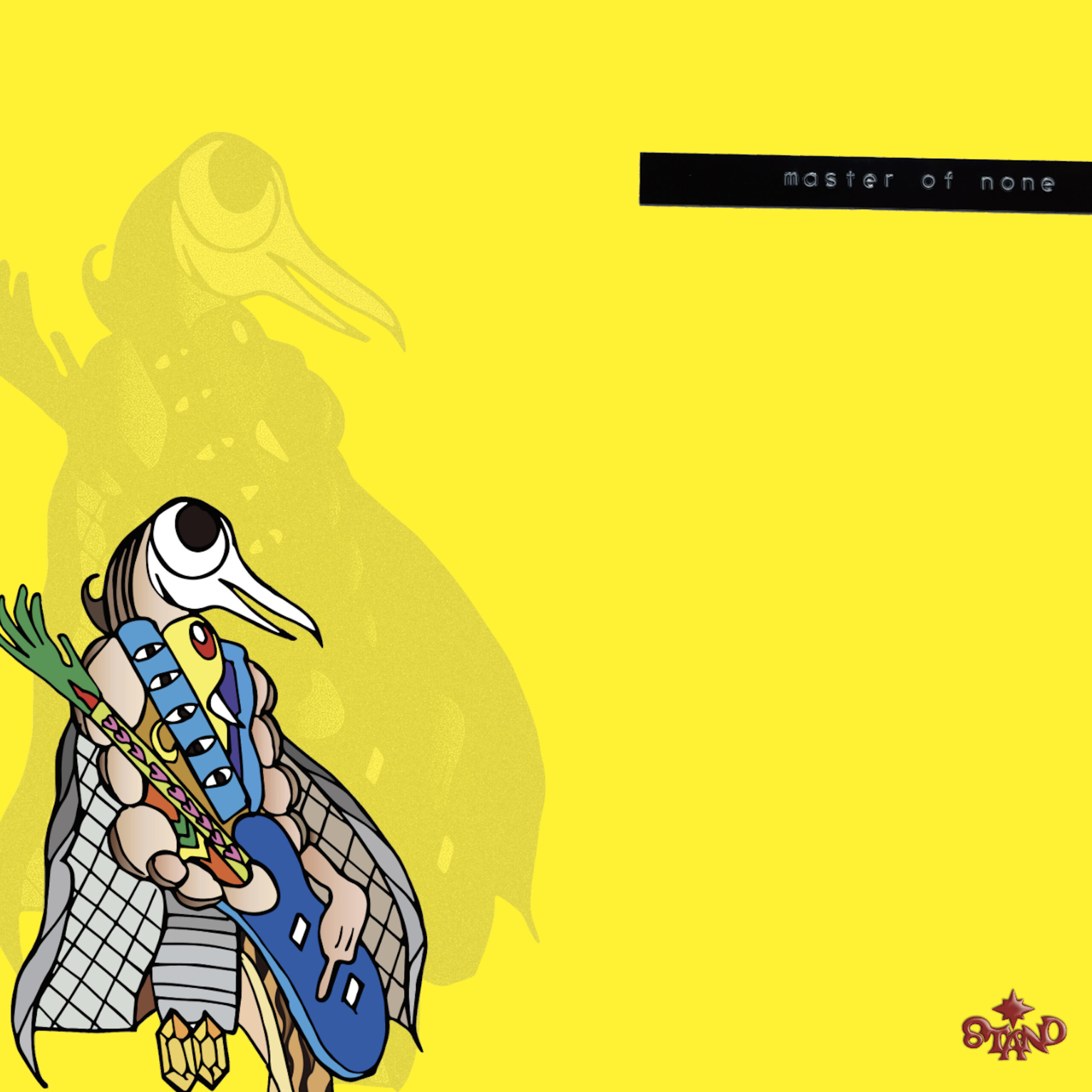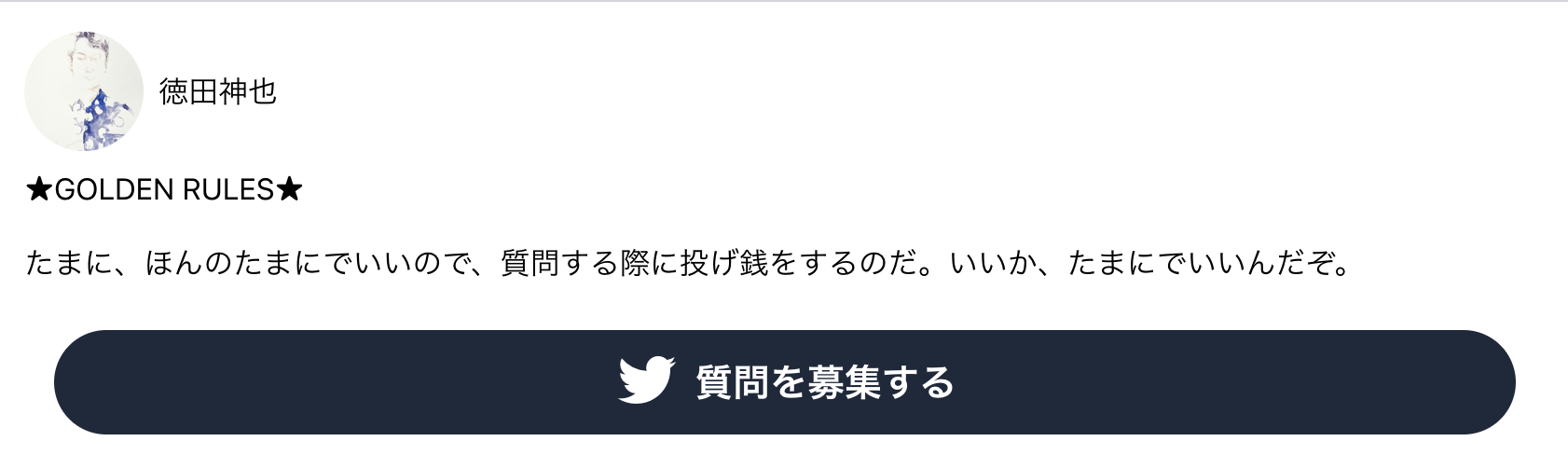先日、「お笑い短歌道場」というイベントで初めてお会いした歌人の枡野浩一さんが、「ビッグコミックオリジナル」という漫画雑誌の2017年12月20日号に、寄稿されていたのを読ませていただきました。
そのコラムのタイトルは「お笑いはもう詩歌なのだ」。
こういうタイトルってご本人がつけるんですかね…それとも編集の人か…コラムを読んだ感銘を、文にしておきたいと思います。
お笑い芸人の経験もある枡野氏の評は正鵠を射つつも、普通はそんなことまで考える人はいないよね…というような領域にまで踏み込んでおられて、それプラス「そこまで考えてしまうと笑えない」ことを受け入れつつも、だからこそ素直に笑える人はほんとうに素晴らしいんじゃないか、というジレンマをも包摂した、静かなる優しみを持った内容でした。
難しそうに書くとそういう感じなんですが、簡潔に言わせてもらえれば「ああ、もう、ほんとそう」っていう納得のいく内容、だったのです。
納得がトマトジュースに溶けててごくごく飲める感じ。
文末にある「後戻りはできない」にも、首肯せざるを得ません。
現在「大御所が引退しないがゆえに年齢層がぐっと上がっている」という現実がありますよね。
明石家さんま…62歳
タモリ…72歳
ビートたけし…70歳
ダウンタウン…54歳
萩本欽一…76歳
「まだまだ現役」と呼ぶのも失礼なくらい、普通に大活躍を続けてらっしゃる方ばかりです。
一線から身を引く、という形でゴールデンタイムの看板番組からは手を引きその枠を後進に譲る、というのがパターンのように、思われていたはずなんです。
欽ちゃんのテレビ全盛期からの移行をみると、そのパターンは踏襲されていく…かのように一瞬、見えたんですよね。
劇場からテレビへと活躍の最先端の場を移した「お笑い」は、スター化と同時に億万長者化が憧れの目標となって、さらに集中力を高めていきました。
そして、若手が台頭して、先輩は別の場所(伊東四朗さんのように役者の道、など)へ移る。
それが「文化的な歴史や伝統」のように錯覚してしまう現象もあった。
でも、よく考えたら「歴史は一回め」なんですよ。
お笑いが発達したのは江戸時代、からでしょうけど、そこから昭和のスター登場、テレビの普及、高度成長期、みたいな背景を得て「大御所が引退しない」という現象へ進んできてる。
これも、1回目。
「引退しないことが異常」ではないんです。
「いつまでも引退しないのがお笑いというもの」という確定事項が、さらに確定事項になって行ってるだけ。
大多数の若手が40代以上、というのも、一回め。
そんな中で、「見る方の視点が変わってきた」ということについて、枡野浩一さんの文章では後段で触れられていました。
かつてはお笑いは素人が、「俺には面白くない」「もっと楽しませろ」と、上から目線で好き勝手言うことができるジャンルだった。だが時代は変わった。歴史や文脈などの「素養」がない素人には、本当の意味では楽しめない。
時代が移り変わる中で、常に「新しさ」が重要なキーポイントになるのが「お笑い」というジャンルです。
なぜなら、時代の空気、時代の要求、時代の趨勢が、最終的に上澄みとして反映されるのがお笑いだからです。
そもそもお笑いの芸は、人間にとってはなくても死なない「余技」に属するものと言えるでしょう。
もし戦争になったら、慰問以外にはなんら勝利に具体的に貢献できない、非生産的な扱いを受けかねないジャンル。
いや、今はそんなことはないと科学的にも実証されてそうですが、外国へ行って、日本のお笑い芸人が日本ほど認知され評価されるというのはありえないと言い切れるくらいに、「日本文化の粋の極み」がお笑い、なのだと思います。
誇るべき豊かさの象徴、と言ってもいい。
そんな中、「歴史は一回め」なら観客側の視点の変遷も「一回め」です。
枡野氏の文章にあった「かつては」というのは、わかりやすくいえば「コント55号以前」と言うことができます。
コント55号以前のお笑いは、落語を含めすべて「観客が上位に立つ」ことを前提に成り立っていました。
日常を笑い飛ばすために、非日常を演じる演者は、馬鹿げた動きやおチャラけた言動で、わざと観客の下位につく。
溜飲を下げたりどこか憎めなさに共感したりで、観ている者は笑いを催す。
あ〜面白かった、と言いながら「芸人なんぞというヤクザものにはなっちゃいけないよ…」、大人はそう子供に諭す、というのが、芸人という存在でした。
かつてテレビの勃興とともにコント55号は、坂上二郎をいじり倒す中で、観客と同じ目線に立つ、という「視点大移動」に挑んで、それに成功しました。
それはおそらく劇場ではなく「ブラウン管の中とお茶の間」という、同じ空気を吸わない関係性の中でこそ成り立った、新しい緊張感の形だったのでしょう。
観客(視聴者)は、二郎さんを自分もいじくり回しているような錯覚にすら陥る。
それが錯覚である証拠に、コント55号のコントを見ると「二郎さんのボケに欽ちゃんがツッコむ」という図式があると思うのですが、これは誤解です。
「欽ちゃんがボケ」なんです。
もちろん二郎さんがボケてるんですが、それを「ボケたらしめている」のは欽ちゃんです。
つまり「これ、これが面白いところです」を明示する欽ちゃんが、観る者の「意志」や「見方」を誘導していた。
それを心地よく感じたからこそ、観客は喝采を送ったのでしょう。
まるで、オルゴールを逆回転させると新しい曲が流れる、そんな楽しみを発見したみたいに。
ツービートや紳助竜介は、ボケであるビートたけし・島田紳助が、観客より視点が上であることを試し、その地位の確立を画策した。
その目論見が真実であったかどうかは、コンビ解散後のご両人の進んだ道を見ればなんとなくわかるのかもしれません。
「この人がそういうなら、そうだわ」という納得と感銘を観客はネタの中に見出し、それを言葉では否定しながら受容するツッコミ側(きよし・竜介)とともに服従し、受け入れ、笑った。
「笑われるだけ」に「笑わせる」を明示的に混ぜ込んだそのスタイルは、その後さらに成長し、拡大していきます。
大阪で大爆発したダウンタウンの人気は、お客さんより明確に上に立つ視点、という意味で、さらに画期的なものになりました。
この二人に任せておけば大丈夫、という安心感ものちに得られ、でもその前に「そんなにグイグイ強気で来るならさぞ、面白いのだ!」と飲み込まざるを得ない、引き込まれる迫力があった。
そこから「面白い、とこの人が指し示すものをみんなで面白がろう」というところまで行き着いた。

ではこの先、「視点」はどう変わって行くのでしょう。
観客と演者の関係性の多様化が止められない以上、「上か、下か、同等か」という3つ(厳密には8つ)だけでは、言い表せない状態になっていくのもまた、必然と言えると思います。
今は、上に挙げた「視点移動を成功させた」大御所たちがほとんど一線を引いていない状態なので、彼らが確立したそのスタイル(秩序、または正義とも言う)は保たれています。
弟子やフォロワーが正確にその系統を受け継いだとしても、観客との関係性を能動的に変化させてきた独自性は個人だけのものであり、他者が代わりにやれるものではありません。
先駆者は同時に破壊者であり、破壊者は自分のクローンを作ることはしない(できない)から。
伝統芸であり古典の継承こそが本質になりつつある落語の場合はその点、継承は比較的容易だとしても時代の変化に、対応しにくいのかも知れませんね。
枡野氏の文章はそういう「お笑いについての一回めの歴史」を認識する者こそが、本当の意味では楽しめる観客なのではないか、という意味だったのかもしれません。
「あれがあって、あのコンビがいて、あれをやってて、そんでここで、それをやるww!!??」
みたいな、いわば「全てを受け入れた上での、パロディとしての芸」こそが新しく見える世界。

新しいものは新しいからこそ、受け入れられない。
そんな保守的な感覚が残るのも、また「是」とされています。
いわゆる「ベタ」と呼ばれる部分。五感に訴えるかのように、「甘いものは甘い」という、どうしようもない反射を利用した部分。
これを踏まえるには、先人たちの芸が(落語や講談、浪曲などを含めて)、とんでもなく参考になります。
これを踏まえておかないと、新しさは新しさを維持できません。
落語を聴いているであろうピン芸人の芸は、すぐわかりますから。
文化的にこのまま、どこまで変化して行くのかは「一回め」の歴史の途中から途中までを横から眺める者として、とても興味深いですね。
まずは「第三世代」が引退を余儀なくされる20年後(いや25年後になるかも)までを目処(めど)に、確定的な変化が起こるでしょう。
それくらい、ゆっくりとじんわりと、変化は起こります。
その中で一点、言っておきたいのは「強者として人気を得た者しか、視点を移動させる変革をすることはできない」ということです。
「イジラレる側」として爆発的人気を長く博しても「視点移動」の文化的価値を変化させることは不可能です。
能動的、かつ強権的な売れ方をした人らこそが、ついに新しい視点を提示できる。
それは「さらに上から」とは限りません。
多様化するメディアの定義に柔軟に対応することこそが「視点移動」なのかもしれない。
悲しいかな、20年後に生きているとしても、それを感応する力がこちらに残っているかどうかは、どうも怪しい…たぶん、無理。
「受信できる人を能動的に選ぶ」というのが、新しい時代に呼応した「視点移動」なのかも知れません。