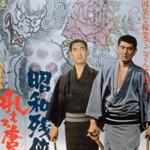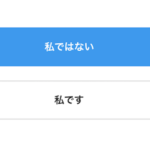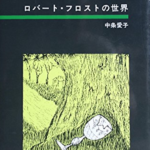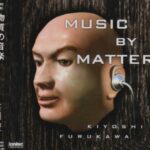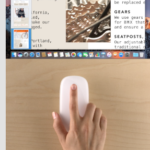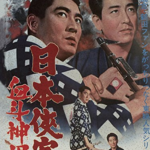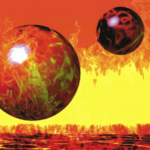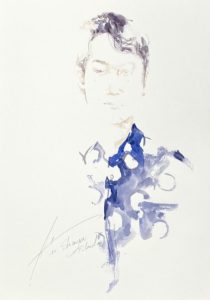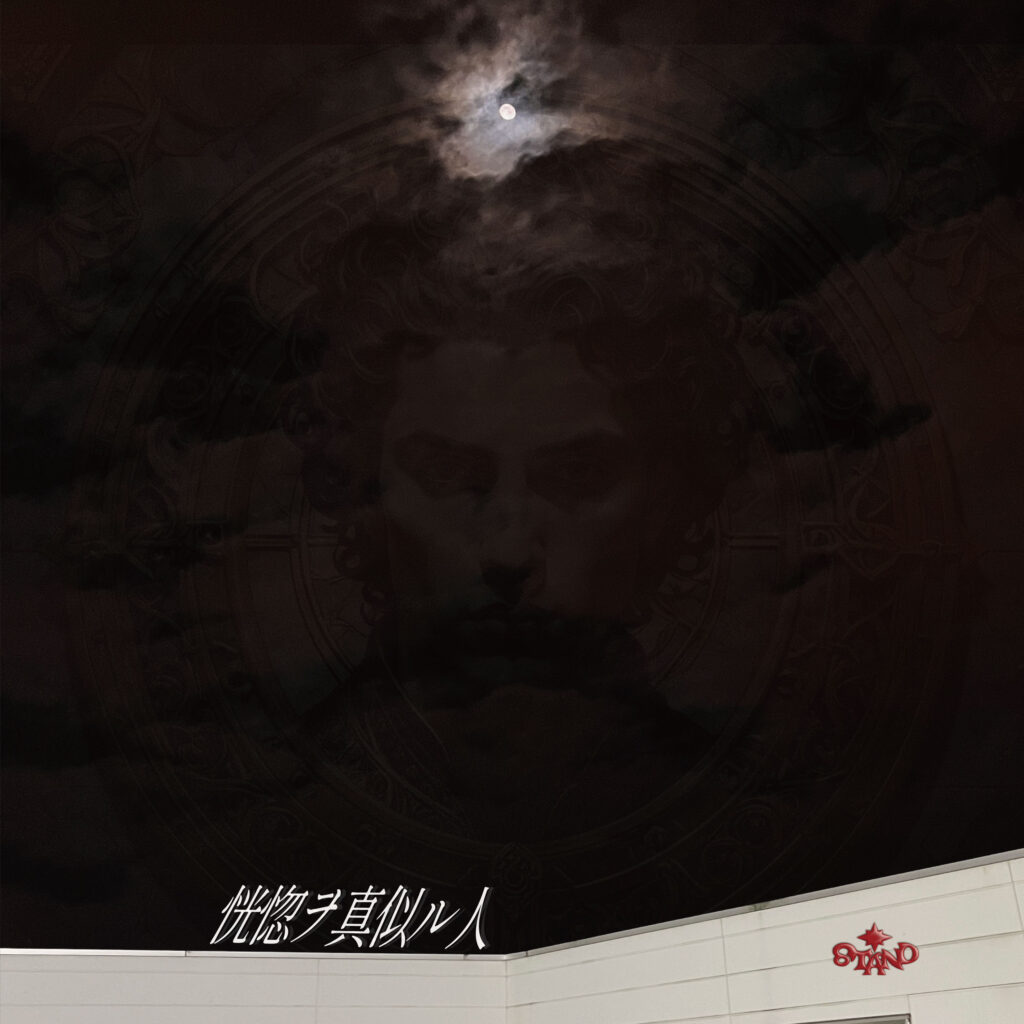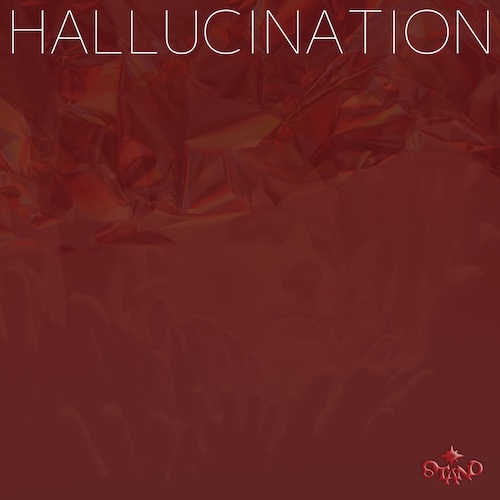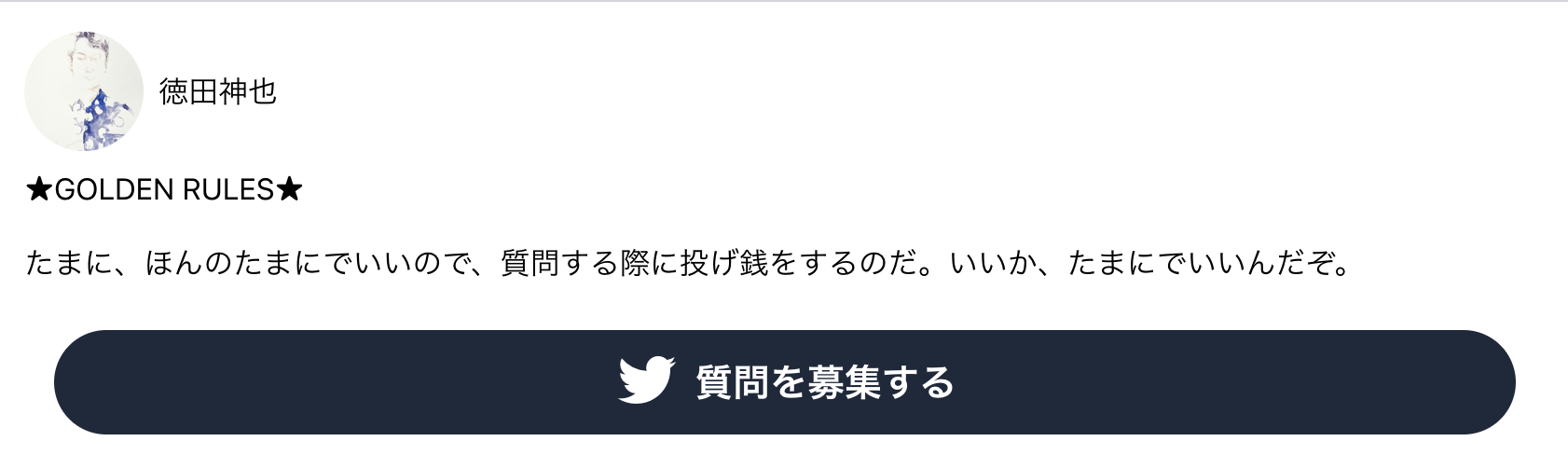過去、ちょっとだけウナギについて書いております。
誰かとウナギについて話をしたりすると「うん、まぁ…そうね…」と、フワフワフワフワ〜っと話題じたいがすぐに立ち消えになったりします。
お互い、ウナギに対しての見解なんて固まってないんですよね。
「結局」なんて決められるわけがないじゃないか、と。
それが何十年も続いていて、結局「結局、ウナギは食べていいのか」がわからないまま、次の土用の丑を迎えてしまう…という流れになっています。
このサイクル、止められてない。
どうやら、元凶は「土用の丑」です。
世界的なウナギ不足は、「土用の丑」を中心にその理由があるようです。
水産資源としてウナギをよく食べる国はいくつかあれど、なぜか日本だけが「土用の丑」という、産物として旬でもない日に異様に執着し、この日に食べないといけないというキャンペーンを狂信し需要を異常にキープし続けています。
宝暦・天明の超人・平賀源内が考案したという(落ち込む夏の売れ行きを上げるため)、曰く「う」のつく日にはウナギを食べよう!!が、未だに衰えずに続いているのです。
例えば日本において、クリスマスにクリスマスケーキを食べよう!は、不二家がしかけたキャンペーンだったのだそうです。これって、なくなりそうにないですよね。
クリスマスケーキを食べることができなくなる理由が、ないから。
だけどウナギは、絶滅するのです。
いまだ生態は謎に包まれ、完全養殖の技術が商業ベースに乗っていないニホンウナギは、絶滅したらもう二度と食べられません。
これは確認されるべきですが、「ウナギの完全養殖は儲からない」ことが分かれば、商業化はされません。「養殖は技術さえできれば普及し市場に出回る」は決まりきったコースではないということです。
絶滅したら伝統ある、秘伝のタレを100年注ぎ足し注ぎ足し…してきたウナギ屋さんも、経営続行は100%不可能になります。だってウナギがいないんだから。
ヨーロッパウナギはすでにワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)で取引が規制され、鰻屋さんやコンビニやスーパーに並べられることは今後もありません。
問題なのは「売られているウナギの7割(!)が、密漁や、違法に取引されたウナギだ」という事実です。
これは、老舗のウナギ屋さんであろうがコンビニであろうがスーパーであろうが同じです。
「ひっくるめて、7割が密猟・違法」です。
え、そんなわけないでしょう、養殖してるところからちゃんと仕入れて、管理されて売られてるんじゃないの大手なんだから、と思いますよね。
ところがそう簡単ではない(だからこそ闇でしかない)。
ウナギは養殖できないので、その稚魚であるシラスウナギを、どこかで獲ってくるしかありません。
それを養殖池に入れて、太らせて出荷する。
この、太らせたウナギが産卵して、池の中で増えていく…これができたら「完全養殖」なわけですが、それはまだ実験が成功したばかり。
ウナギ完全養殖に成功 期待高まる安定供給
https://www.fnn.jp/articles/-/1317
この採算が取れるようになるまでは、もう少しかかりそうです。
できるようになるかもわかりません。
そしてその技術の確立と採算が安定するまでに絶滅したら、もう終わりです。
上の↑記事は、実験に成功して、期待が高まっているだけ、です。
何も解決はまだ、していません。
こうなってくると、「そこまでしてウナギを、食べないといけないのか?」という気持ちになってきませんか。
そして現代の、偉そうなマーケッターやら広告屋やらコピーライターの人らにも言いたい。
平賀源内のキャンペーン(ほんとうは売り上げの落ちる夏場に無理やり売るためのウナギ屋の嘘)である、「夏のスタミナ源」「伝統ある日本の風物詩」という常識を、なんで覆せてないんだよお前ら、と。「違ったのだ!」みたいな、アイデアはないのかと。
絶滅を救うキャンペーンでひっくり返してくれよ、と。
どっかで獲ってきたシラスウナギは、正規に獲られたものと混ぜられ、高値で取引されます。
養殖池に入れてしまえば、そして育ってしまえば、どれが正規でどれが密猟かの区別はつかない。
なにか、ある程度の大きさのところでチップを埋め込むようなことをして追いかけないと(トレーサビリティ)、大手の食品会社ですら、密漁のウナギを扱っていることになります(現にそうなっている)。
コンビニ並んでるから、有名スーパーだから大丈夫だろう、ということはないということですね。
なにせ「7割が密漁」ですよ。
売られているんだからワシらは知らんわ、で済みますかねコレ。
「サカナとヤクザ」の最終章にも、がっちりウナギのことが載ってます。
ヤクザのシノギになっている…だけでは、「7割が違法」という状態にはならないでしょう。
正規の、カタギの、水産関係の会社や人たちが、いえ末端の街の魚屋・ウナギ屋までもが、絶滅に向けて一致団結してニホンウナギを滅ぼそうとしている状態、だと言えます。
めちゃくちゃに遠いマリアナ海溝で産卵し、そこで生まれて、海流に乗って日本までやってくるウナギ。
川を昇ってそこで大きくなり、また産卵のために遥かなマリアナ海溝を目指すウナギ。「そんなとこ目指すなよ」と言ってもこれは仕方のないことで、ウナギってそういうものなんですよ。
サケのように「育った川に戻ってくる」ということはないそうですが、海流なので、先に台湾あたりの川にもたくさん、進んでいくようです。
台湾で養殖されたウナギが、香港で「中国製」のスタンプを押されて化けて、日本に輸入されたり。
そのあたりも、ものすごく異常な、違法な、金が儲かる仕組みができているんですね。
なぜ、ちょっと悪いことは知りつつも、香港・台湾・日本、ウナギに関わる人らが絶滅が見えてきてるのにやめられないかというと、金になるから。
なぜ金になるのかというと、やっぱり「土用の丑の日」のせいなんです。
例えば、「恵方巻」のせいで、米が足りなくなっても、輸入してでも恵方巻って食べますか?もともと関西の風習である「恵方巻」は、今はコンビニなどでも全国で親しまれるようになりましたが、実はけっこう関東以東の人らって、この風習に冷淡だったりするのでもし米不足になったら「わかるけど、米がなくなるほど恵方巻食べてどーすんだ。バカなのか?」って思うはずなんです。
なのに「土用の丑」だけは「夏バテ防止にスタミナを」「やっぱり日本人はウナギですね」とか、平気で言ってる状態なんですよ。ウナギの絶滅が迫ってるのに。お前らはバカなのか?
ニホンウナギはIUCN(国際自然保護連合)の、絶滅危惧種(EN/Endangered)指定を受けています。
日本独自の基準で、環境省がレッドリスト「絶滅危惧IB類」に指定。
ぜひ、冒頭に挙げ今回のタイトルにしている「結局、ウナギは食べていいのか問題」と、「サカナとヤクザ」の最終章は読んでいただきたいと思う次第です。
本のタイトルだけ見ると「で、結局、ウナギは食べていいの?どっちなの?」の答えが書いてあるような気がしますけど、自分で読んでみると、これは「売ってるから食べてもいいに決まってるよね〜」と、アホヅラで風物詩を満喫してる場合じゃないぞ…なんやねん土用の丑って…という気分になってきます。
ぜひご一読を。
極端な言い方をすれば、ウナギを食べることは(高級/格安関係なくどこででもです)、違法な、犯罪的な密漁を、助長していることにつながります。
完全養殖(シラスウナギを生ませて育てる)ができるまでは、待つべきでしょうね。
需要が減れば(『土用の丑幻想』から目覚めれば)、ニホンウナギの数は戻ります。
儲からなければ、誰が法律違反までして密漁なんかしますか、という話になってきますからね。
そうなってから、また適度に食べればいいじゃないですか。
「今売ってるぶんはいいでしょう、もう死んでるんだし」も正論みたいですが、製造や流通ってそういうものじゃないですよね。どんな商品でも、常に「在庫がゼロになってから考えます」なんてことはありえないですよね、今日1パック売れたなら、1000パックを作るつもりですべてが動く、みたいな感じでしょう。今売ってるのを破棄してゼロにするくらいじゃないと、おそらく絶滅は防げないのではないか…とすら思います。
「もう、今日からちょっと考える」にしないと、絶滅への道は止められないんじゃないでしょうか。
お前、鰻屋のこと考えてんのかウナギ業界を潰す気か、と言われそうですけど絶滅したらどっちみち業界なんてこっぱ微塵ですから。
ウナギを絶滅させない方が、業界のためでしょう。
ウナギが絶滅したら、ウナギで稼いでる人の商売も全滅です。
「美味い。これぞ伝統。食文化。」みたいな理由で永久に食べられなくなるのがいいのか、ちゃんと考えて、抑えて、江戸時代から続くキャンペーンをさらに長く続く本当の食文化にしていくのか…恥ずかしくないのはどっち、なのかを考えないといけませんね。
日本はすごい!と普段言ってる人らなら「結局、ウナギは食べていいのか問題」にはおのずと答え、見出せるんじゃないでしょうか。
イオンがんばれ。
あなたも食べてる「違法ウナギ」排除 イオン新商品の画期
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/060500019/
「結局、ウナギは食べていいのか問題」の著者・海部健三博士のサイト
ニホンウナギは絶滅するのか
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~kaifu/3zetsumetsu.html