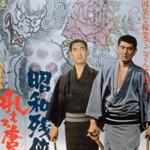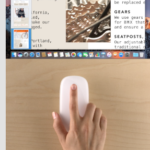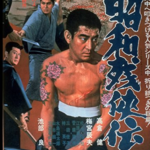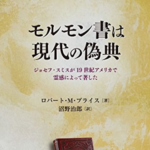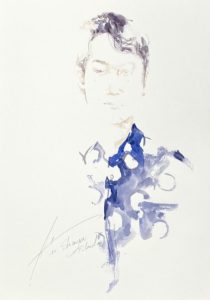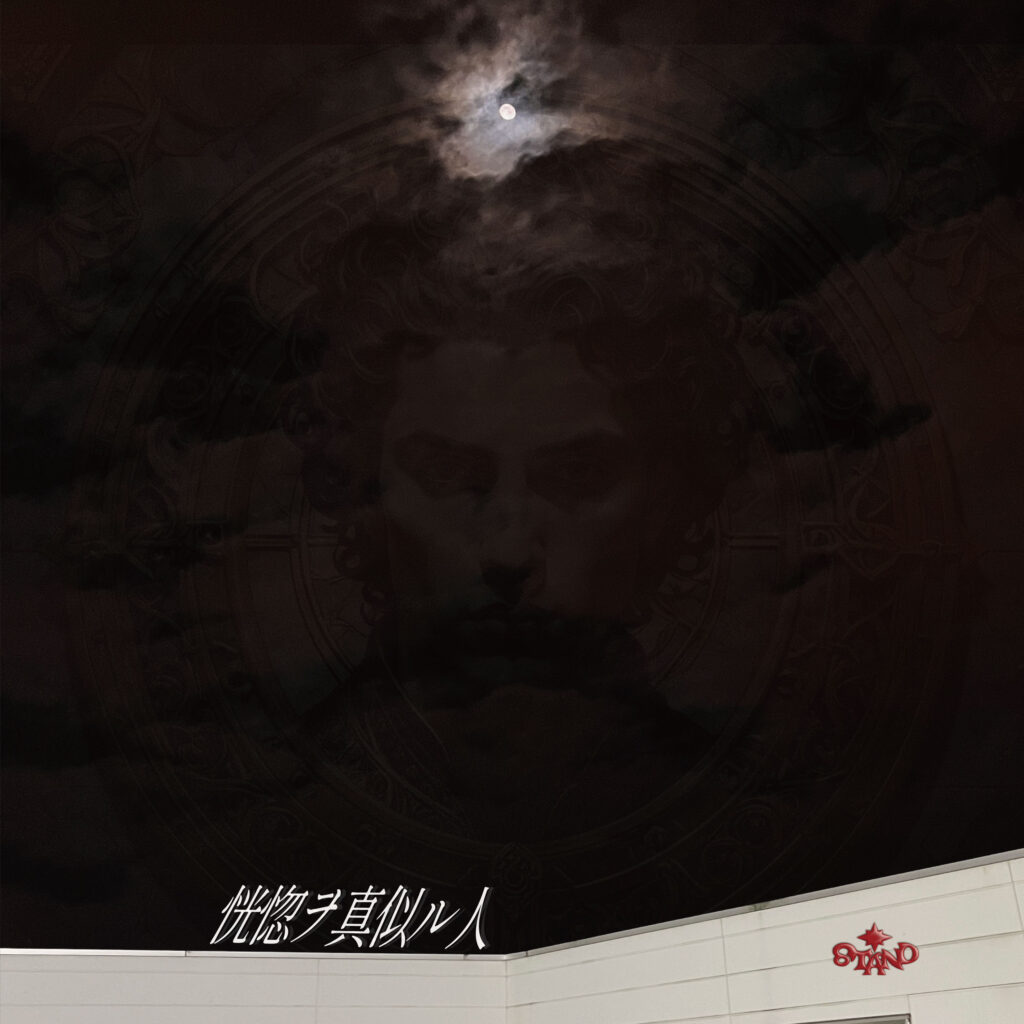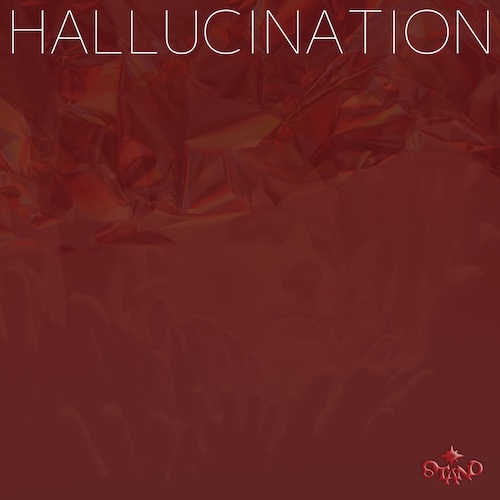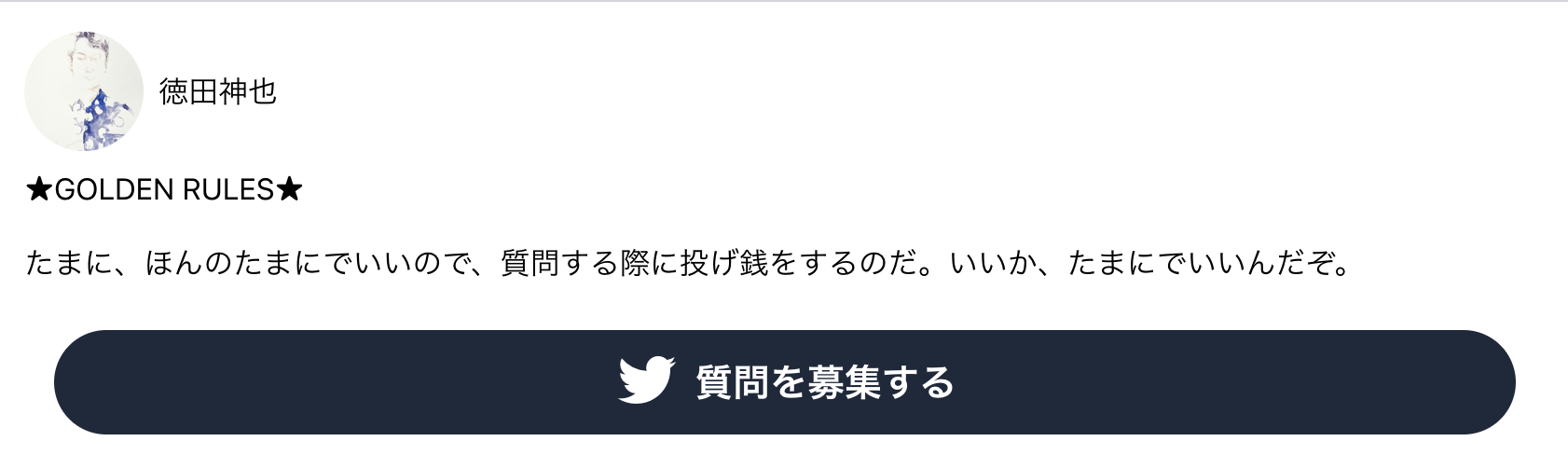不思議だった。
源頼朝(みなもとのよりとも)が天下を獲り、鎌倉幕府を開くというとんでもない結果に至る上で、最初の契機として「以仁王(もちひとおう)の乱」がある。
その短い乱の中で、源氏の長老の座にあった源頼政(みなもとのよりまさ)が急に実戦に参加し、討ち死にしてしまう。
平氏全盛の、京都においての源氏だし、源頼朝と呼応してクーデターを起こしたというわけでもない。
その時点ではまだいわゆる「源平の戦い」は存在ない。
あくまで「以仁王の」乱になんだか「責任がありますので…」的に参加して、あっさり死ぬ。
源平合戦の派手さではないので、あまり注目もされていない。
2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では老獪な武士として品川徹さんが演じていた。それでもストーリーとしてはあくまで「源行家(みなもとのゆきいえ)がもたらした以仁王の宣旨を北条時政(ほうじょうときまさ)と一緒に源頼朝が読む」という流れを捕捉するかのような、「京都情報」の一端として語られた。

源氏のメインストリーム
源頼政は、源氏の中では「摂津源氏」と呼ばれる。
あの源頼光(みなもとのよりみつ・らいこう)の流れを汲む。
源頼光の弟は源頼信(みなもとのよりのぶ)で、この流れが「河内源氏」であり、源頼朝に繋がっていく。
系統としてはれっきとした「源氏の本流」であり、平穏であれば源氏の棟梁と呼んで差し支えない人なのである。

とにかく官位が高い。
「源三位(げんさんみ)」と呼ばれた。
保元の乱と平治の乱で政治的に生き残り、それが時の権力者・平清盛(たいらのきよもり)にも気に入られ、彼の推挙を受けて三位に昇った。源氏として初めて従三位(じゅさんみ)になった。公卿の仲間入りである。
京都では平清盛が「源平の並立」を心掛けていたらしい。
武を扱う家柄なので、洛中の治安や内裏の警護などの責任が平氏のみに集中しないように、平清盛は源頼政を丁重に扱った。だからこそ、彼の官位を上げることにも協力した。
軍事力として「源平併用」を朝廷に強く働きかけていた。
責任を、源・平ではなく任命権者(朝廷や院)のせいにしようという、深謀遠慮である。
律令制度の中では従三位以上はもはや「雲の上の人」である。
従三位より上には
正三位
↓
従二位
↓
正二位
↓
従一位
↓
正一位
しかいない。
その上には帝しかいない。
ちなみに源頼朝は、後に正二位になっている。
武力で全国を席巻し天下人となった源頼朝が正二位なのだから、「ほぼ平時」に従三位にまでなった源頼政はとにかくすごいのである。
とにかくずっとモメてる平安京
だいたい、平清盛と後白河法皇が悪い。
この二人が仲良くできるわけがない。
平清盛は自分の娘を天皇に嫁がせて生まれた子を、半ば強引に天皇にした。
安徳天皇、その時3歳。
その時代、小さい子が成年まで育つこと自体が難しい。
いかに過保護に贅沢に保育しても、基準としての衛生観念が現代と違いすぎるので、幼き帝ほど危ういものはない。
当然のこと、皇室周りには「皇位継承候補者」が他にもいる。
継承候補者たる男児を増やすのが王家の仕事なのだから、いて当たり前だ。
皇位に就かなかったものは臣籍降下したり、仏門に入って「宮門跡」の別当になったりする。
予定通り、理想である「直系の子供・孫」ではなく、いろんな事情で先帝の兄弟の子供・孫に皇位が移ってしまうと、周りの近臣たちもゴソッと入れ替わってしまうので、皇位継承問題はダイレクトに貴族たちにとって、権力の維持のための死活問題なのだ。
煽るやつ・唆すやつ、嘘つくやつ。
「皇位継承者」がいるということは、その数だけ「それを神輿として担ぎたい人ら」がいるということだ。
以仁王は後白河法皇の皇子なので、皇位継承権がある。
いったんは強引な安徳天皇の即位で消えた火種だが、「幼帝さえいなくなれば」と考える輩が出て来ないとも限らない。いや、必ず出てくる…どころか、多分もういる。
平清盛はそう考え、いずれ以仁王をなんとかしよう、と考えていた。
ただ黙っているだけでは皇位継承に欲目があると思われるので、身を案じる皇族は、自ら落飾する。
僧になってしまう。
現在では考えにくいがこの時代、僧籍に入るのは「現実からの離脱」くらいのイメージがある。
その割に延暦寺は政治にガンガン絡んできてキャスティングボートを握ったりするのだが、以仁王は仏門に自ら入って大人しくしたりしないものだから、「何か企まないうちに…!」と目をつけられてしまった。
以仁王は自分でも予想できないくらいに、平氏にとって邪魔な存在になっていたのかも知れない。
挙兵を計画するも失敗、「臣籍降下」させられてしまう。
形式的に、身分は「後白河源氏」ということになっている。
その上、配流が決定したが以仁王は滋賀・大津にある園城寺(おんじょうじ)へ逃げた。
これを捕まえる軍隊に平頼政の名が連なっていることから当初、平氏は以仁王の反乱に源頼政が加担しているとは考えておらず、また本当に、共謀などしていなかったと思われる。
園城寺は以仁王を匿い、南都の大寺院に救援要請を送った。
寺院が結託し、政治勢力となって「嗷訴 (ごうそ) 」の線で進めていけば、皇位継承をめぐった実際の戦乱になどならず、穏便に済むのではないかと考えたからだ。
嗷訴はイベントであり、政治的妥協点を見つけるパフォーマンスでもあった。
人が死んだりはしない。
ところが、比叡山延暦寺がそれを許さなかった。
延暦寺は、勝手に一派を建てて独立した園城寺を憎んでおり、「焼き討ち」も辞さない強硬な構えを全山で打ち出した。とにかくこの時代の寺院の兵力は恐ろしいので、朝廷や武士はいちいち「延暦寺は味方になってくれますか?」的なお伺いを立てるのだ。例えば延暦寺に誰かが匿われたら、誰も奪い返せない。
ああ…延暦寺がそういう感じならこれは単なる引き渡し・配流・蟄居では済まない…以仁王危うし、と源頼政は判断したのだろう。
この時点で「以仁王捕縛部隊」側だった立場を翻し、立場を鮮明にして、園城寺へ合流してしまった。
なぜか。
源頼政は、責任を感じていたのである。
以仁王の配流が決定した時、その身柄を拘束に行く予定だったのは源頼政の養子・源兼綱(みなもとのかねつな)である。
以仁王とは顔見知りであったと考えられる。
それに伴い、源頼政は、以仁王にメッセージを送っていた。
「うちの子が行くし、八条院様にも迷惑がかからないように、よくお考えを。」という内容だったのだろう。
それなのに、以仁王は短慮なのか源頼政の気遣いが読めなかったのか、逃げ出してしまった。
平氏政権は、あくまで穏便に済まそうとしていた。
源頼政の血縁者・八条院のつながりのある者を捕縛に差し向けたことに、それが現れている。
なのに、以仁王が過激に反応してしまった。
対決姿勢を鮮明にしてしまった。
僧兵を頼って、武力でなんとかなると思い上がってしまった。
…結果的に、延暦寺の超のつく攻撃性まで引き出してしまった。
この引き金が、あのメッセージによる情報漏洩だったと疑われたら…。
結局その後、以仁王は南都へ逃げ出す。
奈良の大寺院にはかなりの戦力があるし、これらがすべて自分の味方になれば平氏政権を転覆できるかも、という目論見だ。甘いけどね。
彼を逃すため、源頼政は宇治で敵軍を待ち構え、あくまで以仁王を逃すために戦い、死ぬ。
齢八十を前にしての自害であった。乱の責任をとったかのような死であった。
先述の源兼綱も、ここで死んでいる。
埋れ木の
花さく事もなかりしに
身のなる果ぞ
悲しかりける
もはや自ら刀で腹をかっさばく膂力も尽きたのか、太刀を腹部に突き立て、うつ伏せになる形で身体を貫いて死んだそうだ。もはや花など咲くべきもなかった老体が、こんな結末になってしまうとは悲しい、という意味の辞世の句だが、『平家物語』の創作っぽい。一族の繁栄も自身の栄華もかなぐり捨てて、「その場その時に正しいと思う行いを素早く」を本当に実行できるこんな文武両道の賢人が、最期にこんな情けない句を詠んだりするだろうか。
悲しい死ではあるが、全うした赤心に曇りはない。そう感じる。
画期となるための画期
以仁王は逃げる途中で矢に当たって死んだが、なぜかその首が出て来なかった。
首実検(検死)ができない。イコール、死んだか生き延びたかがわからない。
それが「以仁王は生きている」という伝説に成長し、各地の抵抗勢力の理論的根拠になった。
平氏は延暦寺と結託して園城寺を攻撃し、南都にも以仁王の反乱に加担したかどを咎める形で攻勢をかけ、結局とんでもない焼き討ちになってしまった(東大寺大仏殿も消失した)。
以仁王の反乱は「皇位継承ラインを攻めればやっぱり政治的に勝てる見込みって、あるよね…?」ということを再確認させた。後白河法皇との対決で、平清盛はやっぱり死ぬまでそれに悩まされる。
源三位頼政の戦死は「源氏、平氏に何もそこまでやられる筋合いってあったっけ?」という怒りと共に、平氏専横の支配体制に憤懣やるかたない地方の豪族たちにも、反乱に加担する理由を与えた。
源三位はすごい人
私たちは歴史を結果として知っているので、これらの事件を「鎌倉幕府勃興の契機」などと位置付けることが、いともかんたんに出来てしまう。
だが実際にはその時点で、未来がどうなるかを知っている者はいない。
自分にとって最善になるような短期的な予測で、必死に動いているだけだ。
源頼政は、源氏に対しての全国的な蜂起などけしかけていない。
平氏政権を転覆させようなどとも考えていない。
そんな構想も計画も持っていない。
ただ成り行きで、守るべき筋の方へ引っ張られて、死んでしまった。
源頼政は優れた歌人でもあったので、朝廷で公卿として生を全うする道もあった。
以仁王の息子・真性(しんしょう)は天台座主に就任するなど、高僧としての一生を送っている。
親である以仁王にも、政治抗争に巻き込まれず、穏やかに生きる道はあったはずだ。
だけど、そうはならなかった。
誰がこの後、20年間も伊豆で黙っていた源頼朝が征夷大将軍になるなどと予想できるだろうか。
同じ年(治承4・1180年)の夏、源頼政も以仁王も想像だにしなかった源氏の大爆発が、始まる。