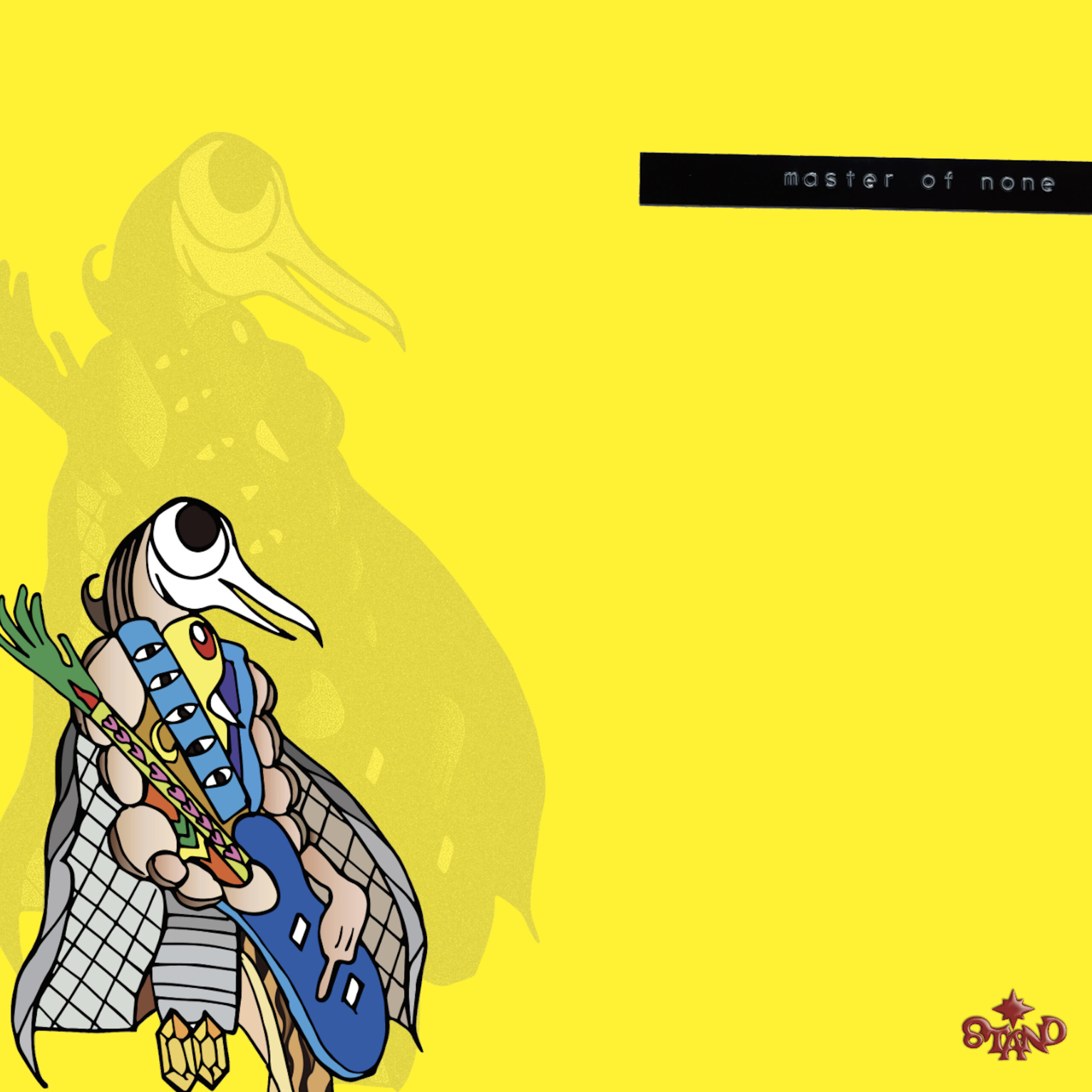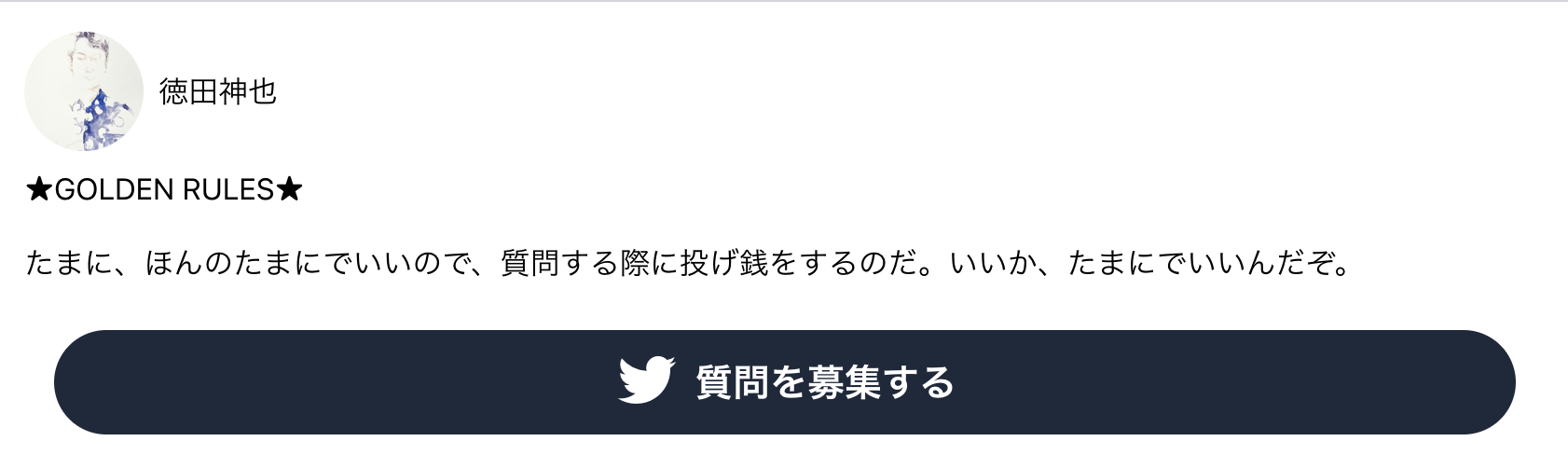いやぁ、いい映画でした。
だいたい、映画はなんの予備知識も先入観もなく観るので、あれ?みたことある俳優、女優さんだなぁと思っててぜんぜん思い出せず、あとで調べるとああ!あれに出てた!出てた!あの人か!と思うことしきりです。
今回の『ミッドナイト・イン・パリ』の、主人公の恋人イネスを演じていた女優さん。最近どこかで見た…なぁ…と思ってたんですが。
レイチェル・マクアダムス!!
『ドクター・ストレンジ』に出てましたね。恋人役で。
この映画、フランスの人が見たら、「まぁ、ねえ」みたいな感じなのかもしれないですけど、こういうファンタジーが普通に感じられてしまうというのは、パリ自体の魅力の一つなんでしょうね。
これ、1920年代に、ふわっと「夜だけ」行ってしまうというフィクションでありながら「いや、あり得るんちゃう…?」とすら思わせてしまうのは、やはりオーウェン・ウィルソンの、あまりにも自然な演技のせいでしょう。
凄まじく芸術の都だったパリ。
いきなりコール・ポーター。
F・スコット・フィッツジェラルド。
ジャン・コクトー。
ヘミングウェイ。
ガートルード・スタイン。
ダリ。
ピカソ。
そして、マリオン・コティヤール(アドリアナ)とさらに19世紀まで旅してしまう主人公ギル。
そこではロートレックだの、ドガだの、ゴーギャンがいる。
こういう歴史に名を残す芸術家がどんどん出てくるんですけど、主人公の妄想っていう感じがぜんぜんしない、ほんとに不思議な映画です。
でもけっきょくギルは、こういう歴史的・芸術的探検を終えて、それを含めて現実的なパリに魅了され、残ることにする。
芸術を愛する人、パリを愛する人、そして現実を愛する人にも、共感できるエンディングになっています。
真夜中の夢、という意味では感傷的で夢想的なんですけど、なんか「今でも普通にあってもいい夢」というか「そういうのって、ありそう」と素直に思えてしまいました。
例えば「真夜中の東京」という映画だったら、と思ったけど芸術史なんてぜんぜん知らないけど、大正時代ですよね。江戸川乱歩!?そうか、でも『ミッドナイト・イン・パリ』は、「アメリカからフランスにやってきた」っていうところがミソなんですよね。
「アメリカ人が日本にやってきた」だと、ちょっとオリエンタリズムがすぎるというか、「何があってもおかしくない感」が強すぎるというか。
すでに西→東の旅で、1個トリップしてますからね(旅行という意味以外に)。
だから例えば、現代の日本の田舎とか路地裏に迷い込んだら、『ミッドナイト・イン・トーキョー』は成り立ってしまう。
なんとなく、アメリカ人が持つヨーロッパへの畏敬とか、裏返った憧憬、みたいなものが下地になっているってことなんですかね。
オーウェン・ウィルソンはこの後、2015年には『クーデター』において東南アジアとおぼしくある国で政変に巻き込まれます。