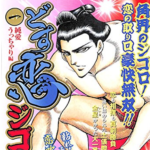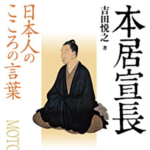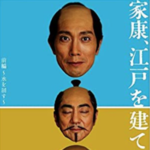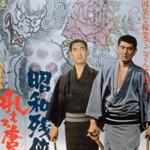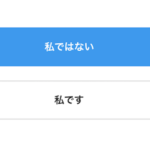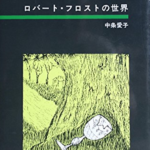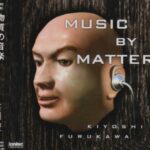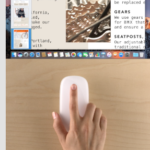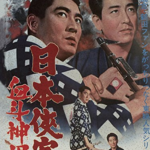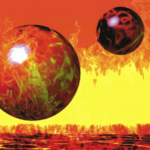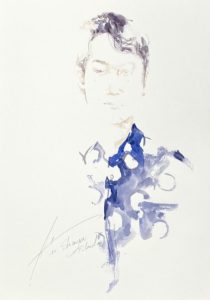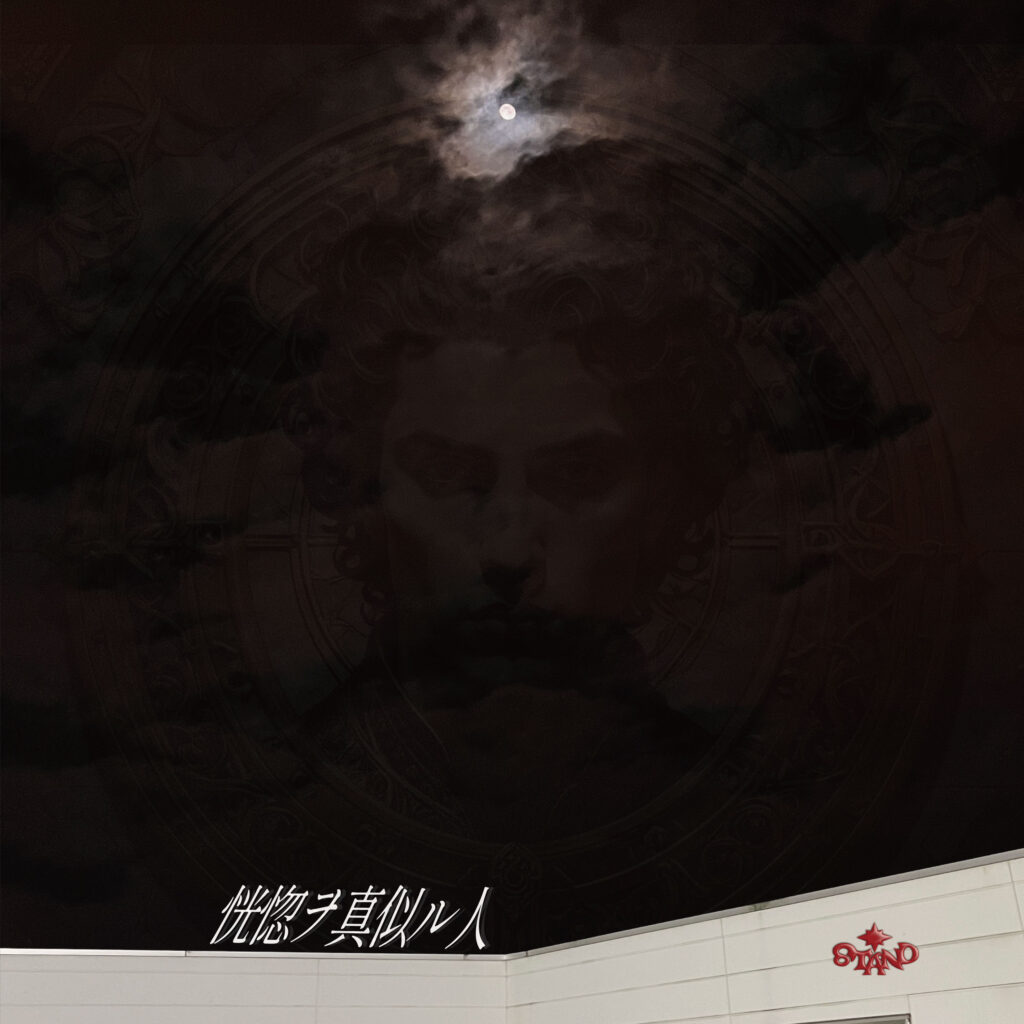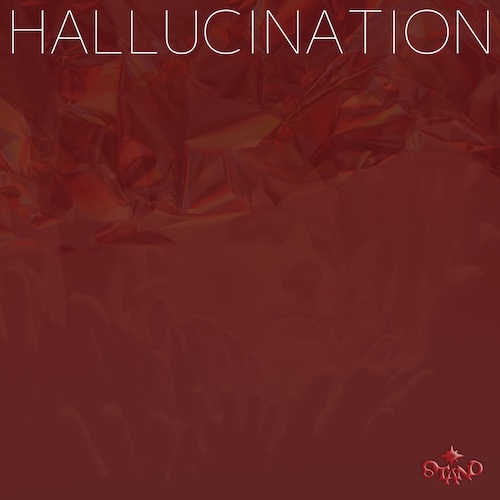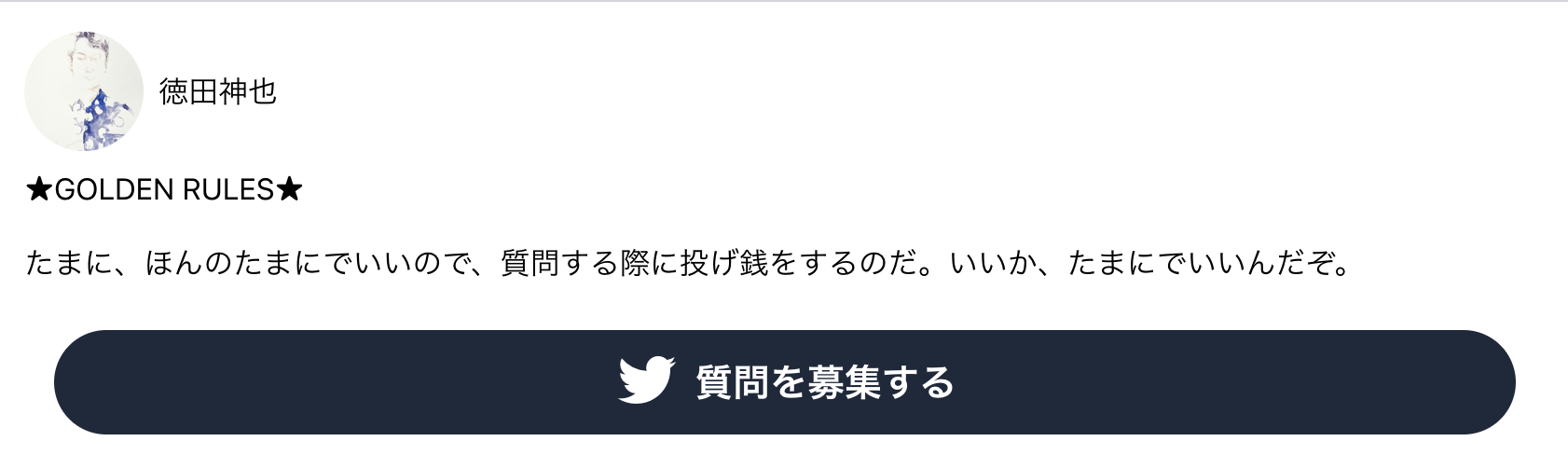関東平野の土層は「ローム」と呼ばれる、火山砕屑物である。
約258万年前から約1万年前までに富士山・箱根山・愛鷹山などの火山から降り注いだ。
含有する鉄分が風化によって酸化している「赤土」が特徴である。
かつては土壌が悪く、農作には適さなかったが、江戸中期に盛んに改良が行われ、現在では土地にあった農作物が豊富に作られるようになった。
関東平野は日本で最も広い平野で、四国の面積に匹敵する。
※河川の堆積作用によってできた平野は、谷底平野・扇状地・氾濫原・三角州などと呼ばれる。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
斎藤孝監修。自然、歴史、文学、科学・技術、芸術、伝統・文化、哲学・思想の7分野からの、日本にまつわる365日分の知識。この本をさらっと読み、知ってるようで知らなかったことをさらっと初めて知りつつ、ああそうなんだね~なんて知ったかぶりしながらほんの少しだけ、書くことを1年間続けます。最低限「350ページ以上ある本を読んだよ!」の事実が残るだけでも、価値はゼロではあるまいて。言わんや「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことかと。
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365