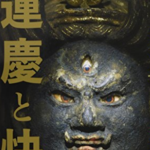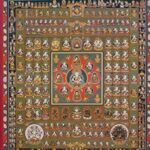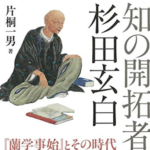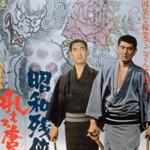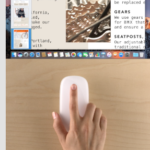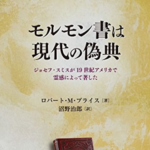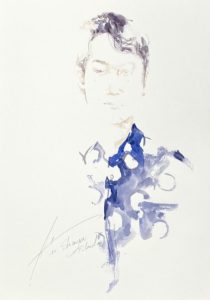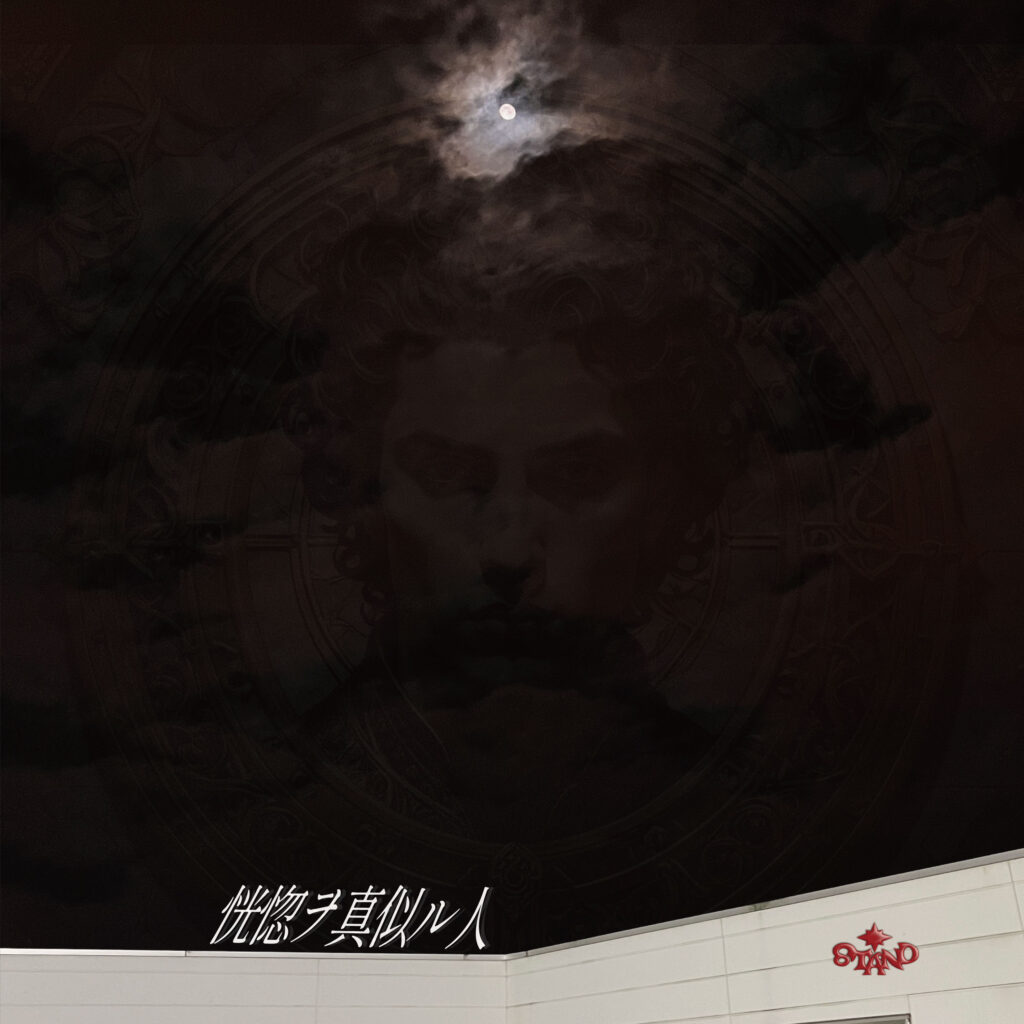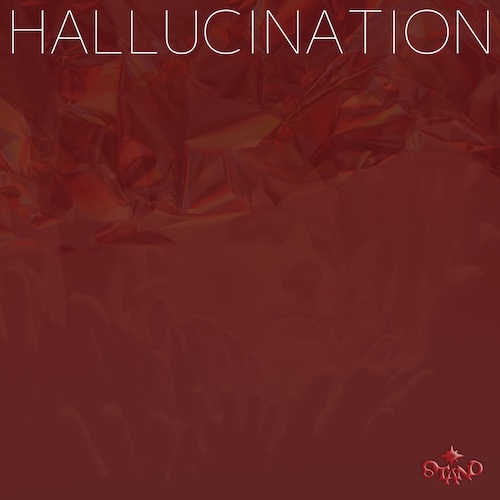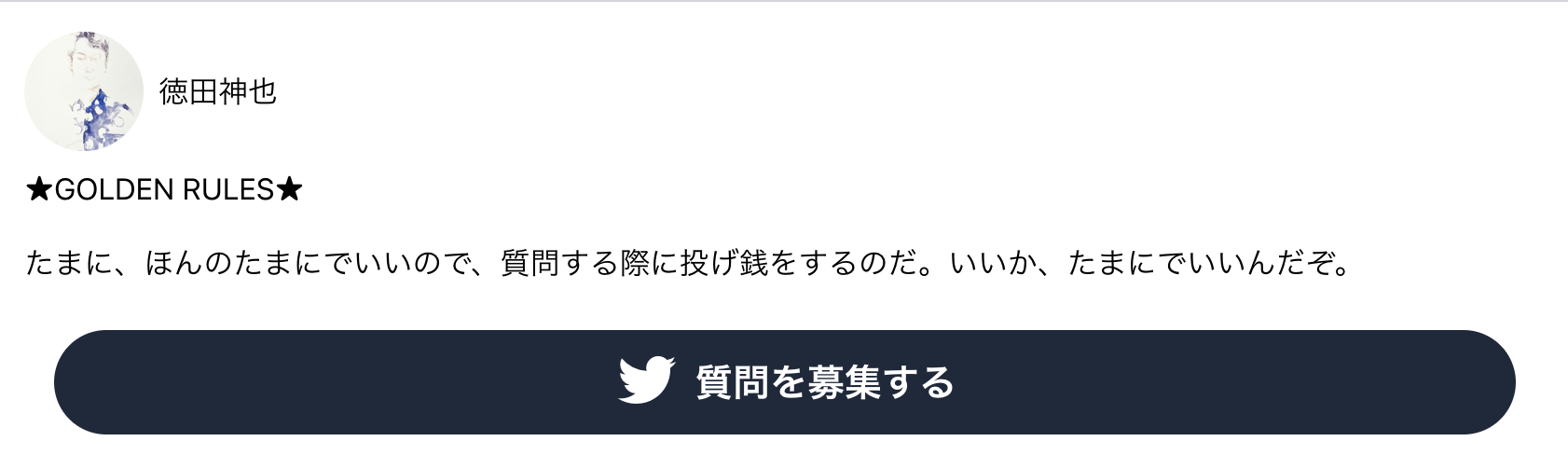平安時代には、端午の節句に天皇が武徳殿からお出ましになり、臣下と共に宴を催し、弓を射る「端午の節会」が行われていた。
江戸時代になり、菖蒲で邪気を払う風習が「尚武(武を重んじること」に通づると言うところから、男子の節句になっていったと言われている。
鯉のぼりは武家の旗指物の代わりに庶民が考案したものだったが、のちに武家でも立てるようになった。
柏餅を食べる風習は日本独特の物で、新芽が出なければ古い葉が落ちない柏の木の習性から、子孫繁栄の縁起物として尊ばれ、広まった。
※赤い緋鯉はもともとは子供たちを表していたが、昭和40年代ごろから「お母さん」という扱いになった。
(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)(“▽”)
斎藤孝監修。自然、歴史、文学、科学・技術、芸術、伝統・文化、哲学・思想の7分野からの、日本にまつわる365日分の知識。この本をさらっと読み、知ってるようで知らなかったことをさらっと初めて知りつつ、ああそうなんだね~なんて知ったかぶりしながらほんの少しだけ、書くことを1年間続けます。最低限「350ページ以上ある本を読んだよ!」の事実が残るだけでも、価値はゼロではあるまいて。言わんや「教養が身につくかどうか」なんて、知ったことかと。
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365