 碁盤斬り
碁盤斬り
江戸の、下級武士たち
江戸には武士が集中して住んでいた。
江戸は、同時代の全世界の国々と比べても突出して発達した大都市だった。
全国の大名が将軍家のために忠誠を誓う証拠を示す場所でもあった。
全武士が、江戸城にいる将軍を気にしながら生きていた。
関ヶ原の戦いが1600(慶長5)年。
江戸を首府として徳川家康が開いた頃には15万人ていどだった人口は、1657(明暦3)年には倍近くに達し、1721(享保6)年には50万人になっていたと推定されている。
この数字はあくまで「町人の人口」であり、実際にはここに、全国から集まった武士・浪人が加わって、それぞれの妻子をプラスすることで江戸は「100万都市」となっていたのである。
全国の大名は、参勤交代で必ず毎年江戸と領地を往復しなければならず、滞在時のために江戸に屋敷を持たなければならない。そこに妻子や子供を幕府への実質的な人質として常住させなければならないし、その世話をする家来たちも、江戸にいることになる。
さらにその家来たちの郎党たちもまた江戸に住むことになるのだから交代はあれど、常に江戸には武士がたくさん留まっていることになる。
武士が常に市中にたくさんいる状態なので、参勤交代で出入りする大名行列に出会った時にいちいち町民たちが土下座をしていては回数が多すぎて大変、ということで江戸市中では、道の脇に寄れば良かったらしい。
江戸を出ると途端に土下座を強要されることになる。
これらがボーダーラインとなって、一歩でも出ると「土下座エリア」が始まったそうだ。
江戸時代に出来上がった価値観
徳川綱吉の時代、「武断政治から文治政治へ」という大パラダイム転換が起こった。
戦争に勝ち、殺しの技術でのし上がった徳川家康による「覇者の王都」だった江戸は、五代将軍の治世で「文化的平和都市」に変貌するきっかけを得た。実際、この頃から江戸は飛躍的に発展する。
現代にも通用する文化的素地はここで醸成され、特権階級である武士以外の知性・財力・嗜好が爆発する。辻斬りや切り捨て御免が当たり前だった乱暴な時代から、犬さえ殺すことはあいならぬ、という徹底した法治が進んだのだ。
落語の原型が出来上がったのも元禄年間(1688年〜1704年)であり、この頃には武士を凌駕するような権力・財力を持つ豪商も台頭してきた。
上方落語にはあまり、武士が出てこない。
大都市とは言え、大阪には武士が江戸ほどいないのだからしょうがない。
「政談もの」はもちろんあるが、それも「奉行と主人公」のような、特殊な例をモチーフにしている。
「武士がたくさんいる」という下地があってこその物語というのは、やはり江戸落語にリアリティがあると言えるだろう。
「人情噺(にんじょうばなし)」にカテゴライズされる「柳田格之進」には、「五十両」という金額が登場する。その点、まったく「文七元結(ぶんしちもっとい)」と同じだ。
「文七元結」も、五十両という大金が無くなるというところがトラブルのメインとなる。そして健気な娘が身を呈するところも同じだ。
どれくらいの価値があるの?
「どうしてくりょう、さんぶにしゅ」という決まり文句がある。
本来は「ふといやつ、どうしてくりょう、さんぶにしゅ」という川柳なのだそうだ。
どうしてくれよう、の「くれよう」と「九両」がかけてある。
さんぶにしゅ、とは「三分二朱」だ。
江戸時代は「一朱」が4枚で「一分(いちぶ)」。
「一分」が4枚で「一両」という計算だった。
一両=四分=十六朱ということになる。
「九両三分二朱」というのは、「あと二朱で十両に達する」というギリギリのラインを表している。
本当のギリギリなら「九両三分三朱」だと思うのだが、そこは語呂の良さを取ったと思われる。
窃盗で、その被害額が「十両」に達したら犯人の首が飛ぶ、という刑罰からから考えだされたシャレである。「ふといやつ」というのは「神経の図太い悪いやつ」ということだろう。
江戸時代は長いので貨幣価値も一定ではないが、そんな時代の「五十両」である。
「花筏(はないかだ)」という噺には「提灯屋の手間賃が日に一分(いちぶ)」というところが出てくる。
提灯屋さんの日給は「一分」だというのだ。
例えば「一両」が現代の4万円ていどだとしたら、「一分」は現代の1万円ということになる。
五十両となると200万円。
もし「一両」を15万円だとして計算するならば、50両は750万円だ。
江戸時代、首が飛ぶどころの騒ぎではなくなるという不穏な感じがする。
200万円のカタにされてしまう娘・お絹。
いや、後者の計算例だとその身代金は750万円かも知れないが、なんら経験も教養も蓄積もない生娘を750万で買う女郎屋はいないような気がする。今でも人身売買の相場は成人女性で200万円だそうだし(知らん知らん)。
吉原という悪所【五人廻し】
「文七元結」の主人公は町人である。
主人公の長兵衛がなぜ「なんで?なんでそうなるわけ?」っていうくらいに意地っ張りで人情深いのかと言うと明治初期、維新後に薩長の男たちが江戸に溢れている状況を苦々しく思った作者が、江戸の心意気を示そうとして作ったからだという。
もしかしたら「柳田格之進」も、同じ動機で作られたのかも知れない。
「正直すぎる」から讒言(ざんげん)にあい、浪人してしまった柳田格之進。
地方の藩の侍だったはずなのになぜ江戸にいるのかというと、おそらく江戸住みだったのだろう。
お役を得て、江戸屋敷に勤める下級武士。可能性としては在住だった彦根から、近所には住めまいと放浪して大都市・江戸に流れ着いたのかも知れないけれど。
舞台とされる浅草阿部川町(あさくさあべかわちょう)は、現在の元浅草三・四丁目あたりのことらしい。
哀しいけれど、武士とはこういうものよ…、という愁いをこれでもかと見せつけるこの噺、やはり武士とは言え、江戸末期には困窮した層がかなり多くいたことを考えさせてくれる。
下級武士の俸禄などはうだつの上がるものでは決してなく、誇りと矜持だけを頼りに耐え忍ぶしかなかった。それが、その苦しみが、実は明治維新の原動力の一つだったのではないかと思う。
つまり腐敗した末期症状の徳川幕府では、武士の身分だけでは飯すらまともに食えないという状況で、各藩に帰属するとは言え「武士」というステータスは貨幣経済の中、現実的には決して社会的上位を保証するものではなかったということだろう。
町人の方がよっぽど豊かに、楽しく生きている。
武士は武士であるがゆえに、ただそれだけの理由で、家族にさえ塗炭の苦しみを味わわせねばならない。
しかも幕府はおろか主家に逆らうことなど出来ようはずもなく、武士道と朱子学でがんじがらめの倫理感に囚われて、鬱積と借金だけが膨張してゆく。
厳しい身分制度が、制度疲労を起こし、逆に大きな不満の種になった。
もちろん外国からの黒船来航や開国を迫る圧力もあるが、外圧だけでなく内側から改革が起こったのは、下級武士たちの「静かな反乱心」がベースになったからだと言えると思う。
「武士道」の弊害
「武士の魂」を持つ柳田格之進は、窃盗の嫌疑を晴らすため、自ら腹を切ろうと決意までする。
これも、「武士がダメになった理由」の一つに数えられる気がする。
日本人として、伝統として歴史的事実として、自ら赤き心を見せるために自害するというパターンはたくさん知っているし、それが「名誉ある死」であることも理解している。
が、が、それは逆に「自分が死にさえすれば一見落着(へ向かわざるを得ない)」、という、本質的解決とは程遠い「ハック」になってしまう側面を持っている。
問題が解決していようとなかろうと謎が解明されようとされなかろうと、「当事者が死ねば済む」という事実は「水に流す」という解釈に直結する。そして幕引きに雪崩れ込む。それを「責任を取る」と呼ぶ。
日本人にはこのメンタリティが、いまだに叩き込まれている。
疑われたら即座に自死する。現代に生きる我々にしても「そんなのは馬鹿げている」と思う一方、どこかで「この命と引き換えに」や「死ねば仏だ」という免責方法が隠れている、隠されていて欲しい、という気持ちがあるような気がする。
やるべきことは、努力すべきは、心血を注ぐべきは「真相の解明」であって、そのためには理路整然とした弁解やアリバイの証明、証人の喚問など、やるべきことがたくさんある。
なのに頑迷な武士たちは、「嫌疑をかけられたことそのもの」を「恥」と感じて、「死ねばその恥は雪がれる」と考えてしまうのである。「自ら死を選ぶのだから、潔白だったのだろうと思ってもらえる」という、一方的な信頼感に依存しているようにも見える。なぜなら、中には「逃げるように死んだってことは犯人だったんだろう?死ねば潔白だと思われると思って死んだんだ!」と、計算づくの自決だと勘繰る人間もいるであろうからだ。恥と死が直結している。これを止めるには、愛する娘の涙の嘆願が必要だった。
白石和彌監督の映画『碁盤斬り』
草薙剛主演の映画『碁盤斬り』では、豪商にあらぬ五十両紛失の濡れ衣をかけられた顛末だけでなく、実は彦根藩を追われた発端と復讐にフォーカスが当てられていた。もちろん、そんな嫌疑をかけられるような逼迫した暮らしは、讒言から浪人になった流れに原因があるわけだから重要なわけだが、落語では語られない創作の部分はシームレスで見事であるし、この部分を人情噺として、今後、落語にプラスしていただきたい、と思うくらいだ。
娘のお絹(清原果耶)が吉原大門に消えていくシーンは、当時「苦界」「悪所」とも呼ばれた大歓楽街の、「遊ぶ場所としてはかなりの憧れだが想い人がいるとなると強烈に悲嘆」という、当時の人も抱えていたであろう矛盾を現しているように見えた。
上方では成立しなかったであろう「武士の矜持モチーフ」。
講釈から発展したからか笑いこそほぼないが、「なぜこんな噺が作られ、残されているのか?」を考えると、150年を経ても「美徳」の感覚は断片的に、現代人にも受け継がれているのだろうなぁと感じる。
柳田格之進の思いや行動原理を、我々が少しでも理解できるというのがその証拠だ。

 鎌倉殿の13人 第24回『変わらぬ人』
全武士・全鎌倉・全源頼朝の欲望が詰まった...
鎌倉殿の13人 第24回『変わらぬ人』
全武士・全鎌倉・全源頼朝の欲望が詰まった...
 夢は必ず叶う?ダニング・クルーガー効果とは。
「さすが豪将。むむ、しかし激戦だったと見...
夢は必ず叶う?ダニング・クルーガー効果とは。
「さすが豪将。むむ、しかし激戦だったと見...
 「わかりみ」。
いったん自分の理解度とは離れて、客体的な...
「わかりみ」。
いったん自分の理解度とは離れて、客体的な...
 「三度目の殺人」の評判がすごすぎる
考えざるを得ない示唆をいただき、ありがと...
「三度目の殺人」の評判がすごすぎる
考えざるを得ない示唆をいただき、ありがと...
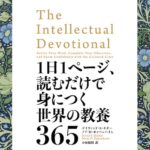 中世/初期教会音楽 026/365
ミサで唱える典礼文には、「通常式文」と「...
中世/初期教会音楽 026/365
ミサで唱える典礼文には、「通常式文」と「...
 GoPro 13BLACKで、「Youtube縦配信」はできません!
YouTubeは「縦画面での使用」を暗に...
GoPro 13BLACKで、「Youtube縦配信」はできません!
YouTubeは「縦画面での使用」を暗に...
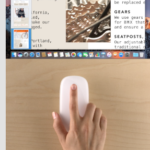 Chromeが勝手にズームする原因がわかったよ(Mac)
以上です(๑ ̄∀ ̄)
Chromeが勝手にズームする原因がわかったよ(Mac)
以上です(๑ ̄∀ ̄)
 今年は靖国へ行かれず(かわりに護国神社へ)。
あれ、コスプレですからね。戦争コスプレ。
今年は靖国へ行かれず(かわりに護国神社へ)。
あれ、コスプレですからね。戦争コスプレ。
 今さらながら「キングダム」ぜんぶ読んだム。
そう言えば印象的なエピソード、ありました...
今さらながら「キングダム」ぜんぶ読んだム。
そう言えば印象的なエピソード、ありました...
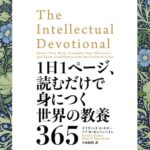 皇帝コンスタンティヌス一世 043/365
コンスタンティヌスのキリスト教への改宗・...
皇帝コンスタンティヌス一世 043/365
コンスタンティヌスのキリスト教への改宗・...
 昭和残侠伝 吼えろ唐獅子
因果な稼業でござんすねぇ!って…誰のセリ...
昭和残侠伝 吼えろ唐獅子
因果な稼業でござんすねぇ!って…誰のセリ...
 華道(生け花) 090/365
室町時代中期に東山文化の影響で「立て花」...
華道(生け花) 090/365
室町時代中期に東山文化の影響で「立て花」...
 JAFのすごいところと唯一の不満(マルチなんかやっとる場合か!)。
要するに車乗ってる人はJAF、入っておい...
JAFのすごいところと唯一の不満(マルチなんかやっとる場合か!)。
要するに車乗ってる人はJAF、入っておい...
 恍惚ヲ真似ル人
配信が開始されました。
恍惚ヲ真似ル人
配信が開始されました。
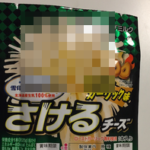 避けないチーズ
ないですよ、めったにない。
避けないチーズ
ないですよ、めったにない。
 ブリーズライト、では無い方を。
「あれ?俺いま、メガネかけてる?」って思...
ブリーズライト、では無い方を。
「あれ?俺いま、メガネかけてる?」って思...
 ジョジョ展2017その3【OWSON編】
さらに、なぜか「からあげクン」をかうと、...
ジョジョ展2017その3【OWSON編】
さらに、なぜか「からあげクン」をかうと、...
 差別は、誰がどうやって作るのか。『イノサン』。
それはなぜか。「死穢に触れる仕事」だから...
差別は、誰がどうやって作るのか。『イノサン』。
それはなぜか。「死穢に触れる仕事」だから...
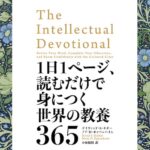 ゴシック美術 045/365
そもそもは古代ローマ帝国を侵略した蛮族「...
ゴシック美術 045/365
そもそもは古代ローマ帝国を侵略した蛮族「...
 変なすごいおじさん
たった24年で…と全員集合…と思わざるを...
変なすごいおじさん
たった24年で…と全員集合…と思わざるを...