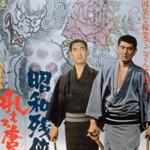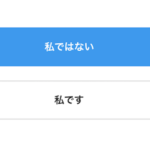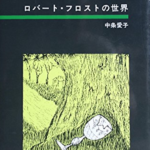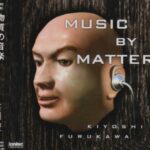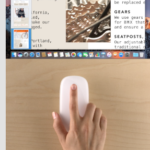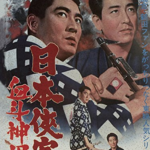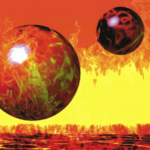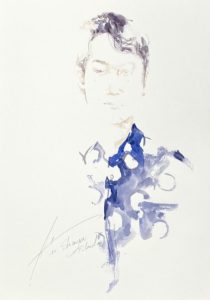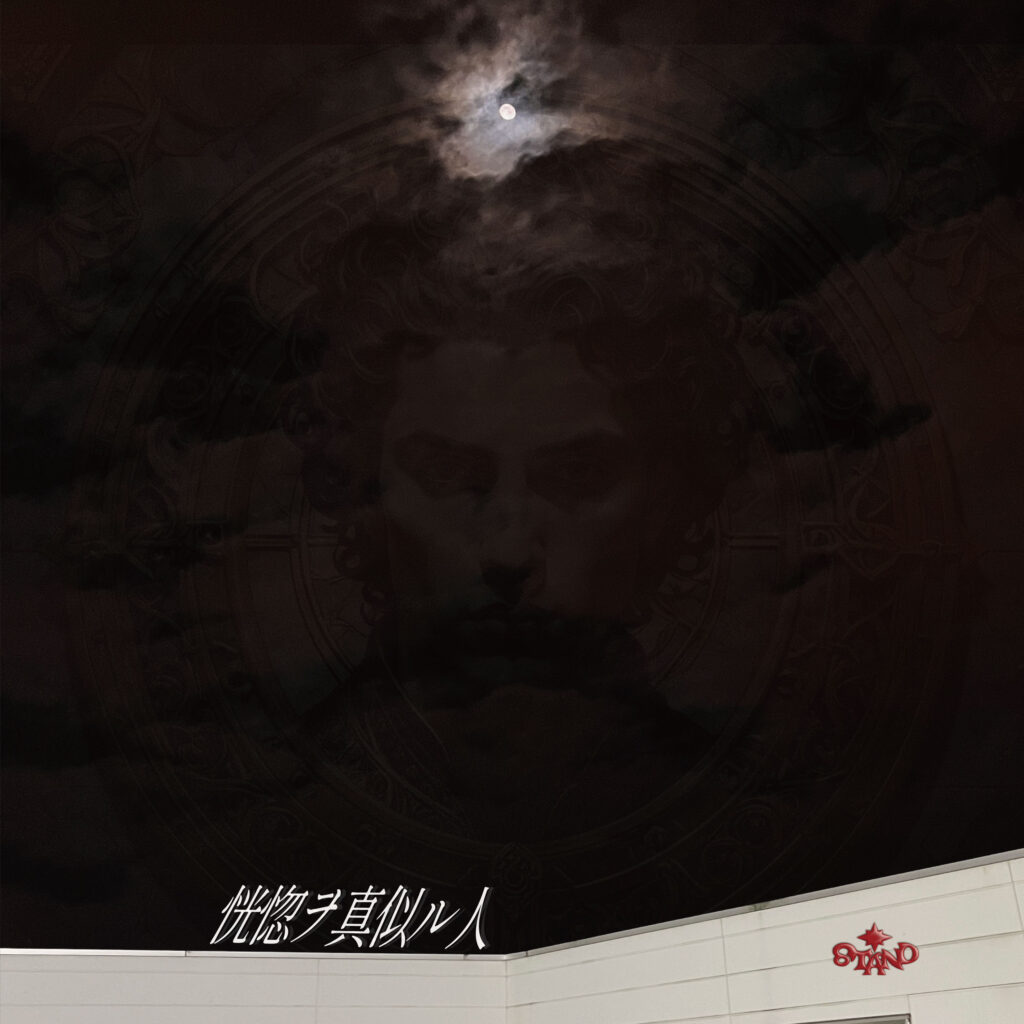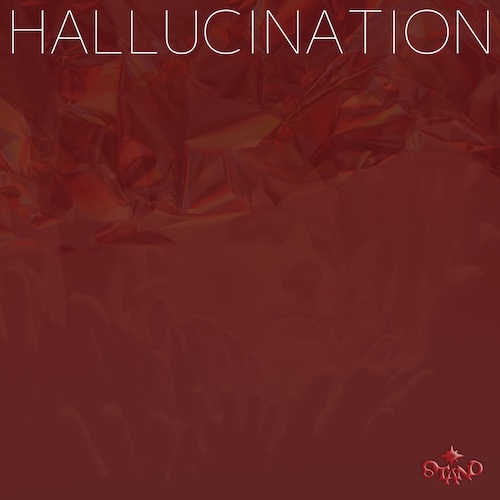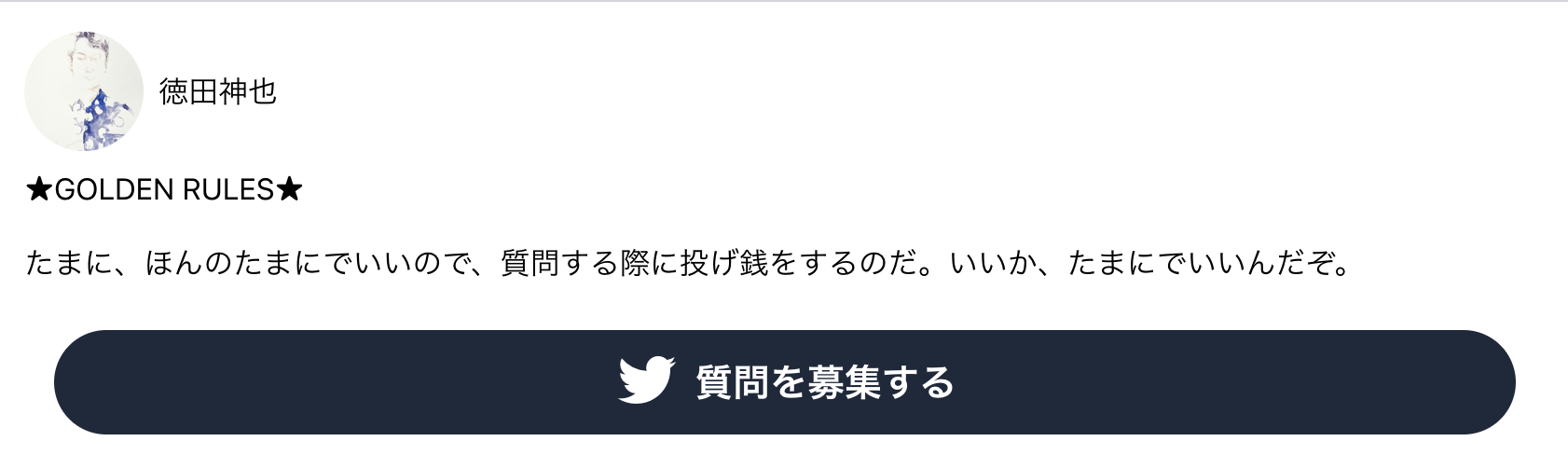どえらいベストセラーになっています。

ここ数年で、彼が、父である落合信彦氏の知名度を上回ってくるなんて、誰が想像していたでしょうか。
いえ、知っている人は知っていた天才。
情熱大陸で「レトルトカレーは飲み物です」な姿を見せたことでも話題になりました。
タイトルはまるで田中角栄の「日本列島改造論」、小沢一郎の「日本改造計画」を彷彿とさせるけど、中身はカタカナだらけw
新しいテクノロジーと現状、消え去るべき思考と直視すべき現実、それらの複合的なややこしい情報が端的に、まるで一度噛み砕いて細かくした獲物を親ジャッカルが子ジャッカルに吐き出して与えるようにわかりやすく解説してくれています。
一度、彼の講演を聴いてみるといいです。
この喋り方、スピード、情報量。
この講演を聴いてからこの本、『日本再興戦略』を読むと、彼の喋り方で脳内再生されるので、意外と早く読み終われますw
今回、注目したいのは「第4章」です。
もちろん、他にも興味深く、現状と未来を見据えた提言がところ狭しと並んでいて、ことあるごとに今後「えーっと、あのことについてはなんて言ってたっけな…」なんて、リファ本として使う人も多いんじゃないかと思います。
「第4章」の特に前半。
これは見解として、その裏付けが明確に書いてあるものに初めて接したという意味で、とても衝撃でした。
この章のすべてを丸写ししてもこの『日本再興戦略』の価値は衰えない、というくらいに他の章もおもしろいんですけど、それは面倒だしやめてw、どういうことが書いてあったのかをちょっとだけ紹介したいと思います。
なんと、「少子化・高齢化、それって良いじゃない!?」ってこと。
こんな意見って聞いた事ないでしょう?
たいていメディアでは「少子高齢化」は、「嘆くべき現象」という文脈で使われる言葉ですから。落合氏は「少子高齢化、これはチャンスだ!」とハッキリ明言しています。
理由も、とてもわかりやすい。
「機械化に、反対する奴がいねえから」だと。
こんなガラは悪くないです、文体は冷静で沈着。
人間が機械に置き換わる…ということに対する嫌悪感は、おそらく年齢が高ければ高い方が多い。
でも、実際は機械に助けてもらう機会も、年齢が高くなればなるほど上がって行く。機械と言っても、ロボットと言っても、そんな、マグマ大使みたいな奴がなんでもやる…ということではないですからね。
人口減少と高齢化を「チャンス」ととらえる理由を本書では3つ、挙げています。
1つは、上にも書いた
・機械化して行くことへの反発が起きにくい
コンビニは、店の前か店内のスペースでスマホでアプリから商品を選択し、決済を済ませ、それに応じた商品が取り出し口から出てくる。今のガソリンスタンドの「セルフ」と同じで、一応警備と説明の店員1人くらいはいてもいいのかも知れないけど、無人化できる。なんだか万引きが心配…とか人と人とのふれあいが…とかすぐ言いたくなりますけど、まずその「人がいなくなるから」っていう話をしてるんですよw
2060年までには6000万人くらいにまで減ると言われている日本の人口。単純に、すべてのお店のスペースや在庫が、半分でいいっていう状況だと言っていいでしょう。イオンモールとか映画館も、半分でいい。そんな中、無人化したお店は便利ですね。
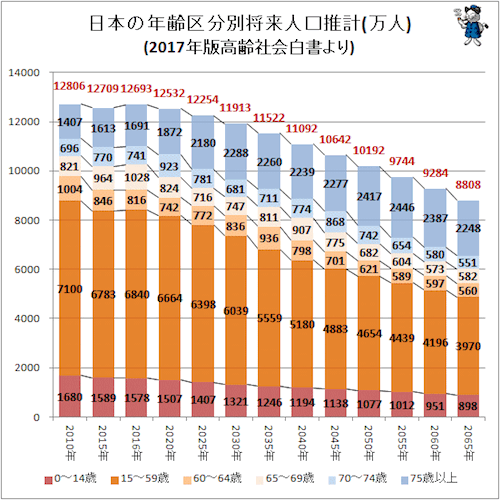
この「2017年版高齢社会白書」のグラフはもう少し緩やかな予想をしてます。それでも一度1億人を切ったら、そこからのスピード感はかなり、でしょうね。
内閣府 高齢社会白書
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
2つめは
・高齢化した社会にマッチしたことを産業として輸出していける
高齢化は、各国でどんどん起こります。
日本が、高齢化社会に合わせた機械化・産業化を本気で推し進めておけば、やはり地球上に住んでいるのは同じ人間ですから「か、介護用ロボ、日本製すげーな!」ってなるわけです。障碍者用のサービスやマシンなども、輸出産業として日本が豊かになる可能性を秘めている。中国・インドが高齢化したら、とてつもないでかい市場になる。その先端を、日本は走っている、というわけです。
そして3つめは
・子供が少ないがゆえに教育に投資を集中できる
1つめの「無人コンビニ」なんかが話題になると「スマホを持ってない人はどうすれば…」ということをおっしゃる方がいるんですが、教育に投資、というのは「スマホを持たせる」っていうことも含むでしょうね。スマホを使いこなせない子供、は今ですらあり得ないと思いますが、だいたい機械化に過剰に文句言ってくるのは、そういうのに適合できない自分を嘆く言葉は悔しいので吐きたくないわがままなジジババなんですね。そういうのが(そういうのってw)いなくなったあと、にどうするか、っていうお話です。
先日、中国の警察でウェアラブルグラス(メガネ型コンピュータ)が導入されたことがニュースになってました。
中国警察がロボコップ化! 「顔認証グラス」は犯罪者も誤魔化せない
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/02/post-9501.php
これのどこがロボコップなのかは良くわかりませんが(ちなみにロボコップという映画のキャラは日本のヒーロー「宇宙刑事ギャバン」がモデルらしい)、この端末を通じて、街角で「顔認証」とかやられたら…。
前に、日本の警察には指名手配の犯人などを人混みから探し出す「プロ中のプロ」がいるというのを聞いたことがあります。新宿や渋谷の雑踏に立って、行き交う人の中から特定の人物を割り出すベテラン。身長・性別・見た目。
この職人技に驚きましたが、データが常に送られてくる眼鏡型コンピュータでは、その照合は小数点以下の速さで行なわれる。そして適合率も100%に限りなく近い。そうなると、人員もカミワザも要らなくなる。「少子化・少人口と、テクノロジーはうまく融合する」というのは、そういうことですね。
著者・落合陽一氏は西洋と東洋の文化にも歴史にも触れつつ、「これからの日本に、未来はある」という例示を与えてくれ、希望を見せてくれる稀有な存在。
それは、「テクノロジーは自分が関わらなくても、いい感じに発展して行く」という明るい楽観に基づいているんだな、と感じます。
「少子高齢化でこれからの日本は…」という、悲観的な文脈で語られる時(そういう方が圧倒的に多い)、やはりそこには「人がいないと何も発展しないよ。」という、人海戦術的な、大量生産的な思考がある。これからの「機械化で人を減らせる」は、「巨大機械で大量に作る」を意味しません。「大量機械で人の仕事がなくなる」ことも意味しない。
「AIのせいで今後なくなる仕事・50」とかいう、危機感を煽る特集記事がよくありますが、「あっ、俺の仕事、機械にとってかわられちゃう!!」なんて嘆いている場合ではないんですよ。これは次の章に書いてあった話ですが、国防をちゃんと機械化すれば、戦争をしなくても済む(攻めにくいぞとなれば良い)し、実際に対人で戦わなくても良くなる。「人を殺すのだから、機械で冷酷に殺すのはアンフェアだ」みたいな、宮本武蔵の時代っぽい価値観もあるのはわかりますが、結局はマシンの発達であろうがなんであろうが「殺しあわない」ことが理想なわけで、「国防力」が人口(兵隊の人数)に比例しない、そんな時代になっていけばいいですよね。
良い面を見つけて、伸ばしていくしかない。それが「未来へ向かう」ってことだろうし、「再興」ってことだろうし「戦略」ってことでしょう。そんな…ロボットに人間様がとって変わられるなんて…と、嘆いているフリで、実はうまくイメージすらできないジジババどもは、結局は「何もしたくない」って言ってるんですから。未来を憂いているフリ、してるだけ。自分にはもう責任はない、と逃げてるだけじゃないですかそれって。
この本は、とても面白いです。
そして何十年後かに、しっかり答え合わせができるというのもすごい。さらに、今言われている科学的な課題、社会の問題、時代の要請、みたいなものが、一気に俯瞰できる。とりあえず意味がわからなくてもサラッと読んでおくだけで、「わかった気になれる」ww
有名になられたので、よくわからない批判で「とりあえず叩きたい」という人も増えてきたようですが、「情熱大陸」を見せていただく限り、流石にそんなのに関わっている非生産的な時間は、彼にはぜんぜん無いみたいですね。
思えばあれはかなり昔…。
はるかかなたの銀河系、あるところで偉いさんに「いろんなところからネタを拾って来んとあかん。例えば SPA!とかを読むとか…」なんてことを、聞いたんです私18。今思えば「偉いさん」と言ってもあの人は30代の課長クラス。たいして偉いさんでもなかったなぁなんてw
とにかく帰りに、なんばウォークの本屋へ寄りました。
「えーっと、なんだったっけ?」
アホな田舎者だった私はあの有名な雑誌名を覚えられず、「ああ、これか…」なんて手にとったんです。買って帰った。それは「SAPIO」だった。間違った。
そこからSAPIO、10年くらい毎号読んでました。確か「ゴーマニズム宣言」がSPA!から移ってきたくらいの時で、表紙はキング・カズだったかな…。
その当時は隔週で発売されてたんですけど、今、隔月誌になってるんですね。
その後、執筆陣の中の落合信彦氏の著作を、それはそれは読みました。そんな20歳。
これとか。
これとか(翻訳だけど)。
印象深く、すごく面白い迫力ある本が多かった。で40冊くらいを、ある時ブックオフへ持っていたら、本当に2000万分の1くらいの確率の奇特な、私を知ってる人が店員さんで「やっぱり勉強、してはるんですね…」とレジで言われてしまい「やっぱり…」ととても微妙な気分になった、という思い出が蘇ってきます。
そこまでが、毎回『日本再興戦略』の著者・メディアアーティストのご子息、落合陽一氏をメディアでお見かけする際にこみ上げる私的な記憶であり、そういうセットで私に、この『日本再興戦略』の内容は部分的に、しっかり定着していくのでありましょうや。
これも、読まないと。