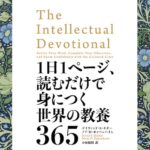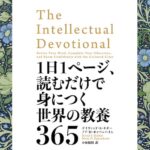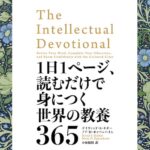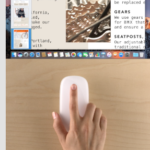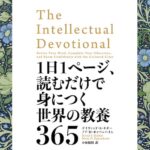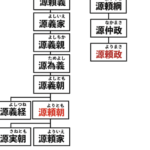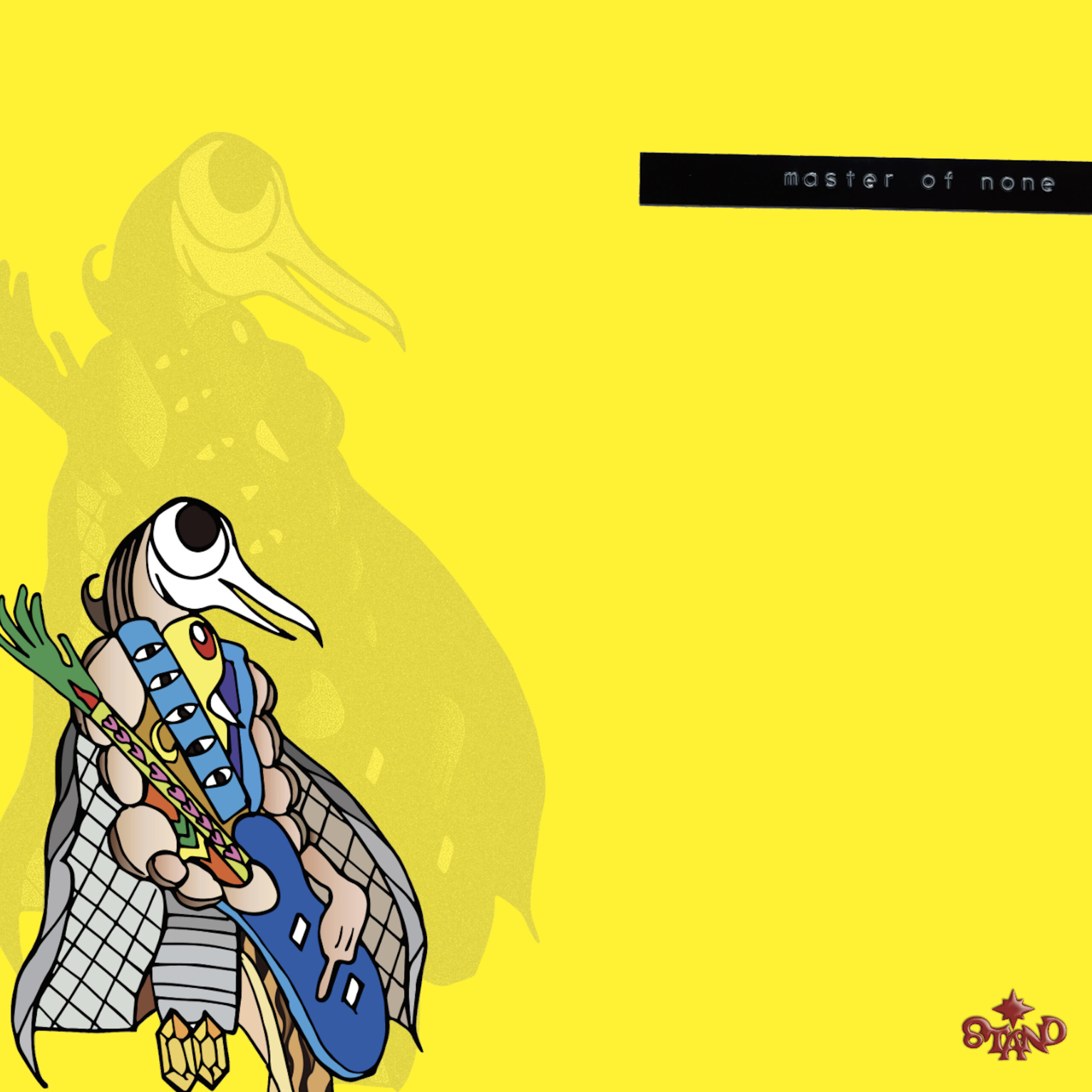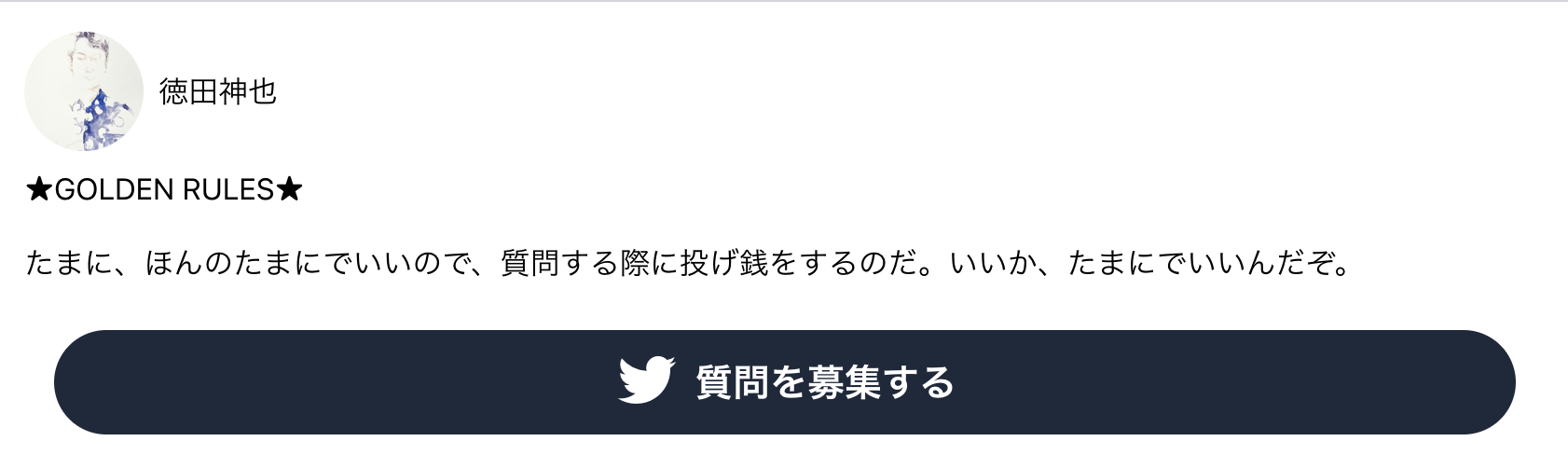「鰻の幇間」。
うなぎのたいこ。
よく聴いているのは六代目三遊亭圓生(以下、六代目)。
もう一つが、古今亭志ん朝(三代目。以下、志ん朝)。
あらすじとしてはレベルとしては中以下の幇間(ほうかん)が、旦那だと勝手に見定めた男性に一緒に鰻屋に連れて行かれ、うまくおだててご馳走になるつもりがコロッと騙されて先に帰られてしまい、そこそこのお代をすべて払わされてしまう…というもの。調子だけが良くその場しのぎで芸の程度も低い芸人が、いっぱい食わされるという話。
幇間(ほうかん)というのは「太鼓持ち」のこと。でも「じゃあ太鼓持ちって何?」と問われたら正確に説明できる知識はない。
なぜ、かの稼業を「太鼓を持つ」という表現によって仕事名としたのか、その過程はどこか「芸者」「芸者遊び」という文化の中で派生してきた「洒落た言い回し」だったのだろうと推察するしかない。力士のことを「相撲取り」と言うように、いつしか幇間のことを「太鼓持ち」と呼ぶようになったのだろうか。だけど太鼓を叩くミュージシャンの側面は薄い。
一説には豊臣秀吉が抱えた「御伽衆」が、ヨイショついでに秀吉を「太閤!太閤!」と持ち上げたことから「タイコウモチ」になり、その姿勢と音感だけが残った、とも言う。ほんとかしら。
幇は助ける(自殺幇助とかの幇)、間は人の間、または間(ま)、か。
間をつなぐ・間を助ける・間を取り持つ…となると御座敷での存在としてのありがたみがなんとなく、わかる気がする。
女性ばかりの「性的な目的を含んだ遊び」だけでなく、そこに「粋」や「洒落」を織り込んだ落ち着きや抑制性・爆発性を添える役割も、果たしていたのかもしれない。
「幇間」と書いて「たいこもち」あるいは「たいこ」と呼んでしまうのが落語における符丁(そしてそのまま演題)になっている。そう言えば落語の中では相撲取りも、略して「相撲」と呼ばれていたりした。
芸者と言えば普通、我々は女性を想定する。
だがもともとは、芸者というのはそのまま「芸をする者」であり、男性のみを指していたという説がある。なので女性の場合は「女芸者」と呼んでいた。現代の「女芸人」というに呼応する部分でもある。現代では逆に幇間を「男芸者」と呼称したりする。
それでも六代目・三遊亭圓生の「ウナギのタイコ」のまくらでは、「太鼓持ちが自分で芸をする、これはあまりよくないんだそうですね、」という説明が入る。
「お客に芸をさせて、それを褒める」のが太鼓持ちの本分だというのだ。
三味線・太鼓・踊り・謡い、それぞれのジャンルにはプロの「芸者」がいるわけだから、いわばそれらの劣化版を披露して、たとえばわざと失敗でもして笑いにする…「笑われる芸」としてはそれでいいのだろうが、そんなものが、粋を極めようと散財を重ねる、歴戦の道楽者にいつまでも通用するとは思えない。やはり座談に優れ、話題にことかかず、すべてに多いて気配りが利き、「そばに置いておいたらなんだか良い」と思わせる空気感が必要だったのだろう。その方が、自分で芸をするタイプよりも「長持ちして収入が高い」ということなのだろうと思う。なんとなくわかる気がする。
古今亭志ん朝の録音のまくらからは、「お客にさからう」というテクニックを知ることができる。お客(金持ち)が、「これはこうだよ」と言う。「いえ、それは違うんじゃないですか?」と異論を唱える。「何言ってるんだ、こうだよ!?」とお客はイラッとして押してくる。「まぁわかりますけど、その考え方はどうも違うっぽいですよねえ…!?」と、もう一回くらい逆らってみる。するとお客はさらに興奮して「なんでだよ!?これこれこうだから、こうなるじゃねえか、だからこうなんだよ!!」と強弁する。このあたりで「…あ!なるほど!なるほど!そうか!そうですねえ…!まったく!」と、意見が客の論理によって見事に覆った状況を作る。難敵を論破したような気分になって「こいつには口で勝てる…!」というような優越感と自らの論理的優位を誇れる気持ちも得られて、お客はスーッとするのだそうだ。
なんとなく日常でも使えるテクニックのような気がする。
暑いねえどーも
猛暑の中、涼しい避暑地や御座敷に直接呼ばれる有能な太鼓持ちと違って、路上で誰か取り巻いてなにかご馳走になってやろうという了見の、あまり上等でない部類の幇間が、向こうからやってくる浴衣がけの旦那っぽい人のことを見つけるところから、噺は始まる。
この時点で「あの人は誰それ」ということが判別できていないところが、この主人公が「負け」る原因だったりするのだ。一流ホテルのドアマンは客の顔・会社・役職・車など、5,000人分を記憶しているという。壮絶な努力なくしてそんなことは不可能だと想像できるが、野幇間(のだいこ。すぐ変換された)だとそうはいかない。そもそも幇間という職業じたいが、頭がよく機転が利かないと成り立たない商売であることは間違いないが、誠意ある人と、要領だけでこなしている輩とには雲泥の差があるのだろう。この噺にはその意味で、教訓めいたものを感じてしまったりもする。
「1000のうち」???
これは「先の家」だと思う。
「せんのうち」。
おそらく「こないだ教えた家」とか、「以前に来たことある家」という意味だ。「先立(さきだ)って」や「先達(せんだ)って」という言い方があるから、それを踏まえた粋な略し方、ということになるのだろうか。
知ったかぶりをして取り巻こうとした意地汚い幇間だから、「ほら、こないだの。知ってるだろ?」と言われると「ええ!もちろん知ってます!知ってますとも!」と答えるしかなく、具体的な説明をあらためて聞くに至らずさらっと流されてしまう。ほんとは知らないのだ。ぜんぜん情報が増えない。この「せんのうち」に対して、しっかり「どこでしたっけ!?すみません、教えてください!」と、正直にしつこく頭を下げて聞き出すことができなかったのがこの幇間の、一番の敗因と言える。
とは言え、相手は最初から騙すつもりなので「せんのうち」以上の情報は出すつもりがない。幇間の知ったかぶりを逆手に取っているのだ。
六代目・三遊亭圓生の録音だと、ここにすごく不透明な印象がある。
なぜなら、その「せん」にあたる過去のポイントが、聴いている者にはわからないのだ。「せん」がいつのことを言ってるのかわからない。とにかく知り合い、以前から知ってる、だから「せんのうち」も知ってるだろう、という部分に、少しだけ強引さがあるような気がする。本当に知り合いなのか(麻布の寺で会ったのは本当なのか!?)
古今亭志ん朝の録音の方は、この「先の家」というのを、幇間みずからが口にしている。「私、わかってますよあなたのこと!」という出会い頭でのカマかけが、結果的に彼にとって逆の効果を発揮してしまうのだ。あとで相手に「ほら、先の家だよ」と言われてしまうと、自分で知ってると言い出した手前、「えーと、どこでしたっけ…?」とは言いにくい空気を作ってしまった。そして後悔もする。「なんで先の家なんて言っちゃったかなぁ」と。これでうまくいったパターンも、過去にはあったのかも知れない。
この点、六代目の録音では浴衣の相手が「先の家」だと最初に言いだす。
だから「えーと、どこでしたっけ??お宅は?」と幇間が聞く。そういう場面が2箇所も出てくる。だけど相手はめんどくさそうに「知ってるじゃねえか先の家だよ」としか言わない。幇間は「さいですかへぇ、あたしゃまた、何かと思ってましたゴニョゴニョ…」とごまかすことになり、住居の具体的な場所は突き止められずじまいで終わる。遊びに来い、だの役者地の浴衣をやる、だのと体のいい提案は出るが、場所そのものが「もともと了解済みの事項」として話が進むので、幇間としては具体的作戦が立てられず、気もそぞろである。
けっきょく、ここで「先の家」たる相手の住居を突き止めることができない(相手は最初から知らせる気はなかった)ので、逃げられてしまい、そのあとを追うこともできなくなる。
逃げられ、鰻屋の支払いもさせられ、柾目(まさめ)の通った下駄すらも奪われる。
六代目の録音には、お土産まで持って帰られてしまった幇間が、そのお金を捻出する際の恨みごとを言う、というくだりがある。明るく陽気に遊び暮らしているような芸人稼業にも、暗く陰惨な苦労部分があるのだ…という側面を垣間見れるような場面だ。
六代目と、志ん朝と。
どちらの「鰻の幇間」が優れているか…を決めることはできない。
ほんとにできない。
お互いに、情報の質が違うからだ。
両方優れているとしか言いようがない。
六代目・三遊亭圓生(明治33年〜昭和54年)の話からは、「師匠から聞いた」というまくらを含め、本物の御座敷遊びと幇間が数多く生きていた時代の空気感がなまなましく感じられる。しかもこの録音は客前での公演ではなく、純粋な音声録音なのである。それだけに、六代目が頭に集中して描きながら語ったであろうイメージが、よりダイレクトに浮かんでくる気がするのだ。
古今亭志ん朝(昭和13年〜平成13年)の録音は、客前での演目なので笑いがぞんぶんに入っている。「どこで客がウケているか」によって、やはりその時代の空気感が、やはりわかるような気がする(おそらく1977年の録音だと思われる)。
両方に共通するのは「愚痴を言う場面での工夫」である。
こんな徳利にお猪口を出すんじゃあないよ、と愚痴る場面で、それぞれがその「絵柄」についての面白みを出している。掛け軸や鰻の質の悪さに文句を言ったりもするが、悪様に罵るその部分は、この話の一番のウケどころ、と言っても良いかも知れない。

鰻も幇間も、レッドデータである。
ともに絶滅危惧種なのである。
落語「鰻の幇間」の舞台は、江戸時代なのだろうか。
そうとも聴けるし、明治になってすぐくらい、とも受け取れる。「古典」とされているが明治の中期ごろには盛んに演じられていたというから、そのあたりにはまだ鰻も幇間も、高級な非日常をイメージさせるものとして、身近な娯楽に感じられるものだったのだろう。
けっきょく、幇間を騙して鰻をせしめ、上等の下駄まで盗んで行ったあいつは、誰だったのか。
オチまで聴けば悲喜劇として、幇間に対してなんて間抜けで情けないんだという印象で終わる噺だが、さかのぼればファーストコンタクトで、見事なまでにナチュラルに、立場を探る様子を気取られずに物事を運んでいくあの男の手腕。
手練れの太鼓持ち、なのか。
それなら界隈で出会って、業界人が知らないわけはないだろう。
もしくは、本当にイタズラ好きの大旦那なのだろうか。
のちにどこかでまた出会って「あの時はすまなかったなぁ、まぁいっぱいいこうや」と、ご贔屓にしてもらえたり、したのだろうか。
そこには「情報収集力は大事」だという、現代人が受け取れるメッセージがあるのかも知れない。
どことも言えない街角の、なんとも言えない鰻屋の二階で、熱風が吹く真夏の光景が、自分の思い出のように脳裏にこびりつく。
とても不思議な噺だ。