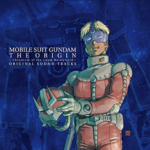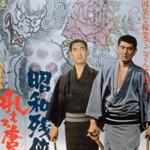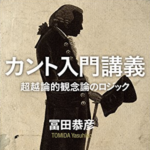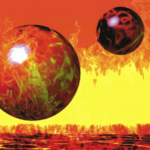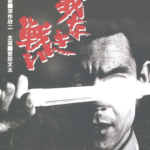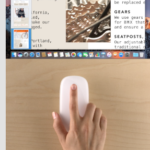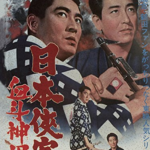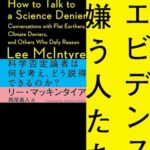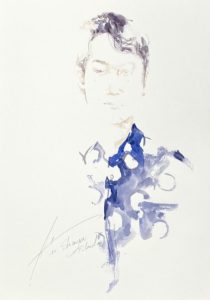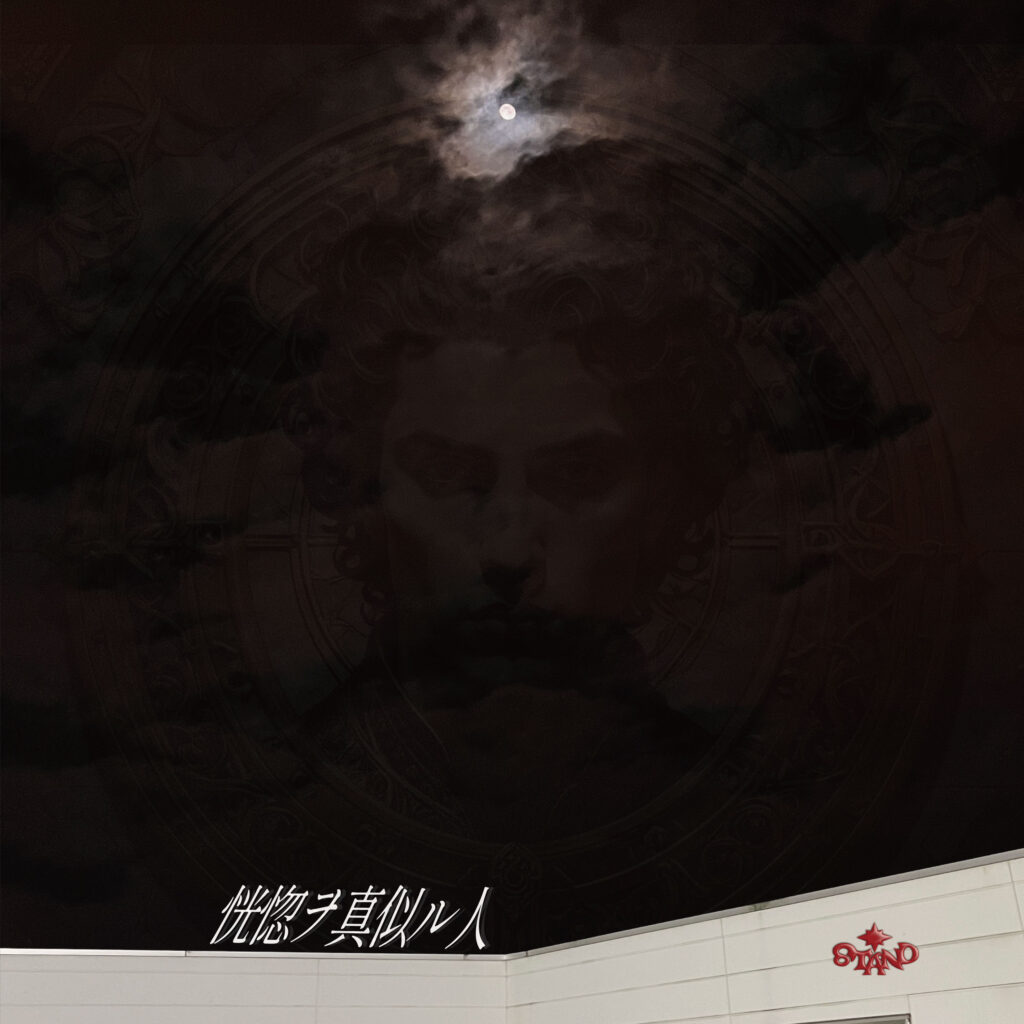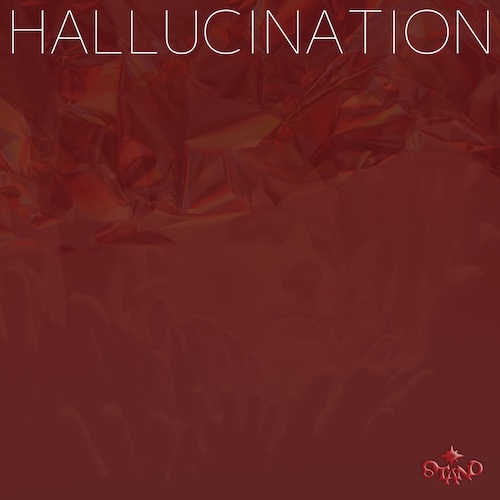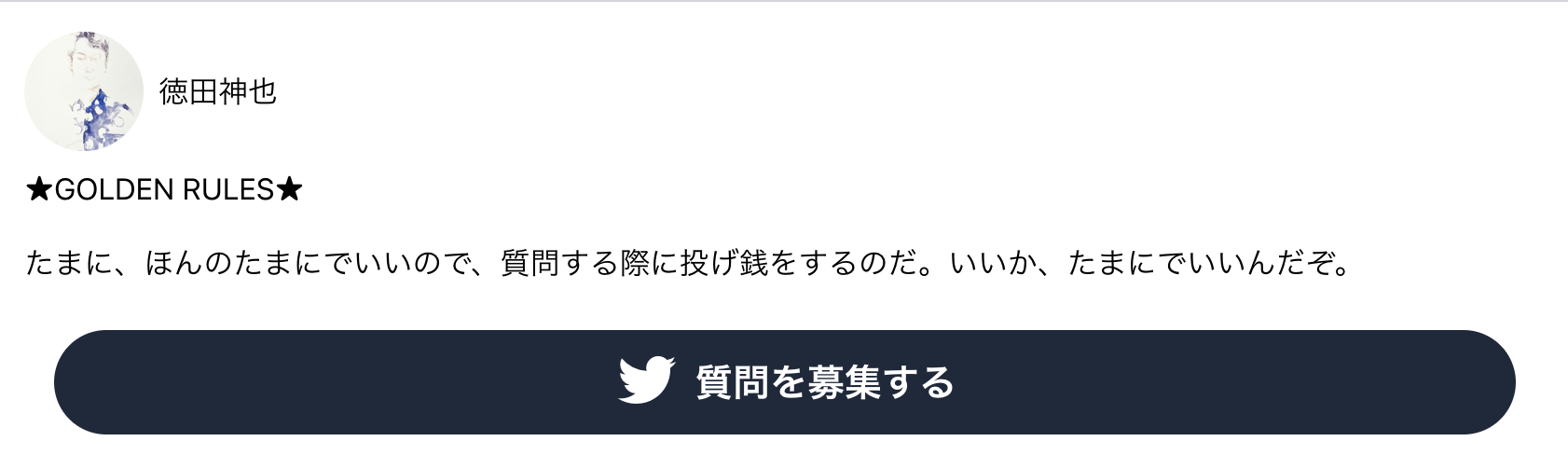\本日放送!/#鎌倉殿の13人
第27回「鎌倉殿と十三人」[総合]夜8時
[BSP・BS4K]午後6時#小栗旬 #小池栄子 #坂口健太郎#山本耕史 #中村獅童#佐藤二朗 #坂東彌十郎 #宮沢りえ ほか pic.twitter.com/NGaynuu7gX— 2022年 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」 (@nhk_kamakura13) July 17, 2022
権力継承の時は
あまりにも突然訪れた。
頼朝亡き後の大きな空白。
若き頼家はそれを、
埋めることが出来るのか。
後鳥羽上皇(尾上松也)、急成長
ドラマ冒頭、「武士にあるまじきこと」の流れで、源頼朝の死去の原因を陰謀ではなく「飲水の病(当時の糖尿病)」と喝破するシーン。聡明で、自分の意志・考えをしっかり持っている次世代の「治天の君」という描写でした。
源頼朝が死んだのは建久10(1199)年1月。
後鳥羽上皇が生まれたのは治承4(1180)年ですから、この時、彼はまだ19歳。
前年、18歳で皇位を譲っているので「上皇(太政天皇)」となっています。
彼は平家滅亡の巻き添えになった安徳天皇(あんとくてんのう・相澤智咲)の次に選ばれ、三種の神器が揃わないままで天皇に即位することになりました。
三種の神器のうち、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)は源義経(みなもとのよしつね・菅田将暉)の猛攻により、平家の人たちとともに壇ノ浦の海底に沈んでしまってついに見つからなかったのです。
何度も探索したそうですが、とうとう消失。
源頼朝は、源義経にその件で激怒したのでした。
形代(かたしろ)は造られたのでしょうけれど、「神器なき即位」になってしまった後鳥羽は、なんらかの強烈なコンプレックスを抱えていた、と考えられています。
中でも刀剣に対する異様な熱意を持っていたと伝えられ、「御番鍛治(ごばんかじ)」という制度を作って刀工に刀を作らせていました。
「太刀 菊御作(きくごさく)」と呼ばれる、自身で鍛えた刀まであります。
帝王は、普通そんなこと自分ではしませんから。
コンプレックスの裏返しなのか、彼は「強い天皇」「強い朝廷」をものすごく意識していたと考えられます。
皮肉にも、始まってしまった武士の時代に生まれた後鳥羽くん。
源義朝の偽ドクロ
「ニセモノが世の中を突き動かした」と、北条ヨシトキ(小栗旬)は、源頼朝挙兵のきっかけとなった、文覚(もんがく・市川猿之助)がもたらした亡父の骸骨を持ち出しました。
源頼家(みなもとのよりいえ・金子大地)はそれを継承する。
現実にはそんなものが正式な神器になるわけはありませんが、そうやって「源氏の嫡流」意識を強引にでも維持しないといけないのだ、という象徴として扱われました。
比企 vs 北条
比企能員(ひきよしかず)は、源頼家の乳母夫。
父・源頼朝時代からのつながりもあって、源頼家にとっては親しい家系です。
北条は当然、母の実家。源頼朝(みなもとのよりとも・大泉洋)挙兵からの重鎮、血のつながりがある家系。
「家の名で人を選ぶことは由とはせぬ」とはっきり源頼家が言い放った姿には、かつての日本史教育の中で刷り込まれてきた「源頼家はバカ殿。どうしようもないボンクラ。」というイメージを払拭する力強さがありました。
13人の合議制も、昔は「非常識で世間知らずでめちゃくちゃな暗愚の二代目・源頼家に、政治をさせないような体制」だと言われていました。近年の合理的な研究によって「源頼家は決して愚君ではない」ということがわかってきましたそうです。
どちらかというと「全国の御家人にこの権力を漏れさせないための一応の結束」みたいな感じだったのではないでしょうか。「混乱を最小限にとどめ、鎌倉に権力を集中させる機構」。
いわば「幕府執行部による寡占状態」を作る目的だった。
ドラマでも、昔の歴史漫画には必ず登場していたであろう、領土問題で訴訟を起こしている地図に真っ直ぐな線を筆で引いて「これで良いではないか、ワハハハ」と遊び半分で政治をやっていた源頼家像は、排除されていました。
自分なりに、若さゆえ、重すぎるプレッシャーに苦しむ姿が描かれていましたね。
そんな中、梶原景時(かじわらのかげとき・中村獅童)に対する憤りが、御家人たちの中で渦巻いていることが表出して来ました。
和田義盛(わだよしもり・横田栄司)が、源頼朝から直々に任命された侍所別当(さむらいどころ・べっとう)。
「別当」は長官で、梶原景時はこの職に就きたかったと言われています。源頼朝に願い出た彼は「所司)という副長官にあたる役職になります。そして実質的に権力を掌握し、とうとう別当の地位を、和田義盛から奪ってしまったのです。
初代の鎌倉殿のおぼえめでたき梶原景時、重鎮ぶって偉そうだったのか、どこかで「こいつのせいで九郎(源義経)殿が…」という思いが、「明日は我が身」を感じさせたのか。
感覚の絶対的な不理解
ドラマを見ていて思うのは「なんでそれで揉めてんの?揉めることじゃないでしょ?」というところ。
「それならそうで、“それはダメよ”って修正すればいいでしょ」とか。「とにかくすぐ殺すなよ」とか。
その不思議に対しては、現代の我々と感覚がまったく違う、というのが的確な答えだと思っています。
「殺せば解決」って、当時の武士、みんな思ってるんです。
紛争の解決、実は穏便かつスムースに運ぶには「皆殺し」が一番だよ、みたいな。
それはもう、我々からは想像しても難しいでしょう。
古代エジプト人の感覚を我々が理解できないのと似ていて、「同じ日本人」だけど、理解できる感覚が芽生えてくるのは室町時代を待たないといけない、という感じのようです。
おそらくその「殺して解決」の原因は、「大きな権威が白と言えば白になる」という世の中だからということなんだと思います。細い法律もないし、守るべき規定もない。全国一律の警察力はないし、照らし合わせる国際基準もない。
権力があらゆる訴訟を毎回その都度裁決し、それだけに理不尽な判決でも原告は聞き入れるしかない。控訴はありませんから。上告なんかしたらその方が罰を喰らいます。
武力(暴力)が背景にあるので、鬱憤が世代を超えて、溜まりやすい構造になっている。
ナイーブな鎌倉殿(二代目)は御家人たちの権力争いも毛嫌いするし、女同士の陰湿な鍔ぜり合いも嫌悪しています。銀の匙をくわえて生まれてきたような人物にとって、この世には無かった権力の座。参考にするのは亡父のみ。だけど真似をすると即・紛争になる感じ。
合議制が始まる?
北条ヨシトキは妙案を生み出しました。
若きプリンスを補佐するために、合議の場として「5人衆」を結成。
大江広元(おおえのひろもと・栗原 英雄)
中原親能(なかはらちかよし・川島潤哉)
二階堂行政(にかいどうゆきまさ・野仲 イサオ)
三善康信(みよしやすのぶ・小林 隆)
ここに梶原景時を加えた。
これらの5人は皆「官僚」なんです。
梶原景時は「坂東八平氏」に連なる武人でもありますが教養もあり、京に太いパイプを持つ文化人でもある。ただ軍隊を率いてる無骨な大将ではないんですね。
鎌倉殿に持ち込まれる政治的イシューのほとんどは訴訟であり土地をめぐる権利紛争なので、その会議メンバーを、冷静かつ論理的に物事を進める人らで構成するは当然の帰結です。
しかし比企能員は反発。
実は比企能員のあと、源頼家の乳母夫になったのが梶原景時で、その意味でもライバル心が燃えた。
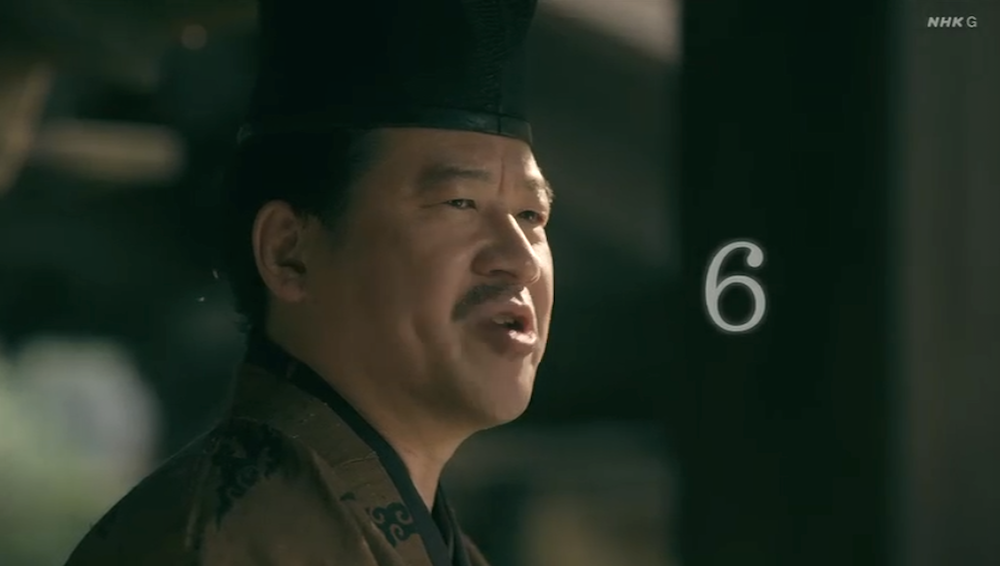
北条時政(ほうじょうときまさ・坂東彌十郎)も「わしも入れろ」で7人衆に。
比企の血縁として謀略で引っぱり安達盛長(あだちもりなが・野添義弘)で8人衆に。
北条時政によって昔からの誼(よしみ)で快諾した三浦義澄(みうらよしずみ・山本耕史)で9人衆に。
三浦義村の提案により和田義盛がなぜかやる気になり10人衆に。
和田義盛が嫌がった畠山重忠(はたけやまのしげただ・中川大志)は謹んで辞退。さすがです。
佐々木の爺さんこと佐々木秀義(ささきひでよし・康すおん)はすでに死んでおり、千葉常胤(ちばつねたね・岡本信人)はもうじき死ぬ。じいさんはやめておきましょう。いや、お前の父親もなかなかじいさんだぞ、よしむら。
比企による要請で参加した八田知家(はったともいえ・市原隼人)で11人。
「俺は俺だ」と言いながら金はしっかり持って帰る、よくわからない男。
知らぬ間に「一徹」足立遠元(あだちとおもと・大野泰広)が加わり12人に。
ラスト1人は…
合議制とは言え、大問題が起こるたびに13人が集まって喧喧囂囂の議論をして最善策を決めていた、とかそういうことはありません。「13人の会議」が開かれたことすらない。
北条vs比企という対立がある中、北条派・比企派はそれぞれ、過半数を揃えておかないと多数決で負ける…から人数で競ったんだろう、とか近代民主主義を軽くかじっている我々はすぐに思ってしまいますが、そんな学級会的な民主主義はこの時代に存在しません。
ドラマのタイトルに対して大変失礼ですが鎌倉殿の13人、にはほぼ、なんの意味もない。
彼らはお互い、仲良くする気などありません。
お互いに「なんとか殺してしまえないかな」という緊張感の中で生きている。
けっきょく最年少、北条ヨシトキがが加わり13人に。
一番若い北条ヨシトキが仕切ってるのは描写としておかしい感じもしますけれど。
ちなみに今回は
「#タイトル回収」がトレンド入りしていたそうです。
タイトルは「鎌倉殿の13人」ですから、『鎌倉殿と十三人』とはまったく違いますと思うんです。
「タイトル回収回」と呼ぶのは早計な感じします。
「鎌倉殿の13人」と『鎌倉殿と十三人』はぜんぜん違います。
「緊張の緩和」と「緊張と緩和」くらい違います。
ただタイトル回収、っていう言葉を使いたいだけなんじゃないの。
「鎌倉殿の13人」は言ってみれば「鎌倉殿と言われる新しい君主を中心とした武士による政治体制に現れた、かりそめの合議制を表す言葉」ですよね。
『鎌倉殿と十三人』は、「二代目となった鎌倉殿と欲得渦巻く御家人たちの、史上初の勢力争いの構図を表す言葉」だったりします。
中世ヨーロッパのイメージに置き換えると「若き王と、13人の貴族」っていう感じで、すんなり入ってくる感じもしますね。そこから始まる側近たちの、それぞれ一族を背負った貴族たちの、怒涛の権謀術数。毒入り酒を飲んで割れるグラス。宮殿に響く悲鳴。
ちょっとだけでも鎌倉幕府を知ってる方々は今、「確かにドラマは楽しみだ。が、しかし…」みたいな、史実を知ってるだけに暗い気持ちにもなってるはずなんです。政治運営もさることながら波瀾万丈っていうか、よくわからん策謀と、はっきりした大量殺戮が待ってるんだから。
源頼朝が成し遂げたような「流人から征夷大将軍へ」という、華々しいイベントはもう起こらない。
だけどそれらの殺戮イベントが、新しい時代につながるきっかけになってさらにそこから色々あって、現代の我々の時代の「この感じ」に落ち着いてるという。その不思議こそが、歴史のおもしろさ、ですよね。
今回の『鎌倉殿の13人紀行』は、ここでした。
永福寺跡