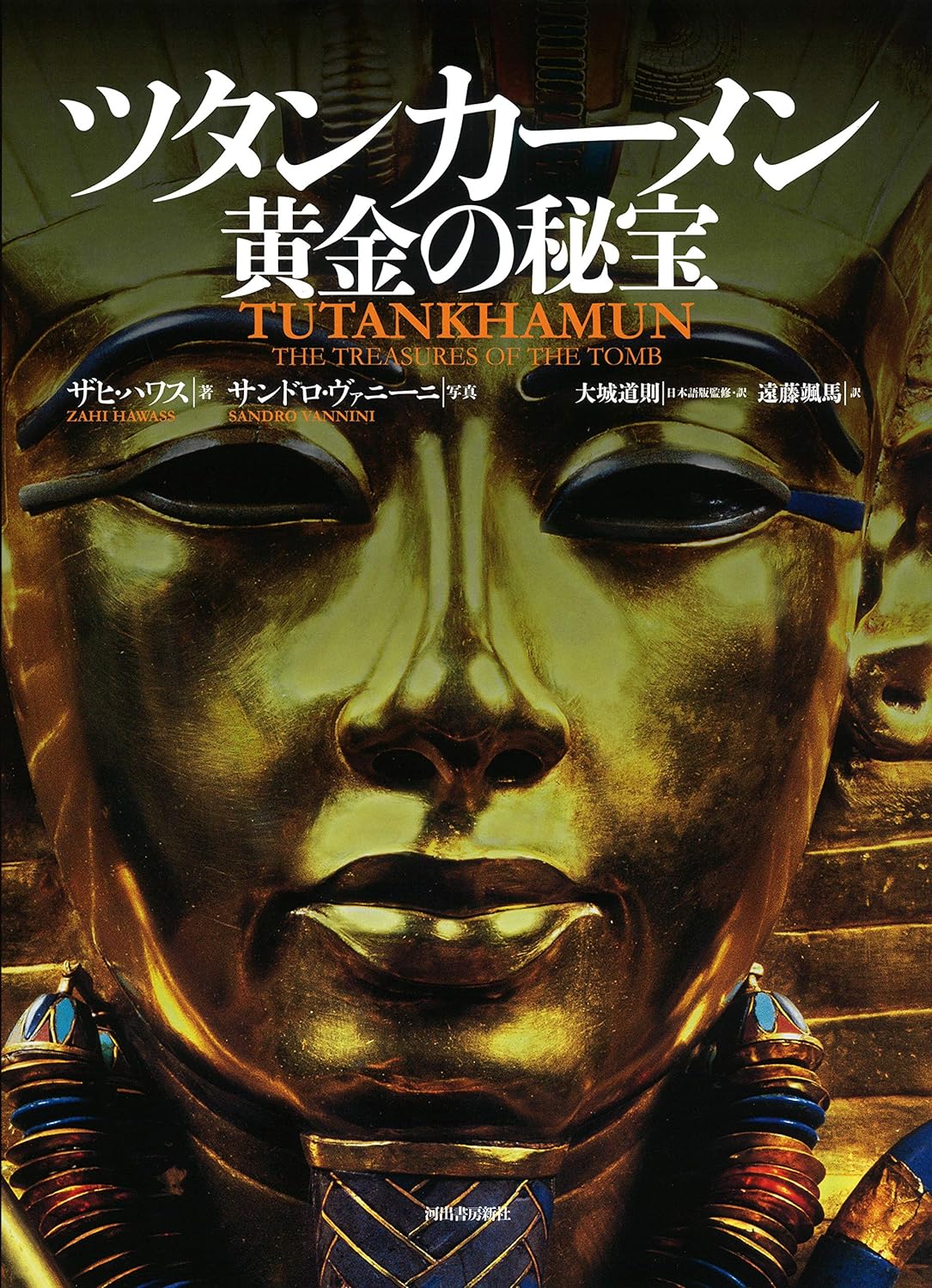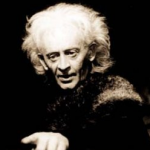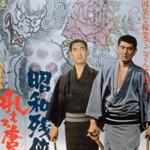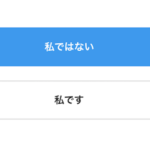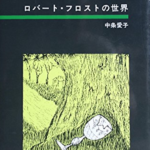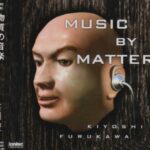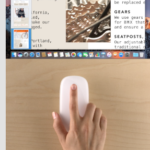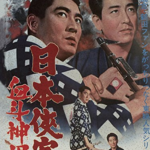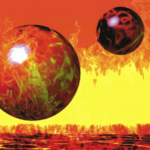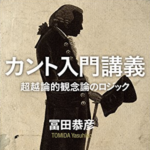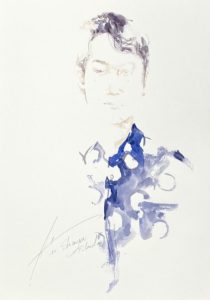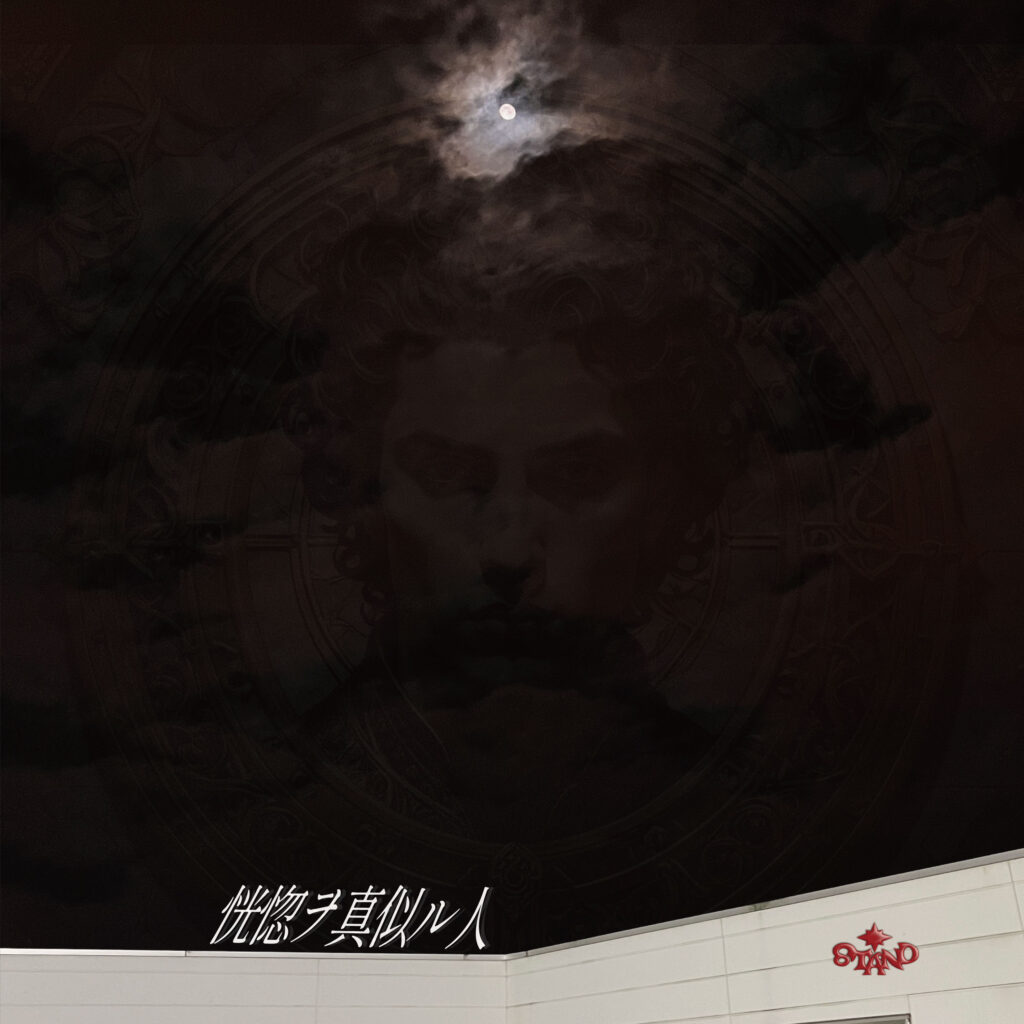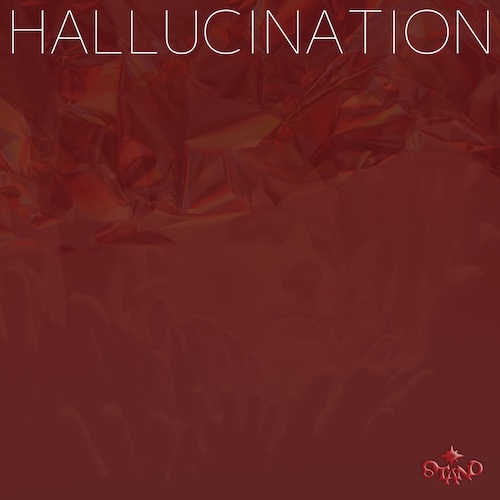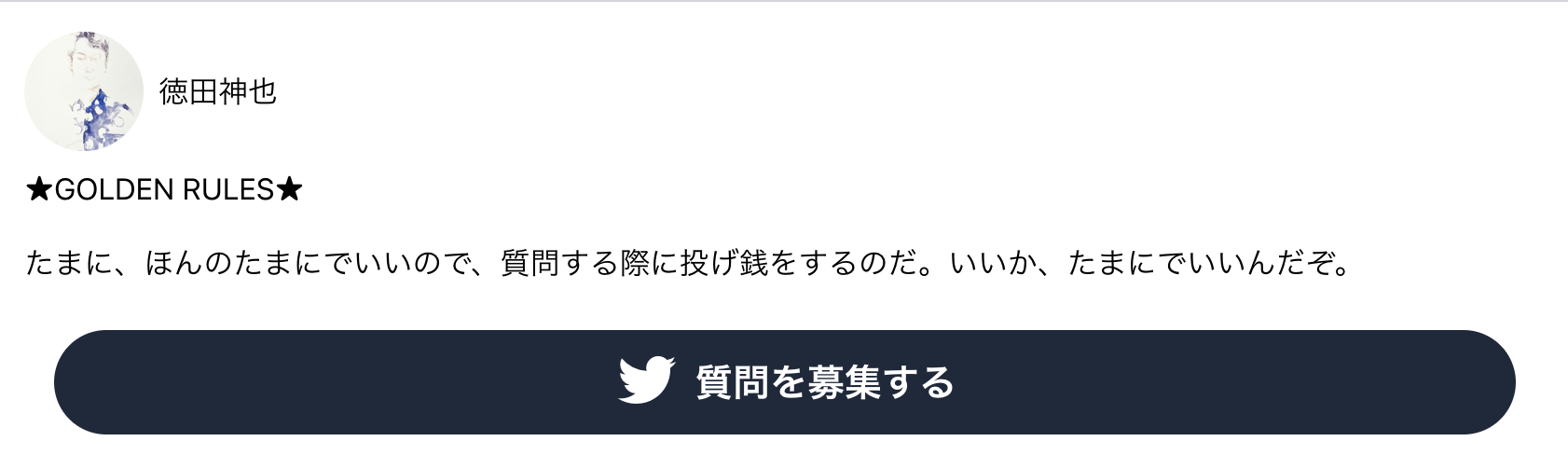こないだ古代エジプトのことについて扱った特番を観た。
~古代エジプト世紀の大発見プロジェクト~ツタンカーメンと伝説の王妃 3300年の新事実
あのツタンカーメンの黄金のマスクは、ツタンカーメン王の為に作られたのではない!という衝撃的な論文を元に、構成されていた。
面白かった。
「王家の谷」を発掘し続けるイギリス始め、ヨーロッパ人のその執念。
その内容と古代の王家の確執を、全員日本人俳優が演じるという再現ドラマがあった。
それがメイン、と言ってもいいくらい。
ドラマ出演:
夏菜(ネフェルティティ役)
鈴木 福(ツタンカーメン役)
今野浩喜(アクナートン役)
宍戸 開(アイ役)
やっぱり舞台は古代エジプトなので、その背景とか習俗とか、完璧に再現することは最初から土台、不可能だ。
そんなことは最初からわかってる、だからこそのフィクションとして楽しまないと。
で、割と酷評されてたりした。
まぁまぁ、いいじゃないの、と思うが。
例えばエジプトのテレビ局で、エジプト人が、古代の日本に興味を持って、エジプト人のあの濃いぃい相貌をもって
「わらわは卑弥呼なるぞ」
とか
「厩戸(うまやど)の皇子(みこ)のオナーリー」
とかやってる、というのを想像してみれば、微笑ましくも好演しているな、と思えてくるではないか。
想像力で埋めて楽しもう。

我々はすぐ、
ツタンカーメンと聞くと
「ツタン・カーメン」みたいに読んでしまう。
でも、なにせ古代のエジプトの言葉。
正確には、たぶん発音できないと考えるのが普通なんじゃないだろうか。
アルファベット表記は
Tutankhamen
トゥトアンクアメン、という感じ。
これは
Tut-ankh-amenと切るのが正確。
ということは
トゥト・アンク・アメン
が正しい。
ずいぶん印象が変わる。
これは、
「アメンに似た姿」というような意味だそうで、「アメン」とは「ラー」、エジプトの太陽神を指す。
しかし、「ツタンカーメン」が骨身にまで染み込んでしまっているわれわれ日本人は、もう彼をトゥトアンクアメンとは呼べない。
あのロシアの街・「ウラジオストック」も、われわれはすぐに「ウラジオ・ストック」と呼んでしまう。
なんだか食堂の厨房の奥に、調味料の買い置きがあるかのような。
「裏塩・ストックある?」みたいな。
でも本当は、Владивосто́к
ヴラディ・ヴァストーク。
ヴラディは「支配する」、ヴァストークは「東」なんだそうだ。
勝手にカタカナで構成を考えて、勝手に節で区切って読んでしまうのは、日本人の音感なのだろうか。
昔から「弁慶読み(ぎなた読み)」というのが得意だということと、関係あるかも…。