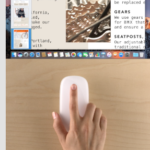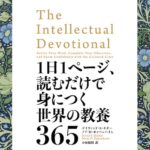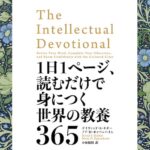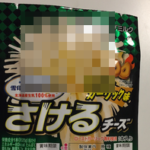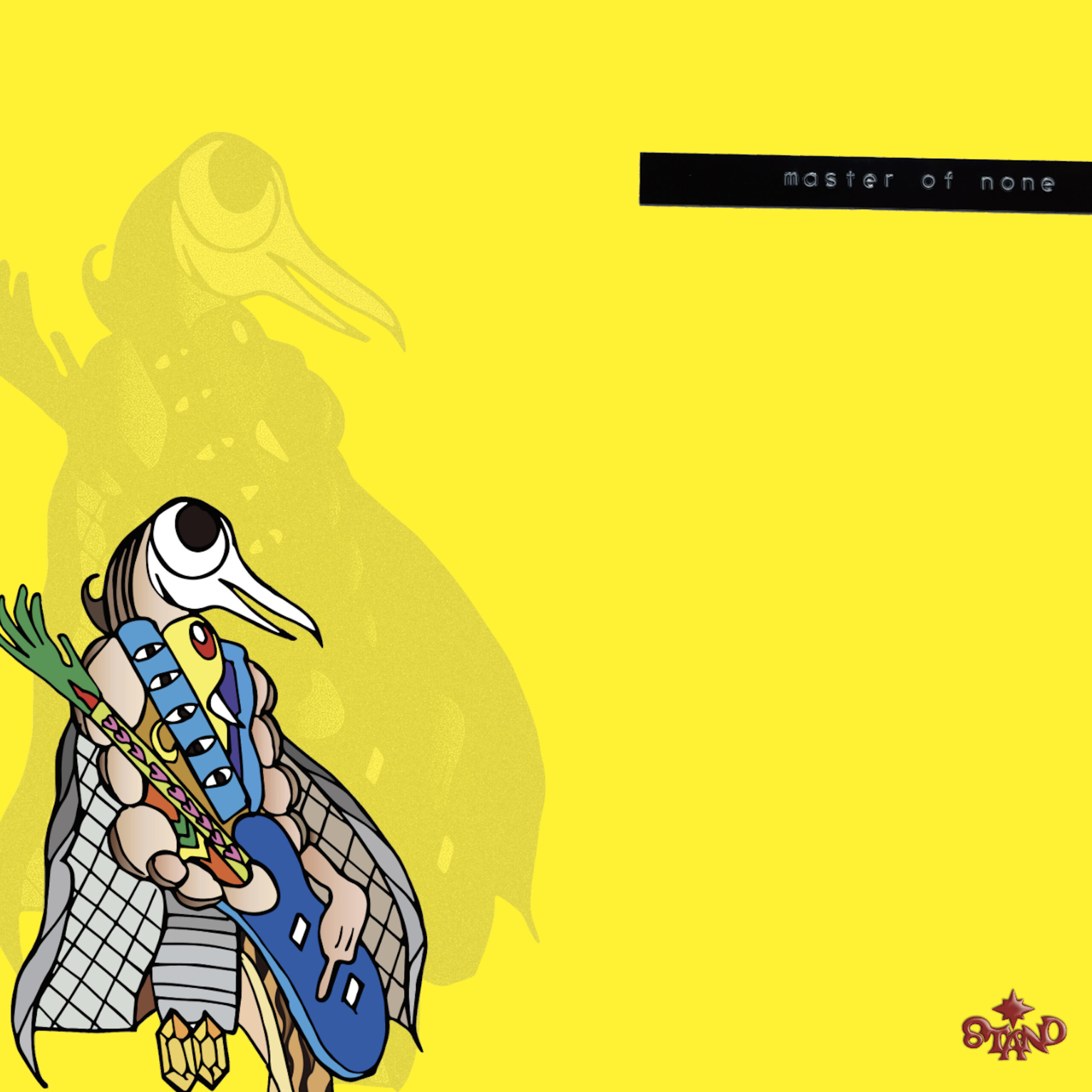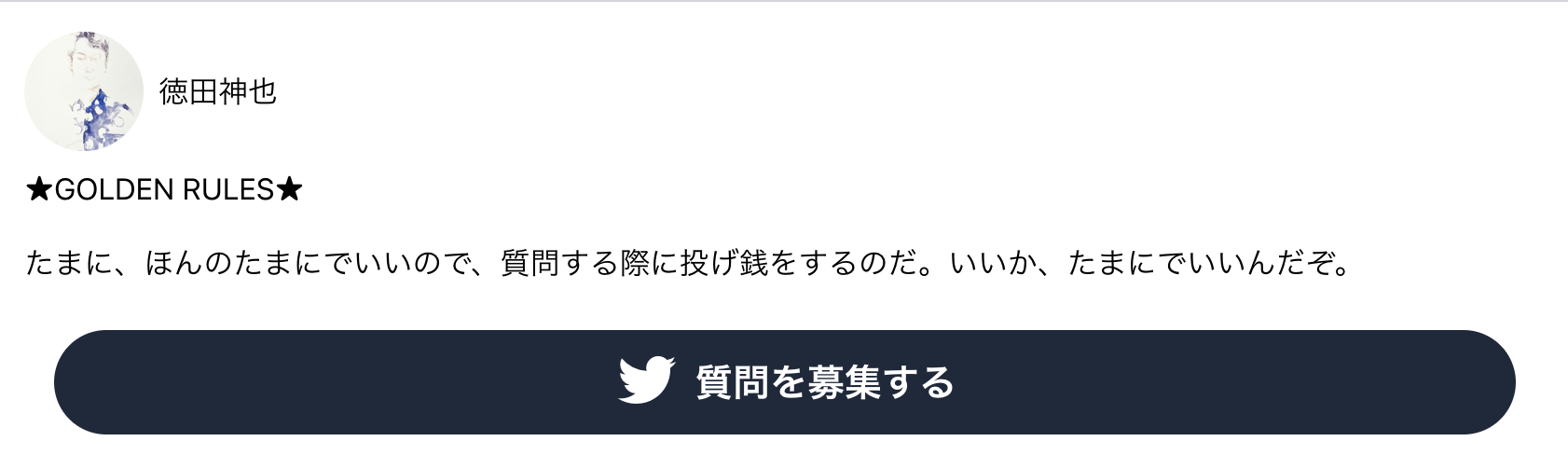影が薄い兄(弟)。
そりゃ、源頼朝(みなもとのよりとも)と比べてしまってはかわいそうである。
かたや鎌倉殿。
河内源氏の嫡流にして征夷大将軍、そして正二位にまで昇り詰める兄。
そりゃ、源義経(みなもとのよしつね)と比べてしまってはかわいそうである。
かたや戦の天才。華やかな勲(いさおし)と、語り継がれる悲劇の主人公。「判官贔屓」は常套句にまでなっている。
兄であり弟である彼は、両方から放たれる光で、まるで影の中を生きてきたような印象がある。
物語の主人公として描かれることも、まずない。
上掲の小説はそんな中とても珍しい。
しかしてその内容は、やはり「天下を狙う恐ろしい兄と、光り輝く眩しい弟の物語を横で見ているテラー」という形を取っている。なにせ本人の軌跡としてはあまりにも、史料がないからだ。
かわいそうにすら思える男。
厳しい“身分”の世界
源範頼(みなもとののりより)は、母が遊女であったがため(町人の娘だった説もあるが)、源頼朝からは一段も二段も低く扱われる存在だった。
この時代、そういうものだった。
源頼朝の母は歴とした貴族の娘であり、だからこそ兄2人を差し置いて、源氏の嫡男となった。
自分の出自が「母の身分による」のだから、「そんなものは関係ない!」とか「実力によるのじゃ」などとは決して言わないし考えもしない。
源頼朝は自分の母より身分の低い人間から生まれた弟を、露骨に差別していた。
そんなものなのだろう。現代では正確に理解することが不可能な価値観だ。
とは言え腹違いの弟たちも源氏一族には違いないから、作戦や計画を進める上ではアイコンとして利用することにした。
でももしかしたら、ある程度まで進めたら源義経も源範頼も、殺すつもりだったのかもしれない、最初から。
源範頼は藤原範季(ふじわらののりすえ)に養育された。前述の通り源頼朝の母は藤原季範(ふじわらのすえのり)の娘だ。
名前が似すぎていてややこしい。
源頼朝は単身、伊豆に流されたが、源範頼も殺されず、立派な貴族に預けられていた。
しかも養父・藤原範季は後白河法皇(ごしらかわほうおう)の近臣でありながら院に反発する九条兼実(くじょうかねざね)の家司でもあり、晩年になっても出家しなかった変わり者だ。よほど能力が高かったのか、それなのに憎まれないキャラクターの持ち主だったのか、おそらく源範頼は、母の出自の賎しさゆえに大した敵視もされておらず、(復讐するかもしれないという)将来性も見込まれておらず、まぁ藤原範季のところならよかろう、と平清盛(たいらのきよもり)はスルーしていた。
後に、その藤原範季の外孫が順徳天皇(じゅんとくてんのう)となり、討幕を目論んで承久の乱を起こすのだから皮肉である。
割と破天荒な人だったのだろうと推察される藤原範季に養育された源範頼は、「やはりここは合流しとかないと危うい」という計算のもと、遠江国から源頼朝の陣に馳せ参じる。
個別に「我こそは源氏の本流なり」と勝手に挙兵しなかったのは賢明だ。
源頼朝が伊豆で挙兵した後、五男である源希義(みなもとのまれよし)は、流されていた土佐で挙兵し、呆気なく鎮圧され殺された。
おそらく源範頼が浜松あたりで小規模な挙兵をしていたら、平家軍によってひねり潰されていただろう。
うまく合流した源範頼は、源義経とともに鎌倉源氏軍団の将軍として歴戦することになる。
源義経との落差
源平合戦において有名で、目立つのは源義経の大活躍だ。
しかしそれは源義経が別働隊として奇抜極まりない戦術を取ったからで(そうは言ってもほとんどが創作だが)あり、それが出来たのは本隊として、源範頼が真正面から進軍していたから出来たことである。
つまり本隊が囮になって、源義経の奇襲の意味を強くしたということだ。
北条ヨシトキ、千葉常胤(ちばつねたね)、三浦義澄(みうらよしずみ)・八田知家(はったともいえ)、小山朝光(おやまともみつ)、比企能員(ひきよしかず)、和田義盛(わだよしもり)、天野遠景(あまのとおかげ)など、鎌倉幕府草創の志士となる勇猛・歴戦の坂東武士団を引き連れて源範頼は総大将として、九州を平定する。中国地方を経て九州に至る、この陸路を堂々と源範頼が進軍していたからこそ、平家勢は瀬戸内海にいるしかなかったのであり、大部隊の兵站に相当苦しんでいたとは言え源範頼の行動は正しく、まっとうで価値のあるものだ。
それは源頼朝の命(企図)を、しっかり守っているという意味でもある。
総大将である源範頼の考えの通りに作戦を進めれば、つまり源義経のやり方を許さず進めていれば、壇ノ浦で平家が滅ぼすことは出来なかったかも知れないが同時に、安徳帝が死ぬことはなかったし、三種の神器・天叢雲剣が海底深く失われることもなかったのかも知れない。
平家をそこで皆殺しのように全滅させることなど、源頼朝は望んでいなかったと言われている。
彼の、謎の終わり
源範頼は1193年に失脚する。
源頼朝が征夷大将軍になった次の年だ。
すでに源義経は数年前に殺されている。
平家追討のために、ともに西国を走り回った弟は、無惨にも敵として死んだ。
奥州征伐にも参加した。
次は自分だ…と源範頼が思っても、無理はない。
他のどんな御家人にもない気苦労と恐怖が、彼にはあっただろうと推察される。
彼は源頼朝に対し、起請文を書く。
忠誠を誓い叛意など抱くはずもない、という内容のものだ。
しかしその起請文に「源範頼」と自署してあった。
これを、源頼朝は咎めたという。
源姓を名乗ることが僭越だ、というのだ。
よくわからないが「源を堂々と名乗って良いのは私(源頼朝)のみ」という意味だろう。
現在、我々は「源頼朝」と普通に呼ぶし、それは源義経もそうだ。
源範頼も同じように呼んでいるが、例えば木曽義仲(きそよしなか)や武田信義(たけだのぶよし)、安田義定(やすだよしさだ)などもみな、「氏」は源である。
彼らを源義仲・源信義・源義定とは呼ばない。便宜上呼ばない。
もし木曽義仲が天下を獲って幕府を作っていたら「源義仲」と呼んでいるだろうし、源平の戦いの中でもし源頼朝が死んでいたら「伊豆頼朝」とか「鎌倉頼朝」とか「相模頼朝」などと、教科書には載っていたことだろう。
当時、本拠とする地名を名乗るのが通例であり、本流である「氏長者」だけが「源」を名乗って良い、というマナーがあったということか。
源義経や源範頼らのことは死後、便宜上・歴史学上、そう呼んでいるだけであって、「源範頼」と書いただけで源頼朝が激怒するくらいだから、決してそうは呼ばれていなかったということになる。「調子に乗るな」と激怒されることなのだ。
やっぱりなんだかかわいそうな人
彼は「源範頼」などと自署せず、「蒲冠者」とでも書いておけば良かったのだ。
いや、それでも源頼朝は何らかのイチャモンをつけたのだろう。
何となくそんな理由では「弱い」ので後世、『吾妻鏡』において「富士の巻狩り」の一件が創出されたと思われる。
幕府は、世代交代の時期を迎えていた。
源頼朝は二代目への世襲を実務的に進めようとしていた。
そして三代目のための体制づくり(つまり嫁問題)を睨み、それ以降の源氏将軍、永遠の安定を目論んでいた。
幕府体制はある程度整い、源氏の血を引く兄弟は「跡目争いの元凶」にしかならなくなっていた。
天皇家も藤原一族も、跡目相続で必ず揉める。
何なら源平抗争の原因である「保元・平治の乱」も天皇家の後継者争いから始まっている。
将軍である自分は良くても、息子・源頼家(みなもとよりいえ)が将軍になろうとする時またはなった時、別勢力が政権転覆・奪取を狙い、源範頼を神輿として担ぎ出してくることは目に見えている。
その勢力と闘い競り勝ち保持し、疲弊し苦労するよりは、今、その候補である源範頼を殺しておいた方がよほど安泰には近い。
源頼朝は、そう考える人だ。
伊豆へ流した(そしておそらく殺した)。
「一族兄弟手を取り合って」というような繁栄のイメージは、河内源氏には存在しない。