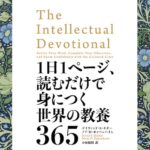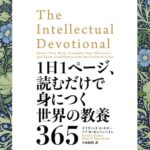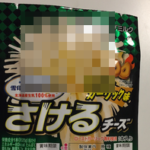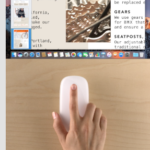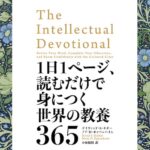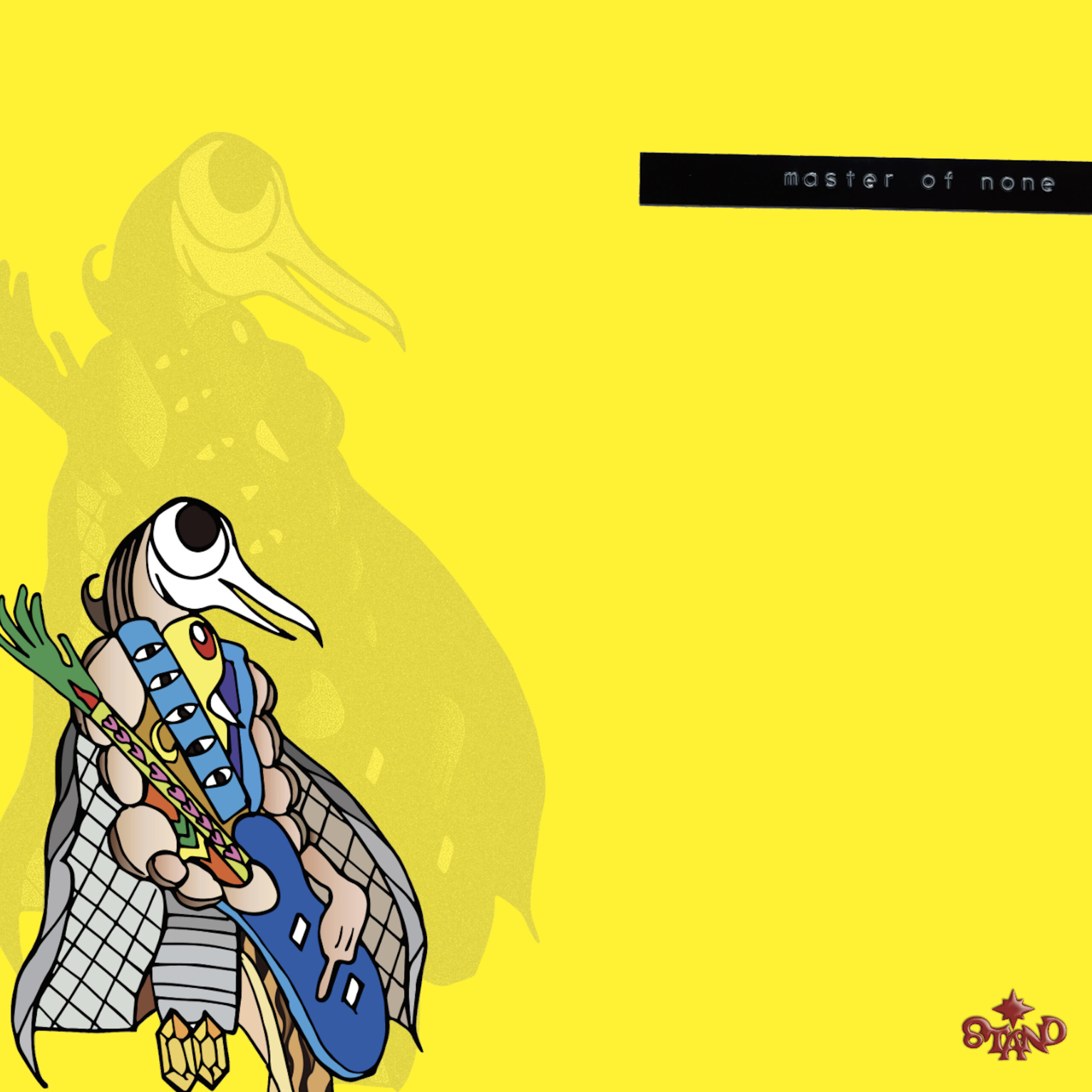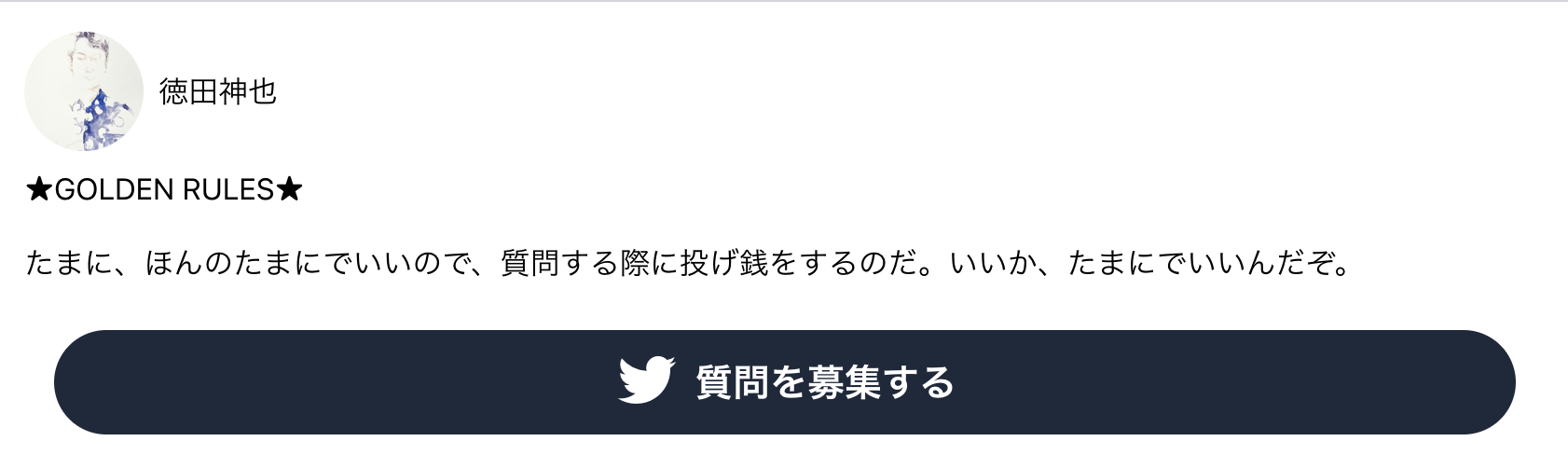あるところで2024年の大晦日の昼間、話をした。
それは曖昧な依頼で、ちょっと神様周りの話を聞きたい、というものだった。
専門家でも宗教者でもない私から一体なにを聞こうというのか。
やたら期待してもらっては困るが、知ってることを語るだけなら、と了承した。
妙な空気の中、私は話し始めた。
以下は、録画から話した内容の要素を取り出し、書き直したものである。
勘違いや間違い・考え違いも含まれる可能性が多分にある。
さらに変わり果てた仏教
1868(慶応4)年から、日本の新政府は12の法令を布告した。
それらはまとめて「神仏分離令」と呼ばれる。
俗に「廃仏令」などと言われることもあるが、名前だけ見ればそれがおおまかにどのようなものだったかは想像できる。
政府は仏教そのものを禁止などしていないのだが、全国の多くお寺ではその効果が出過ぎて、仏像が燃やされ、多くの寺院が壊される事態に至った。
南都・興福寺の五重塔すらも、焼かれる寸前だった。
今なら国宝になりかねないクラスの多くの木像も、ただの燃料として使われた。
なんとか生き残った国宝「阿修羅像」の腕が折れているのは、そういうことの名残りなのかも知れない。
禁忌とされていたはずの肉食妻帯が何となく日本の僧侶に許される空気感が出来たのも、この頃である。
「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」の太政官布告で、僧侶らは雪崩を打った。
表向きにはタブーだった肉食妻帯がオープンに許され、当たり前のようになっている現状について語るのは、仏教界においてタブーになっているらしい。
随分とタブーも、日本式に変容したものだ。
現在の仏教界に、肉食妻帯を当然としていることを弁明する語彙は無い、ということでもある。
なんら、宗教的正当性があって十戒を破っているわけでもなく、ただ「時代の移り変わりの中で…」「当時の政府がそう言ったんだし…」などとお坊さんたちは、モゴモゴ言うしかないのである。
もちろん、浄土真宗では最初から禁じられていない。
日本の宗教のかたちたち
仏教が渡来してから、日本にもともとあった神々は、仏教の中に取り込まれた。
神仏は見事に習合し、本地垂迹(ほんじすいじゃく)が当たり前の考え方となった。
日本古来の神は、実は仏教の神が化身となって現れたというのである。
「権現」というのがそれだ。
「権」という字には「仮に」という意味がある。
江戸時代まで、大きな神社に従事する僧は「社僧」と呼ばれ、神前で読経した。
神宮寺という形式もあり、神道と仏教は見事に混淆していた。
仏教は政治力の強さで信者を極楽へと誘導した。
貴族は浄土を願い、民衆も往生の方法として、念仏を唱えた。
一方、鎮守は土地を守ったし、支配層は古来の神々を、天皇をその頂点として崇めた。
明治、日本という国家を欧米列強並みにするという至上命題のもと、ヨーロッパで学んできた志士たちはキリスト教の世界観っぽさを出すために仏教より、神道を選択する。
天皇を中心として国力を糾合する為に、その系譜につながる神話を持つ神道にこそ、国家の求心力は求められた。
江戸時代後期には「神道講釈」というものが庶民の間では大流行し、国学の勃興と共に「もともと日本は神の国」だと主張し、仏教に部分的に反発する人たちが一定数いたという。
庶民の生活に、お寺はすごく密着していたのはよく知られてるところだ。
戸籍を管理する役割を幕府は考案し、檀那寺として地域に浸透させた。
人別帳(にんべつちょう)に書かれた戸籍こそが真っ当な民であることを証明だったし、それに従うしかなかった。
「人別」のないものは「無宿者」と呼ばれ、生活における保障を受けることが出来なかった。
つまり幕府政治の弱体化は、仏教を瓦解させる下地になっていたと考えることも出来る。
すんなり廃仏毀釈が進んだのは、政治的・制度的な仏教による支配にも、限界が来ていたからだと考えられるのである。
キリスト教などに親しんでる海外の人から見ると、神道は「不思議すぎる」らしい。
本殿や拝殿はあるが、教義もなければ経典もない。神像も本尊もない。
宗教画としての神影は描かれたりするが、日本人はそれが、神の確定的な姿であるとは誰も思っていない。
それが語られ始めたのであろう時代の、特権階級の人々の似姿だとしか認識していない。
日本にしかいない神なので、「シルクロードのこの地域の様式では」などの比較対象もない。
美術としても成立していないのである。
神道は、日本人が持っている「礼節」や「規範」「道徳」などが作法となって結実している、ようなものかも知れない。
日本の宗教は「アニミズム」という言葉で説明されることが多い。
語源であるアニマは、生命を指す。
あらゆる自然物に生命や霊的な存在を認め、人間はその中で生きているからこそ、自然そのものを崇拝する。
畏れと恐れ、それは表裏一体であり、その思想を「様式にしなかった」という意味では、神道はやはり根源的には宗教ではないのかも知れない。
キリスト教の世界宗教化、そして古代エジプト
古代ローマ帝国はギリシャ文明から受け継がれ発展し、驚くほどの多神教だったが、支配地域だったユダヤ地域で生まれたキリスト教が、帝国の後半には国教となった。
磔刑に処したのはローマから派遣された総督ピラトだ。
支配する側だったはずの帝国は東へ東へ勢力を伸ばし、事実上分裂し、コンスタンティヌス一世の時代、正式にキリスト教が国教となった。
そして帝国は滅亡する。
アニミズムに即した肥沃で芳醇な、古代から続く素朴な宗教感覚は、峻厳で清貧を尊ぶ新宗教に、塗り替えられてしまったのだ。
一般に、キリスト教がヨーロッパを始めて支配し始めた頃からを「中世」と呼ぶ。
中世は「暗黒時代」と言われる。
人間の肉体などは神に造られた塵芥でしかなく、大切にする価値はない。
清潔さをも必要としてはならないという考えのもと、あのテルマエが盛んだったローマでも、「風呂は禁止」とされた。
豪華な神殿や精緻な神像は破壊され、その上に教会が建てられた。
古代エジプトも多神教だったが、ある時、唯一神アテンを崇める強権的な政策が採られることになった時期がある。
エジプトのファラオ・アメンホテプ四世は、アメン神の信仰が強く多神教的な崇拝をしていた社会を、太陽神・アテン神だけを祀るための状態に変革した(アマルナ宗教改革)。
そのために遷都までした。
自分の名前も「アクエンアテン(アテン神に有益な者)」に変えてしまった。
他の神々を祀る神殿や神像は破壊され、「神々(ネチェルゥ)」という複数形すら使用を禁じた。
現在では「異端の王」とも呼ばれるアクエンアテンは、オシリス信仰すら認めなかった。
来世への再生を信じミイラづくりなどにも強い影響を与える冥界の神・オシリスを否定したがゆえに、結果的に一神教的なアテン信仰は、国民的で長期的な信頼を集めることは出来なかった。
当時のエジプトの人々にとっては、死後の世界や来世への転生を司るオシリスがいないと、人生そのものの意味を感じられなかったのだろう。
「ツタンカーメン」という名前は「トゥト・アンク・アメン」が本来的の発音に近い。
これは「アメン神の生命の似姿」という意味だそうだが、彼の元々の名前は「トゥト・アンク・アテン」である。
アテン神の一神教化を推し進めた父である異端の王・アクエンアテンは、自分の息子に当然ながら「アテン神の姿をしている」というような意味の名前をつけて神格化させた。
日本風に言えば「ツタンカーテン」だ。
アテン神は日輪の象徴とされており、いわゆる神像というものがない。
偶像がない分、名付けることで息子である「トゥト・アンク・アテン」への忠誠も同時に強めることができる、という狙いがあったのかもしれない。
やがてアテン信仰への国教化は失敗し、エジプトは、アメンをはじめとする多神信仰に戻る。
少年王は自らの名を「トゥト・アンク・アテン」から「トゥト・アンク・アメン」にし、様々な神事も復活させた。
セム系一神教の原型は実はここにあり、ユダヤ民族もこの古代エジプトのアテン信仰の形式を一部採用したのではないかとも言われている。
「セム系」と呼ばれる神は、みんな同じだ。
ヤハウェという神を信じている。
ユダヤ教徒であったイエス・キリストは、その中で異端となって処刑された。
キリスト教にとって、「最後の預言者」はイエスであり神ではない。
イスラム教にとっての「最後の預言者」はマホメットである。マホメットも神ではない。
イスラム教もイエスを預言者として認めてはいるが、「数ある預言者のうちの一人に過ぎない」という扱いである。
「厳格な神」のイメージとは
セム系の神には、砂漠の地ならではの厳しさがある。
宗教誕生の時期には今ほど荒涼とした土地ではなかったと思われるが、やはり日本とは風土そのものが違う。
宗教が生まれるにはやはり、その地域性が重要だ。
日本には山があり谷があり、流れの早い川があり海がある。
気候は湿潤であり、動植物が肥沃に育ち、季節によって寒暖差があり、景勝がある。
砂漠に手の届く広大で果てしない荒涼とした大地と、急峻な山から水が流れ続ける湿った狭い島国とで、同じような神が生み出されるわけがない。
セム系の神はやはり、厳しい環境で生き抜くための知恵を「限定した民に教えてくれる」ために降臨した、厳格な性格を有している。
キリスト教徒は教会で、イエスキリストの像に祈りを捧げているように見える。
イエス・キリストが処刑されたのは人間が持つ原罪を一身に背負い、あえて死を選んだからであり、それは自らが「復活」することを予見していたからだ。
そしてキリスト教の信仰は、この「復活」を信じるところから始まる。
なのでそれを象徴する一番強烈なイメージを持つ「磔の刑」をモチーフにしたデザインを、祈りの対象に掲げているのだろう。
もともと十字架での磔刑は、ローマ帝国における、政治犯の処刑方法である。
イエスが磔の刑に処されている姿はかなり残虐な場面だし、グロテスクだ。
しかしその残酷さが、「このあと復活する」というイメージに最速で直結する最良のモチーフなのだ。
深く長く考える必要がない。
圧倒的に強烈なシーンを偶像化することで、信者は自分の中に、忘れ得ぬ「復活」への信仰の出発点を刻み続けることが出来る。
「偶像崇拝」の意味
キリスト教はのちに変化してしまったが、本来イスラム教やユダヤ教と同様、「偶像崇拝の禁止」が守られる。
仏像や神像を祈祷の対象にするのではなく、信者は自分の心で、直接神に祈る。
仏像や木や石で出来ており、木や石は神ではないので、それを信仰の対象とすることは許されないのだ。
神の存在は、たとえば自分の頭の後ろに神がいると思えばそれこそが神であり、必ずしも目の前にいる考える必要すらない。
仏像や神像は、たとえば本殿の奥に鎮座しており、木や石や金属でできた「それそのもの」を感じる場所でないと、ありがたみを感じることが出来ない。
しかしその存在感とは、「木や石や金属、並びにその彫刻」が放つ存在感であり、神とは全く無関係なはずなのだ。
しかしいつしか木そのもの、石そのもの、金属そのものを、神仏そのものだと勘違いし始める。
物質に依存してしまうのだ。
そしてその物体を守り、物質を追い求める。
それを追っている間、神のことを忘れてしまうのだ。
だから偶像崇拝は禁じられた。
「そこにいる」と自分が思えば神はそこにいるのであり、そう思えれば、何より神に親近感がわく。
必ずしも物体に神はいないではなく、依存する心をこそ諌めていると言えるだろう。
現在イエス像やマリア像を信仰の、祈祷の対象として掲げるキリスト教は、厳格さを備えながらも世界宗教となっていく過程では、各地の様々な宗教と習合していった。
埋葬の仕方に、世界観が顕れる
ユダヤ教徒やキリスト教徒、そしてイスラム教徒は、「最後の審判」を待っている。
世界が終わると、神がすべての人間(というか教徒の)生前を審理し、ヘヴン行きかヘル行きかを決めるのである。
それまでにまず「世界は終わる」。
世界はそこに向かって進んでいるのであり、西暦が単なる数字の積み上げに過ぎないのはそういうことだ。
世界は脇目もふらず一直線に「終わり」に向かっているという感覚なのだ。
現実的にそれを心から信じている人がどれくらいいるかはわからないが、天使が「最後のラッパ」を吹き鳴らす時、信者は天国へ行くべく、蘇る。
その時のために、土葬にしないといけないのだ。
現在に至るも土葬がなぜ「遺体がそのまま残る」という根拠になるのかは謎だ(分解されて無くなってしまう)。
おそらくかつては火葬のように分解が可視化されない分、「最後の審判のための保存」に見えたということだろう。
日本の仏教のように、死んで49日間を過ぎたら「成仏する」という世界観とは違う。
いつか(本人が最高の状態だと信じる姿で)蘇る、と信じているからこそ墓を破って這い出てくる「ゾンビ」が成立する。
「いつか墓場から蘇る、があり得る」とどこかで思っていないと、火葬では、どうもゾンビに説得力がなくなってしまう。
「神様はいるか」と聞かれたら?
二足歩行に達した人類は、脳が大きくなり、進化の結果、右脳と左脳が脳幹でつながったことで現実と抽象が混ざり合ったことを考えられるようになった。
目の前の事象を追うだけだった動物同然の状態から、「ここにないものを想像し、そのための道具を作り出す」ことができるようになったのだ。
想像の産物を、「ある」と言い切れる精神状態が生まれた。
全知全能の神の存在は人間には確認のしようがないし、実存としては「いない」と言わざるを得ない。
しかし世界にこれだけ多くの人々が「いる」というなら、「いるとする」しかない。
その意味で、神は、いる。
神がいると信じる人たちの慈悲深い行動によって、様々な恩恵が生まれる。
その恩恵を受けた人にとって、恩恵が生まれた理由は「神」だ。
その意味で、神は、いる。
誰も「愛」の実体など見たことはないが、愛はあるかと言われたら今日持ち合わせているかどうかは別にして、「ある」と答えるしかない。
愛があると自負する人たちの「愛ある」行動によって、優しさが生まれる。
その優しさを享受した人にとって、優しさが生まれた理由は「愛」だ。
その意味で、愛は、ある。
「神」は、「いる」としか答えようがないのである。
これを「科学的」だと呼ぶかどうかには、それぞれ異論もあるだろう。
無宗教は「無宗教」という名の宗教
無宗教な人たちも全世界にはたくさんいるし、無神論者だという言う人もいる。
しかしそれらの人たちは、宗教行事に積極的に参加しないことをもって「無宗教だ」と言っているに過ぎない場合があると思われる。人の心の中は、誰にも覗くことはできないからだ。
何かを畏れる気持ち、何かを信じる気持ち、誰かを敬う気持ち、人智の及ばぬ事象について思いを馳せる時…なんらかの敬虔な気持ちが生まれるのであれば、それは宗教と呼んで差し支えないように思う。
積極的にあらゆる神を冒涜し、あらゆる宗教行事を妨害し、あらゆる宗教施設を破壊し続けて、それこそが人間にとって幸せな、必要な行為だと説いている「無神論者」はいない。
たいていが「ただ単に宗教に対して極度に消極的なだけ」である。
多くの人が、自分にとって特定の宗教が必要かどうかを判断するよりも前に、幼い頃から「宗教由来の」イベントを人生経験として積み重ねているので、それに対する違和感や嫌悪感がない限り、やんわりと、あっさりとした宗教観が根付いているという現実性・地域性に囚われているはずで、それを一切合切取り払うには、それこそ特定の宗教に帰依するしかなくなるのではないか。
キリスト教から資本主義が
古代ローマ帝国は、清貧のを人民に強いたキリスト教のせいもあって崩壊した。
ところが、キリスト教世界から資本主義は生まれている。
キリスト教にも色々あって、宗教革命後、プロテスタントの中から資本主義につながる考え方が生み出された。
宗教改革がなかったら、カトリックだけがキリスト教を支配し続けていたら、21世紀になってもまだ世界に資本主義は生まれていなかったかも知れない。
ことほど左様に、キリスト教は世界の解釈をその時代によって変えてきた。
うまくアジャスト出来たからこそ、世界宗教として広く受け入れられているのだろう。
科学が「神の領域」にどこまで踏み込むのか…というような問題に関しても、どこからが「神の領域」なのかを決めるのは誰なのか…?
人間の尊厳に関わるところ(脳死や臓器移植)については、バチカンの解釈が毎度注目されたりする。
ローマ教皇庁は「聖年」にあたる2025年の公式マスコット「Luce(ルーチェ)」を発表した。
紀元2025年を経て、まさか偶像そのものと言えるゆるキャラをバチカンが認めるなど、マツダもびっくりだろう。
「死」について考えることこそが…
宗教の根幹は「死んだらどうなる?」から始まっていると言っていい。
死は怖い。
死にたくない。
死がただの死であった動物時代と違い、進化した人類は、それらを「問い」として捉えることになった。
死んだらどうなる?
死んだあと人間はどうなるのか。
死に対する不安と恐怖が「来世」や「生まれ変わり」を生み出したと想像することは容易だ。
今生きている自分は、来世に、転生する。
なので前世から今、転生して生きている。
これは一直線な世界観を持つセム系の宗教とは相容れない価値観のように見えるが、なんとなく「生まれ変わってどこかでまた生きる」ということは、全人類にとってしっくりくる想像のように思える。
重要なのは、「自分の死は、他人の死とは違う」というところだ。
戦争をはじめ、たくさんの死が、生活の中にはある。
それらの死は、自分の死ではない。
いくら何千何万の死がそこにあろうとも、自分の死はたった一つしかない。
普通は他人の死を見て自分の死を想像するものだから、死んだ後の人の姿を当てはめて、死後をイメージしてしまう。
しかし自分の死後、「自分の死について考えを巡らす余地がある」などというのは単なる妄想ではないか。
「他人の死について考えを巡らす余地が自分にはある」から、死後の自分について死後、自分も考える余地を妄想してしまっているのだ。
もし死後自分に、自分のことを考える余地などないとしたら。
死後のことを心配する理由がなくなる。
「あの後あれはどうなるんだろう」とか「残された人たちはどうなっていくんだろう」などを考える主体が存在しない。
意識が存在しないのだから、心配も恥ずかしさも未練も存在しない。
そう思えたら、そう完璧に考えることが出来るようになったら、死への恐怖は消える。
「自分などただのゴミと同じだ」と吐き捨てることはないと思うが、「他人の死と自分の死を混同しない」ことは、生きていく上でおそらく重大な思考実験・精神修養だと思う。
たまにワニの映像を見ることがある。
ワニは大きな口で、獲物をまるで「反応のみ」で捉えている。
飼育された池で、餌が投げられたことを感知した1匹のワニが、実際に餌がはるか遠くへ消え去っているにも関わらず、隣にいたワニの腕をそれと見定めて瞬時に食らいついた。
あっこれは同族の腕だ!などとも思わずそのワニは即座にデスロールを始め、食いちぎった。
改めて視認するわけでもなくそのまま腕を飲み込み、同じ場所に佇んだ。
食いちぎられた方のワニも逃げたりのたうち回ったりすることなく、ただ同じ場所に佇んでいた。
あれを見ると、愚鈍な爬虫類たちの下等な生態と吐き捨てることも出来なくはないのだが、ワニはただ、「ワニのプログラムで生きている」と言うことが出来る。
ワニにとってはそうなるように出来ているというだけで、ワニにとって、それが生きていく上での最適解だということに過ぎない。
ワニが選んだわけでもないし、なぜそうなっているかの理由もない。
決まった反応を示しているだけで、ただ人間が人間になぞらえて勝手に「無慈悲に食いちぎった」とか「仲間なのに」とか「ちゃんと見てない愚昧な動物」などと低い価値を与えてしまっているに過ぎない。
温度によって花が開き、温度によって実をつけ、温度によって枯れていく植物たちも同じだ。
それがそれぞれの植物にとって、生きていく上での最適解だというだけだ。
なぜそうなっているかの理由もない。
そんな地球上の生物の中、人間だけが「そういうシステムから外れている」わけがない。
人間も同じように、なぜか決まっている「人間のプログラムで生きている」。
人間は外部からの刺激で、感情が湧き上がるように出来ている。
その点はもしかしたらワニよりも植物よりも、ずいぶん複雑で厄介かも知れない。
感情は、人間の、外部認識能力で捉えた情報を得て自動的に生まれる。
そしてみんな、そうやって自動的に生まれた感情を「私が生んだものだ」と勘違いして、性格だったり個性だったりと、ぞんぶんに勘違いをしている。
ただの反応(あのワニが隣の腕に食いついたのと同じ)を「私だからこそ!」と自慢げに誇っているのである。
もしかすると「私がある」というような勘違いすることすら、決められたプログラムなのかも知れないが、おそらく人間が死んだら残るのはそのプログラムだけで、その主体だと盲信しているような「私」は残らない。
もし感情が単なる反応で、それに日々、翻弄されていることを苦しみだと感じるのであれば、それぞれの感情に名前をつけて、それが起ち上がりうねりのたうつ様を、言葉で描写してみるといいだろう。
おわりに
世界の理解は言葉によって進む。
神は言葉で世界を支配している。
地域と言葉と関係に縛られた我々の人生の物語は、神という第三者を置くことで、やっと冷静に語ることが出来るのかも知れない。