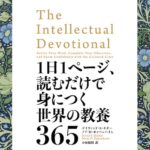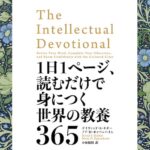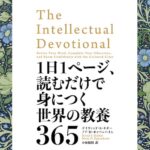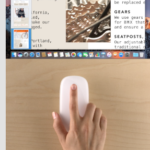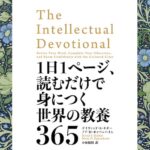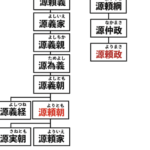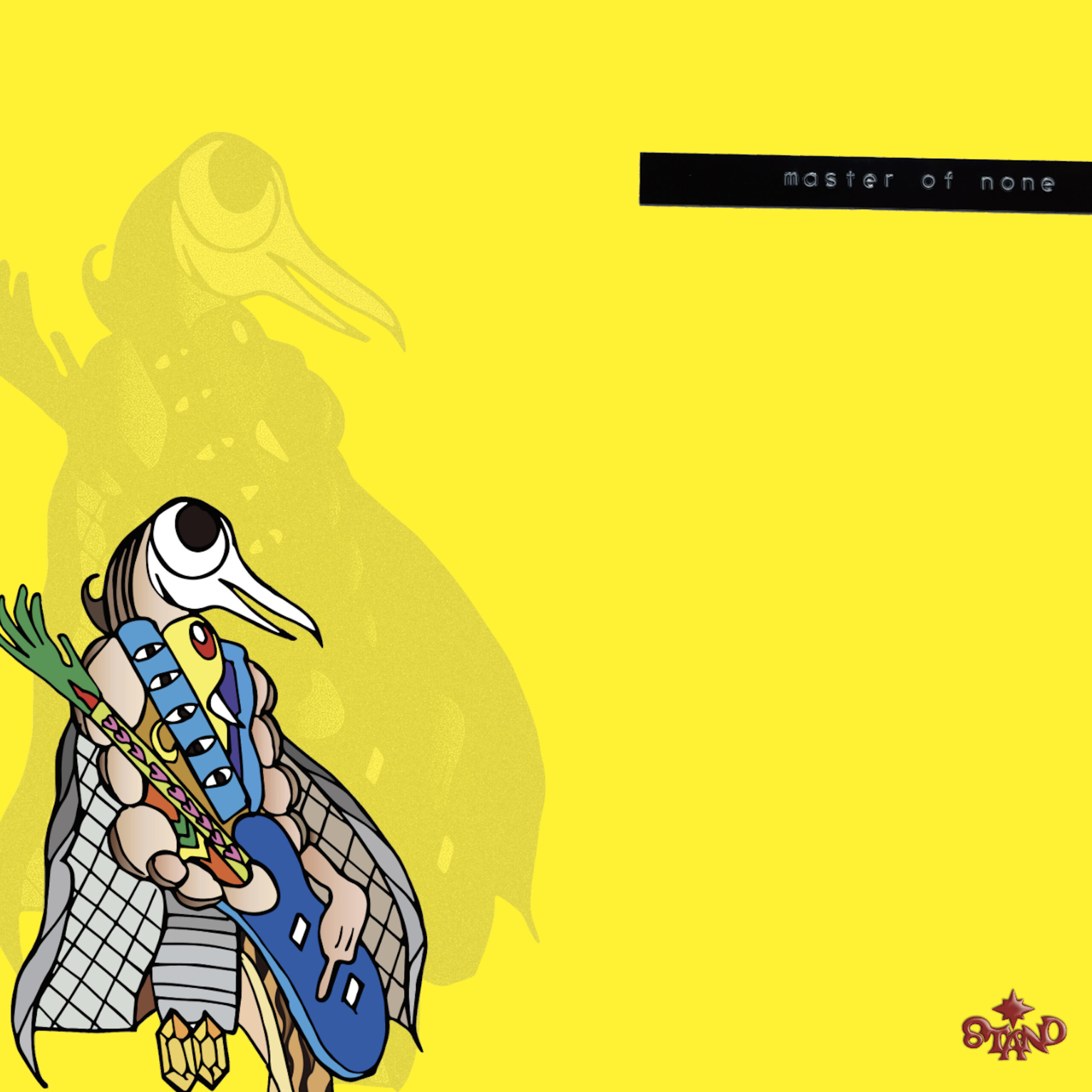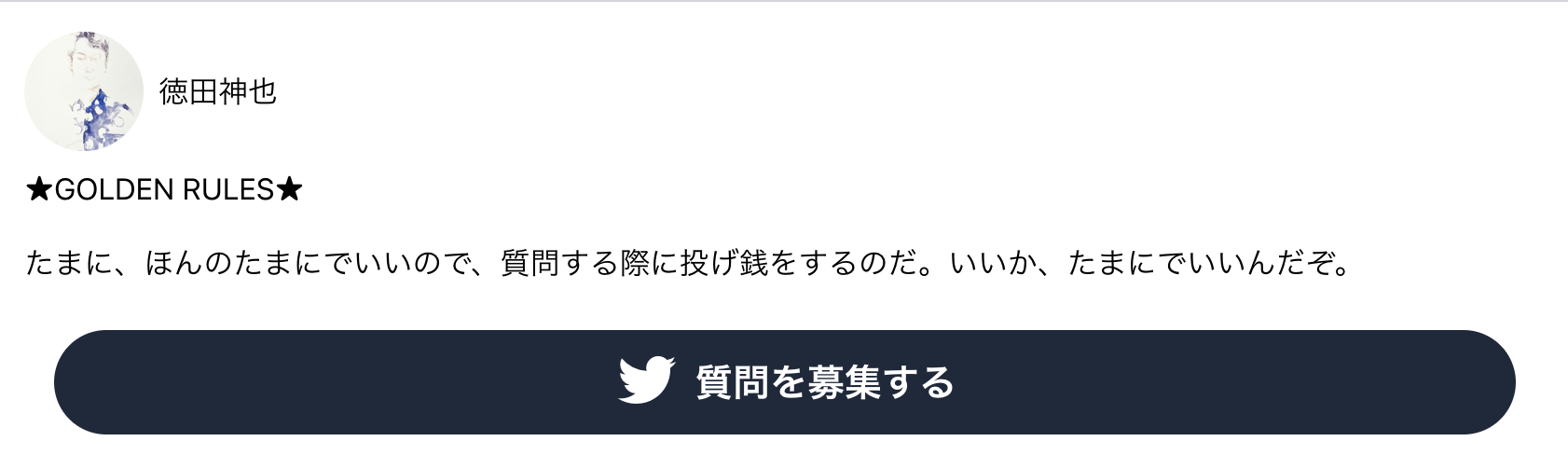男は、夢を見ていない。
または見ていたが、いっさい覚えていない。
話せと言われても、見ていないものは見ていない。
夢の内容など、適当にその場で捏造して話すこともできたはずだ。
しかしこの「適当に流す能力」や「相手の要求や気持ちに沿う能力」の欠如こそが話をこじれさせる原因だった、と言える
ついに「天狗裁(さば)き」にまで至ってしまう。
周りの「興味本位のわからず屋たち」が悪いのではない。
意固地に「本当」のみを突き通そうとする男の頑固さが、ことを大きくしてしまったのだ。
「どんな夢見たん??」
となにげなく、訪ねた妻。
「見てへん」と突っぱねる男。
確かに寝ながらニヤニヤしていたり難しい顔をしていたり…という、夫の寝姿についての客観的な事実を持っている妻は、「見ていない」と言い張る男に「言えない内容だから言わないんだろう!」と嫉妬し、嫌疑をかける。いっさい見ていないわけがない。なぜなら自分は、寝ながら表情すら変えていた夫の顔を、この目で見ているのだ。嘘をついてまで、なぜ夫は「見てない」と言い張るのか。それは「言えない内容の夢だから」ということになる。
殺す・殺さないの夫婦喧嘩に発展しては、壁の薄い長屋で暮らす隣の男も仲裁に入らざるを得ない。
喧嘩の仲裁人は「時の氏神」とすら呼ばれる。
カッとなって感情的に激昂する喧嘩というものは、逆に言えばきっかけがあれば冷静になれておさまってしまうということなのだろう。だから仲裁者は、たまたまいてくれただけでご利益がアラタカな「その時の」氏神なのだ。
仲裁者はまぁまぁと女性をなだめて、近所の井戸端へ送り出した。
その後、興味本位で同じ質問をする。
「女には言われへんやろうけど、どんな夢やったんや?」
と、秘密の共有のつもりで問う男。
だが「見てへん」と突っぱねられる。
またもや喧嘩である。
つまらない喧嘩は常に、個人が持つ最大級の価値観を賭しておこなわれる。
夫婦では「めおとの絆」を。
友人とは「長年の友情」を。
大家が仲裁に入って、また同じように興味本位な訊かれ方をして、言い合いになり、とうとう「出ていけ」「訴え出てやる」という公事沙汰(くじざた)になってしまう。
大家とは「生活基盤」を賭けた闘争になってしまうのだ。
彼らの住んでいる長屋というのは、大家の所有物だ。「家主(いえぬし)」ともいう。
現代の賃貸物件よりも店子と大家は密接に結びついていて、仲介業者もいない。
大家は生活全般を見守りながら治安を含め、その町をまとめる役目をも担っていた。公権力との橋渡し役でもある。町役とも呼ばれ、彼が一筆したためないと、江戸の男たちは勝手に丸坊主にもできないのである。
なので「大家に逆らう」は、まず一番身近な権力に逆らうことを意味する。
ここを追い出されらら「家主と揉めて追い出されたような男」のレッテルを貼られ、次に借りられる家があるかどうかもわからない。
それでも「夢は見ていない」と突っぱねるのだから、頑固すぎるだろうこの男。
なんなんだこいつ。
とうとう町奉行の前で詮議を受けることになる。
「アホか大家。町役ともあろう者がそんなことで立ち退けなどとは馬鹿馬鹿しすぎる」と奉行は大家の方を怒る。この時代、訴えが直々に町奉行の前で、いわゆる「お白洲」で裁かれることなど滅多になかったそうだが、民事不介入の原則もまた、江戸時代にはなかっただろう。

なにせ町奉行と言えば行政・司法を一手に引き受ける、絶大なる権力を掌握した存在である。一人で町長・市長・消防署長・警視総監などを兼任していると言ってもいい。しかも独断即決が許される身分差もある。だからこそ、こんなつまらない訴えを「つまらんことでお上の手をわずらわすでない!」と叱るためだけに「お白洲」で取り上げる…ということこそがとんでもない、異例中の異例なのだ。
しかし、だからこそこの町奉行は、なんなんだこの訴えは…と嘆きつつも「そこまでモメることを想定するほど、お上に訴えても勝てると見込めるほど、生活の基盤を賭けて勝つと踏めるほど、秘める必要のある夢とは…いったいどんなものなのだ…!?」と、興味を持ってしまったのではないか。
なぜか絶対に捏造しない男は、絶対権力者である町奉行にすら「見てまへんのです」と突っぱねる。
町奉行がダメなら今度は江戸城で老中や将軍、また朝廷に呼び出されて関白鷹司公とか時の帝の聴聞を受ける…という展開にはなぜかならず、いきなり超常の存在、「天狗」が登場する。
天狗は人間の公権力の横暴から男を救い出したが、人間の価値観に依拠せず天狗基準で怒り出し、八つ裂きにしてでも聞き出すぞこのやろう…と凄んでくる。ああ、言わないとダメだ…だけど見てないし…ああ殺される…となって、それじたいが夢だった!というオチになるのだが…。
全然、納得がいかないのである。
夢を言わない、見ていないからと突っぱねる男が、嫁→隣の男→大家→町奉行→天狗と、相手をどんどん大きくしていったというこの話、そもそもいったいどこからが「夢」なのであろうか。
もしかすると最初に嫁に起こされた、それじたいがまだ、夢の中での出来事だったのかもしれない。
男は、二度起こされる。
「見てない夢は言わない」ということ自体が、夢の中でしかなし得ない、この男にとっての「貫き通す意地の象徴」だったとしたら、普段(つまり嫁とも誰とも喧嘩などしない)の日常の、鬱憤が、そういう形で夢に現れたということになる。
そう考えると、町奉行から上の存在(江戸の将軍や朝廷の帝)などは、想像の埒外にあったであろうという一般庶民の、思考の幅が見えてくる。素朴な町人にとって、人生の中における最大権力者たる町奉行の次にはもう、「天狗」なのである。
もしかするとこれは、小さな発端が大ごとになっていく…というエスカレート型ではなく「小さな小さな、まどろみの中での超絶にかわいい、庶民の日常的な戯言」という、実にほんわかした意味を持っている噺なのかもしれない。
どんな夢だったんだろう。