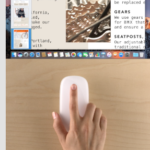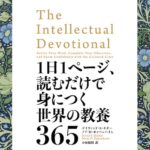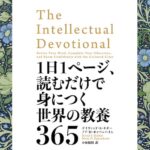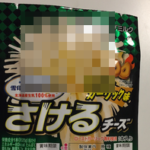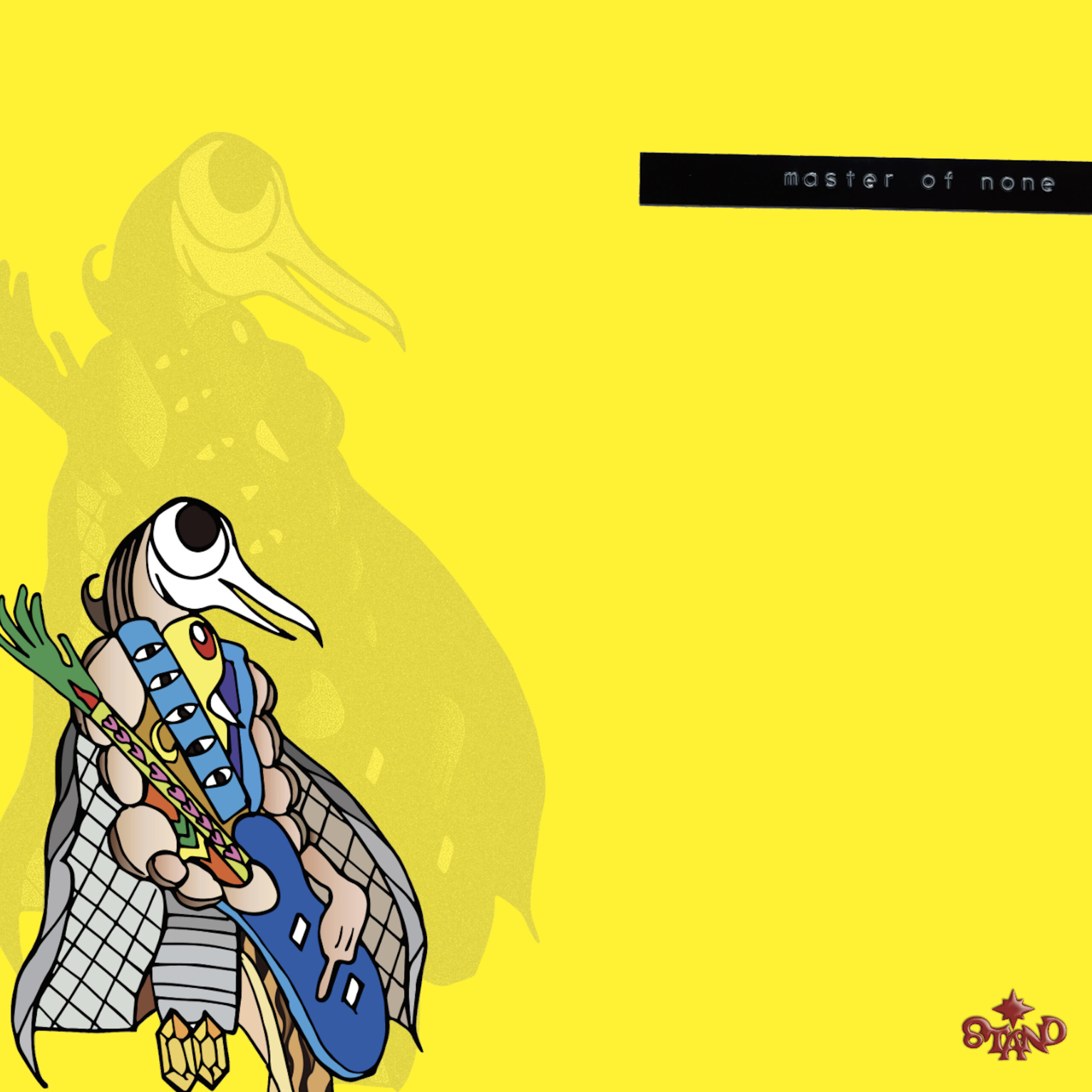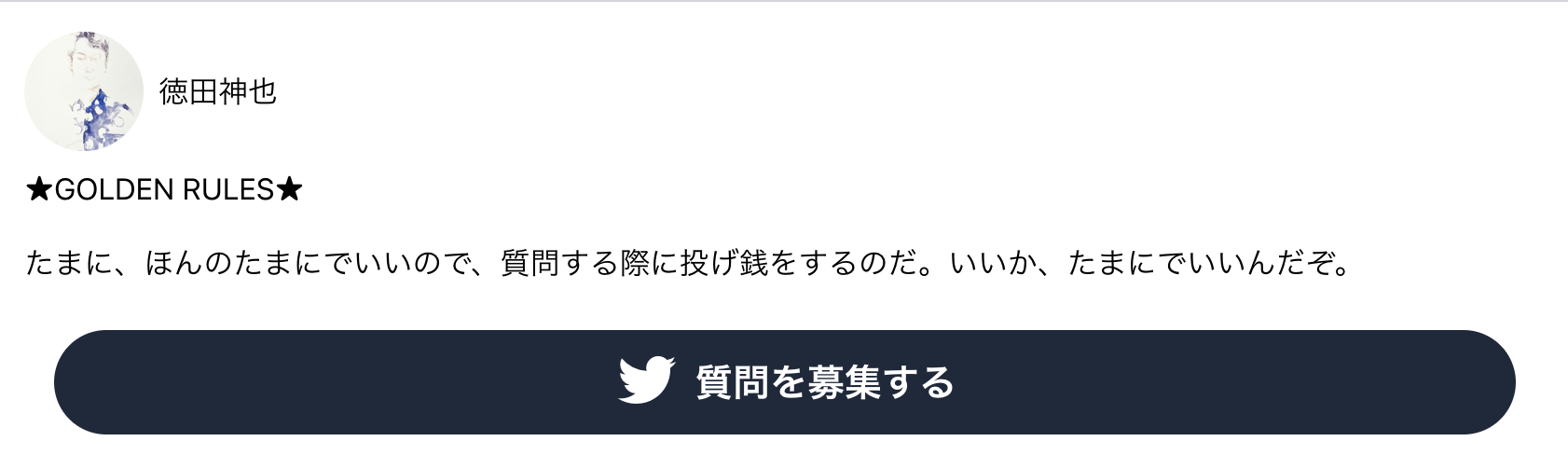自分にとっての社会は、成長するにつれてどんどんと、だんだんと大きくなっていく。奈良市にいた子供のころの自分には「あのレストランから向こうが大阪」だと、何となく信じていた場所があった。大阪から、親に車に乗せられて夜に通ると「ああ、奈良に帰って来た…」と安心していた。でも大人になって何度もそこを通って生駒山を超えていたとき、フと、え?ここをそう思ってたのか?と思い出して、わりと驚いた。そこはまだまだ大阪にはほど遠い、今は第二阪奈道路の入り口になっているあたりのことだった。小さい頃は家を出てそれくらいの距離を離れたら、もうかなり遠い別世界だと感じていたということなのだろう。小学校の「校区」というのも、子供の頃の社会性や行動範囲を決めていた重要な線引きだった気がする。この道路から向こうは「遠出」。このパチンコ屋から向こうは「遠出」。そうなんとなく感じていた。16インチもあったかどうかわからないくらいの自転車にまたがるしかない、子供にしか見えない、厳重なラインがそこにはあったのだ。中学生になると、隣の学区に入ればそこは「隣の中学校の縄張り」というような感覚が足された。やたら暴力的に解決することが生き様、というような田舎の粗暴な少年らの風潮に引きずられ、喧嘩をするために集まろうとする友人たちに、その中間地点くらいにある公園まで着いていったこともある。高校生くらいになると、それらの狭苦しい線引きが自分を守ってくれるための保護ラインだったのだとありがたく気づくし、だからこそその範疇を飛び出したくもなる。バイクや自動車でどこまでも行きたくなるし、どの社会に認められれる事が認められることなのだろう、とおぼろげに考えるようになる。自分の本当の心地のいい居場所は、どの社会にある、どのポジションなのだろう、と。友達の集まりだって社会だし、バイト先にはバイト先の社会がある。家庭にも社会はあるし、2人いればもうそれは社会かも知れない。いやひょっとすると自分自身の中にだって、社会はある。ニュースやメディアでは、「社会」と言えば格差社会とか社会的制裁とか、そもそも「日本社会」という特別な機構かシステムがあるかのように扱われている。でもそれらはただ大人たちが、うまく人格のない概念に責任転嫁をして何かをあきらめるために想定した、巨大な妄想なのではないだろうか。「社会が許さない」と言われれば、どこへ謝りに行けばいいのだろうか。「社会人」とは、学校を出れば自動的になるものなのだろうか。「会社人」と間違ってはいないだろうか。社会って、かなりおぼろげな、とりようによってはいかようにも変幻自在な、考えるだけ無駄な、刹那的結果論の集合体のようにも思える。何かを始めたり、何かに没頭しようとするとき、社会のことなんか気にしてたら、まずは指先さえぴくりとも動かせない。「社会が許さない」と言われたら「それはあなたが許したくないのでしょう?」と言い返してもいいかもしれない。社会なんかどうでもいい、ということではなく、社会に住まわせてもらってる意識は、「自分の中の社会」でまず自分がトップに立つことから始まる。自分が、「自分社会」のトップだ。そのトップとしての自信で、外界にある社会と対峙する。小さい頃見たあのレストランから向こうは、今は自分の中にある。社会を恐れることはない。社会は、自分で、いかようにも作れるものだからだ。